怒髪天 – 武蔵野犬式(2002)
- アーティスト名:怒髪天
- 発売日:2002年6月29日
THEイナズマ戦隊、ジャパハリネットと、2000年代半ば(筆者は16~17歳頃)は武骨で男臭いロックバンドにどっぷりの時代だった。
そして初めてと言っても良いかもしれないが、”好きなバンドが影響されたバンド”を聴いてみようと思ったのが怒髪天である。
THEイナズマ戦隊が常にアルバムのブックレットでスペシャル・サンクスとして挙げていたのがウルフルズと怒髪天であった。
気になる名前であった怒髪天は、調べてみるとメジャーで活動しているようで、当時は『握拳と寒椿』『桜吹雪と男呼唄』という2枚のミニアルバムをリリースした頃だった。
聴いてみると、イナ戦とはまた違ったアプローチで、リズム&演歌なるジャンルを標榜して、日本人によるロックを歌うバンドとして活動していた。どこか人間椅子と重なるところも感じて好きになった。
好きになると掘り下げずにはおれず、メジャーになる以前にインディーズ時代の作品が何枚もあると言う。最初に手に取ったのが2002年の『武蔵野犬式』(ムサシノドッグスタイルと読む)だった。
『握拳と寒椿』『桜吹雪と男呼唄』に比べれば、もう少し若者のロックンロールという感じで、当時の筆者にはよりしっくり来たアルバムであった。
その頃は、美しい音楽とか、綺麗なことを歌っている音楽はくそくらえだと思っていたので、怒髪天の楽曲・歌詞の世界観はとても惹かれるものだった。
「欠けたパーツの唄」とか「福音魂列車弐号」などストレートなロックも良かったが、個人的には「宿六小唄」「社会人のファイター」など社会や生き方に対する不満のようなものを歌った曲に惹かれた。
ようやくこの頃、自分の中で言いようのないモヤモヤは、自らの生き方や将来、そして社会に対する違和感などと結び付いていくようになっていたように思う。
怒髪天の楽曲は、社会に対する風刺めいた歌詞でありつつ、そこにユーモアがあり、それゆえに皮肉たっぷりで痛快だった。
その後の怒髪天は、そうした社会に対する斜に構えた雰囲気はもう少し俯瞰したものになり、中年に入ったことでカラッとした音楽性に変化していった。
だが当時のモヤモヤしていた筆者にとっては、『武蔵野犬式』の頃の怒髪天が1番しっくり来たのだった。
奥村愛子 – 万華鏡(2005)
- アーティスト名:奥村愛子
- 発売日:2005年2月23日
2005~2006年頃、大学受験も近くなってきた筆者ではあったが、音楽的な関心がより広がりつつある年代だった。タワーレコードだったか、フリーペーパーの新人紹介で奥村愛子氏が出ていたのだった。
いわゆる昭和歌謡のメロディと、おしゃれな音楽が融合した、というような文言が書かれていたようなあ気がする。クレイジーケンバンドが好きだったこともあり、関心を持った。
当時はメジャーデビューして、『万華鏡』というアルバムが入手しやすかったので聴いてみた。耳に飛び込んできたのは、デビュー曲「いっさいがっさい」であった。
スカのリズムに乗せつつ、昭和歌謡的なメロディが乗るのがとてもカッコ良かった。その少し前にEGO-WRAPPIN’というバンドが流行り、それに近い感じもするが、もっとオシャレな感じがした。
順に聴いていくと、もっと音楽的な幅が広いのを感じた。「冬の光」のじっくり聴かせるバラードや「フリージア」の美しいメロディと優しい歌唱にも惹かれた。
聴いていると”奥村愛子節”のような曲と、少し違う色合いの曲があることに気付いた。作曲が彼女自身のものと、提供によるものがあると知った。
彼女の曲は、毒気もありつつオシャレで心地好いメロディなのであり、単に昭和歌謡リバイバルで括られるものでもないと感じたのだった。
彼女の独特の個性に当時も惹かれたように記憶しているが、続く『虹色ナミダ』はどうも彼女の望む方向性と違う方に進んでいったので違和感もあった。(良い曲も多数入ったアルバムではあるが)
ほどなくしてメジャーから離れ、インディーズで活動することになり、『ラヴマッチ』(シングル盤)を通販で注文して購入したのをよく覚えている。(通販でわざわざ買ったのはこの時が初めて)
再び『万華鏡』の頃の作風に戻っていて、とても安心したものだ。それ以降、ずっとマイペースに活動している奥村氏であるが、そんな活動の在り方も含めてファンである。
陰陽座 – 臥龍點睛(2005)
- アーティスト名:陰陽座
- 発売日:2005年6月22日
人間椅子が好きで音楽を掘り下げ始めたのであるが、随分と違うジャンルの音楽へと興味が広がっていったのが、中高生の時代であった。
この頃の人間椅子と言うと、後藤マスヒロ氏が脱退しナカジマノブ氏が加入して、”新生人間椅子”となっていたが、音楽性がやや迷走していた時代であった。
子どもながらに、あまり良い時期ではないのだろう、とは思っていた。そんな時に耳に入ってきたのが、陰陽座の「甲賀忍法帖」であった。
陰陽座と言えば、人間椅子も出演してVHS化された『涅槃神楽』というイベントに出ていたバンドだ、と筆者の中では記憶されていた。しかしどんな音楽のバンドなのか知らないままだった。
2005年にテレビアニメ『バジリスク 〜甲賀忍法帖〜』の主題歌となった「甲賀忍法帖」が好評となり、ヒットチャートに上がって来ていたのだった。
かなりポップで歌謡曲のようなメロディに驚いたのを覚えている。名前からしてもっと恐ろしい雰囲気の音楽なのかと思ったら、耳馴染みやすいメロディだった。
ひとまず興味を持って聴いたのが、アルバム『臥龍點睛』である。アルバム1曲目、「靂」が始まると、思いのほかハードなリフが始まり、男性ボーカルが入って来てまた驚いた。
楽曲によってはかなり人間椅子の影響も感じる曲があるし、一方で「龍の雲を得る如し」「月花」「蛟龍の巫女」などはもっとメロディアスなメタルであると感じた。
圧巻だったのは3曲続きとなっている「組曲「義経」」であった。疾走感のあるヘヴィメタルから、おどろおどろしくも美しいメロディや展開の多さなど、聴きどころ満載の楽曲である。
この当時の陰陽座はまさにブレイク中であり、勢いに乗っている感じがあった。アルバム全体からもそうしたパワーを感じたものである。
その後にリリースされたベスト盤『陰陽珠玉』と併せて擦り切れるほど聴いた記憶がある。また当時から公式サイトにライブのセットリストが掲載されていたのが陰陽座だった。
セトリの順に並べて聴いたり、自ら疑似ライブセットリストや自分用のベストを作ったりと、プレイリスト作りに没頭したのも陰陽座の楽曲だったのが思い出である。
エレファントカシマシ – 東京の空(1994)
- アーティスト名:エレファントカシマシ
- 発売日:1994年5月21日
怒髪天を熱心に聴いていた頃、参加したアルバムの中でエレファントカシマシのトリビュートアルバム『エレファントカシマシ カヴァーアルバム 花男 ~A Tribute To The Elephant Kashimashi~』を見つけた。
怒髪天は「男餓鬼道空っ風」という、怒髪天の曲のタイトルでも違和感のない楽曲をカバーしているとのこと。音源を試聴してみると、怒髪天の曲と言われたら気付かないくらいだった。
エレファントカシマシと言えば、小学生の頃に「今宵の月のように」がヒットしていたことぐらいしか知らなかったのだが、どうやら全然違う音楽性らしい、ということで途端に興味を持ったのだ。
さっそく「男餓鬼道空っ風」の入っている『東京の空』から聴いてみると、もう自分の求めていた音楽が全てここにあった、というくらいの衝撃度であった。
男臭くてヤケクソな雰囲気、それでいてカラッとした心地好さまで感じさせるアルバムで、ひと頃は本当によく聴いていたアルバムだった。
「この世は最高!」「甘い夢さえ」「男餓鬼道空っ風」などのヤケクソ感、「誰かのささやき」「明日があるのさ」などの優しさ、「東京の空」「暮れゆく夕べの空」などの凛とした佇まい。
全てが素晴らしく、男と言う存在、そして男のロマンとでも言うべきものが全て詰まっているようなアルバムだと思った。
10代の終わり、反抗期からそれを抜け始めて、何とも物寂しさが強かったこの当時、エレカシの音楽は筆者の心に入り込み、もうどっぷりだった時代である。
とりわけエピックソニーに在籍した時代のアルバムは、どれも擦り切れるほど聴き尽くした。荒々しいサウンドながらも、悲しみや怒りの表現の純度の高さに感動したのをよく覚えている。
エレカシを聴きながら、ぼんやりと過ごしていたために、大学受験には失敗し浪人することになってしまった。
しかしその後、「俺たちの明日」で奮起したエレカシと足並みを合わせるように成績が伸び、試験の日には「ファイティングマン」に勇気づけられた。
そして合格の発表を見た時には「桜の花、舞い上がる道を」が流れていた、というエレカシとともにあった受験時代については、以下の記事に書いている。
浜田省吾 – FATHER’S SON(1988)
- アーティスト名:浜田省吾
- 発売日:1988年3月16日
2005年に浜田省吾氏の久しぶりにストレートなロックアルバム『My First Love』、2006年にはベスト盤『The Best of Shogo Hamada vol.1&vol.2』がリリースされていた。
父親が浜田氏の音楽が好きで、家族で過ごす時には一緒に聴くこともあった。エレカシや怒髪天など、尖がった音楽を聴いていたので、いくぶん距離は置きつつ、その良さも認識し始めていた。
そのバラードやポップスが多いベスト盤の中で、「Darkness in the heart – 少年の夏」と言う楽曲が、やや毛色が違うと言うか、浮き出て聞こえてきたのだった。
マイナー調のロックであり、こういうタイプの曲もあるのかと思って、収録されているアルバム『FATHER’S SON』を聴いてみることにしたのだった。
家族と一緒に暮らしていた時には、それほどこのアルバムを聴いた記憶はないのだが、大学進学のために上京し、初めての一人暮らしをしてから、このアルバムが沁みるようになった記憶が強い。
このアルバムと1990年の『誰がために鐘は鳴る』の2枚が、とにかく沁みて仕方がなかったのである。
自分自身の境遇とそこまでリンクした訳ではない。しかし浜田氏のボーカルは、寂しい心に寄り添ってくれるような、不思議なパワーがあるのだ。
後から考えてみれば『FATHER’S SON』あるいは『誰がために鐘は鳴る』は、浜田氏の作品の中でも内省的な色合いが強く、曲の世界に浸れるようなアルバムだった。
現実の筆者は大学生活が始まり、慌ただしさと新鮮さでいっぱいではあったが、一人になると寂しさがやって来た。そんな筆者にとって、浜田氏の音楽・歌は癒しになったのである。
『FATHER’S SON』はサウンド面でもやや異色で、当時のバブリーな雰囲気もしつつ、ヘヴィメタルすら感じさせる歪んだギターサウンドも特徴的だった。
ハードな曲とバラードのバランスも絶妙で、音楽的にもとても好みのアルバムなのである。
まとめ
今回は筆者が10代、あるいは思春期の頃に擦り切れるほど聴いたアルバムを10枚紹介した。
10代より前に聴いた曲(こちらの記事に書いた)は、そのアーティストが好きになるというより、もう少し深いところ、ジャンルやリズム、音楽の方向性のようなものの根幹だった。
10代に好きになった音楽は、まさに好きなアーティストであり、当ブログで最も取り上げているバンド・ミュージシャンが並んでいることにお気づきになるだろう。
音楽ジャンル的に見れば様々であるが、あえて共通点を見つけるとすれば、現役でずっと続けているバンドが好きである、ということである。
一度解散を経験したジャパハリネット、メンバーの脱退・解雇があったTHEイナズマ戦隊・怒髪天、メンバーの交代があった人間椅子など、それぞれ事情はあるがバンド自体は現在も続いている。
思うに、好きになったバンドは音楽に対する思いの純度が高いように思える。もちろん商業的な成功も重要ではあるが、あくまで好きな音楽を貫いた結果としての成功である。
そうした一貫性や信念の強いバンド・アーティストに惹かれるのだ。
※音楽的好奇心が薄れる”音楽的老化”が起きる人・起きない人の違いとは? – ”音楽好き”の違いから考える
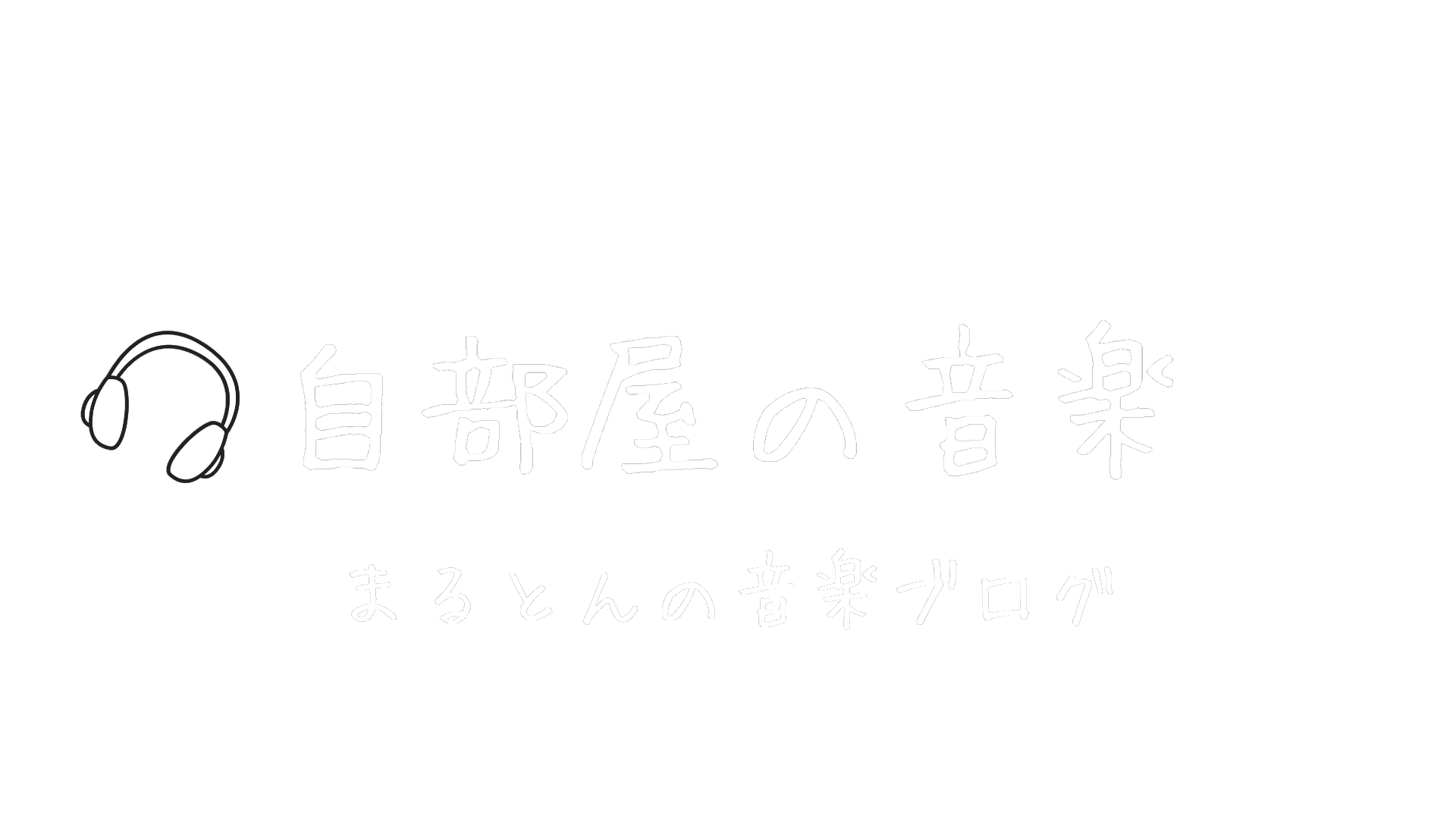







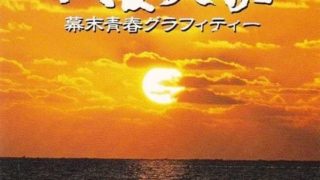
















コメント