10代の頃に聴いた音楽が最も好きな音楽になる、とはよく言われたものである。実際に調査も行われているようで、11~14歳頃に聴いた音楽の影響が大きいそうだ。
当ブログ「自部屋の音楽」の筆者も、10代の初めから徐々に好きな音楽ができ始めていった。それまでは好きな”曲”だったのが、好きな”アルバム”が出てきたのも10代に入ってからのことである。
今回は筆者が10代の頃に擦り切れるほど聴いた(CDなので擦り切れはしないが)アルバムを10枚にまとめて紹介したい。
前回紹介した思春期以前に好きになった楽曲の記事と併せて、筆者の自己紹介記事としてお読みいただければと思う。
「自部屋の音楽」筆者が10代の頃に擦り切れるほど聴いたアルバム10枚
筆者が10代の頃に聴いたアルバムと言うことだが、筆者が10代だったのはおよそ1998年~2007年の頃である。
そして当ブログでも書いている通り、2000年にリリースされた人間椅子の『怪人二十面相』を好きになって以来、人間椅子が好きになったのが、音楽自体をより深めていくきっかけとなった。
10代前半頃(~2003年頃)はまだ親の影響が強く、その当時親が聴いていたものを好きになっていた。10代後半に入ると、徐々に自分の好きなものを追求するようになっていく。
その中で、同時代ではない過去のアルバムも聴き始めるようになっていった。
今回は筆者がおよそ聴いてきた順に沿ってアルバムを紹介する。筆者の音楽的な好みの変遷などが分かりやすくなると思う。
またアルバムそのものの客観的なレビューと言うよりは、そのアルバムと自分自身の関わり、そして当時そのアルバムに対して感じていたことを中心に書くこととした。
人間椅子 – 見知らぬ世界(2001)
- アーティスト名:人間椅子
- 発売日:2001年9月21日
筆者が音楽に(ロックに、とも言える)より深く興味を示したきっかけが人間椅子だった。両親が当時喜んで聴いていた『怪人二十面相』(2000年)が好きになって聴いていたのだった。
当時、筆者は12~13歳の頃だった。
過去の作品ももちろん聴き漁っていたが、ついに新譜がリリースされることとなった。筆者にとっては、初めての人間椅子の新譜であったし、新譜を楽しみに待つ体験自体が初めてだった。
タイトル、アルバムジャケット、曲目が告知になると、『怪人二十面相』のような不気味な雰囲気ではなく、どこか幻想的で落ち着いた雰囲気なのかな、と思ったのをよく覚えている。
最初に聴いた時の「死神の饗宴」の衝撃は忘れられない。そして聴き進めていくと、明らかに不気味な人間椅子ではなく、何だか綺麗な曲が多いのに驚いた。
当時、かなり賛否両論あったアルバムだったが、筆者は不思議とすんなりと受け入れられることができた。
今思えば、それまでの人間椅子とはかなり色合いが異なるものの、良い曲が並んでいるアルバムだったからなのだろう。
特に好きだったのは、「さよならの向こう側」から「人喰い戦車」の流れだった。どちらも美しいメロディを持ちつつも、正反対の世界観が並び立つのが人間椅子の面白いところである。
当時、リフもののハードロックばかり追いかけていた筆者にとって、もっとポップなロックのスタイルがあることを教えてくれたのが、このアルバムだった。
さらにはギターを弾き始めて、ようやくリフを弾くことができるようになった頃だった。不気味なリフとは異なる、和音ベースのフレーズや展開など、大いに勉強になったものである。
もう1つ筆者にとっての初めての体験だったのが、本格的なロックのコンサートへの参加であった。音が大きいのではないか、と始まる前は少し不安になったりしたものである。
しかしライブの幕開けである「見知らぬ世界」が始まった瞬間、音の洪水(当時は今よりずっと音量が大きかった)に飲み込まれていく快感を感じた。
ライブで「見知らぬ世界」を始め、アルバム曲を聴いたことで、さらに好きになって繰り返し聴いた思い出のアルバムである。
※【アルバムレビュー】人間椅子 – 見知らぬ世界 (2001) 転換期、現在の人間椅子へとつながる道
氣志團 – 1/6 LONELY NIGHT(2002)
- アーティスト名:氣志團
- 発売日:2002年4月11日
人間椅子にはどっぷりハマりつつ、他に好きなバンドはなく、あとはもっぱら当時のJ-POPを聴いている、という感じだった。
録画して観ていたTBS系列「COUNT DOWN TV」で、リーゼント&学ラン姿の不思議なバンドに惹きつけられることになる。それが氣志團との出会いだった。
おそらく最初に知ったのは「One Night Carnival」「黒い太陽」という2曲だったと思う。まだ”流行りかけ”ぐらいのタイミングで、次にブレイクするバンド、という感じの扱いだった。
いずれの曲も、何とゾクゾクする良いメロディなのだろう、と感動したのだった。見た目の怖い雰囲気とは裏腹に、歌っているメロディはとても美しいのだった。
さっそく『One Night Carnival』のシングル、そして1stアルバムだと言う『1/6 LONELY NIGHT』を入手して、ずっと聴いていたものである。
氣志團がよく使うこのメロディというか進行は一体なんだ?と思っていたが、どうやらベースのルートだけが下がっていく進行が、とても心地好いのが分かってきた。
当時は名前を知らず「半音下がり」と呼んでいたが、いわゆるクリシェと呼ばれる進行のことだ。
「One Night Carnival」のサビではメジャーコードのクリシェが、「黒い太陽」のサビではメジャーコードのクリシェから、マイナーのクリシェへとコンボになっている。
後々はそれが定番の進行であると知っていくのだが、このクリシェ進行の心地好さを最初に知ったのが氣志團だったので、とても思い出深いのだ。
またパンクっぽい音楽で好きになったのも氣志團が初めてだった。ただヘヴィメタル的なものを通ってきている感じもするので、筆者にとっては入りやすかったのだと思う。
しかも氣志團はもともとインストのバンドだったようで、当時もっと音源を聴きたくて、CDショップで見かけた『房総与太郎路薫狼琉』なるミニアルバムを買った。
彼らのインディーズ時代の作品で、確かにメロディはなかったが、「國道127号線の白き稲妻」(アルバムには新録された)が後のメロディ路線を予感させるものであった。
続く2003年の『BOY’S COLOR』も同じく擦り切れるほど聴いたアルバムであるが、この作品を境に、氣志團の猛烈に良いメロディはやや枯渇していったように思える。
あそこまで良い曲を作り続けるのは難しいのだろう。しかし良い時代の氣志團をリアルタイムで聴けたのはとても良かった。
クレイジーケンバンド – 777(2003)
- アーティスト名:クレイジーケンバンド
- 発売日:2003年6月25日
氣志團を聴いていた頃とほぼ同時期、父親が面白いバンドがあると喜んで聴いていたのがクレイジーケンバンドであった。
ちょうど「GT」がシングルになったり、アルバム『肉体関係』が一部の音楽マニアの間で話題になったりしながら、徐々にクレイジーケンバンドの知名度が上がりつつあった時期だった。
まだ「タイガー&ドラゴン」がドラマ主題歌となる以前だったが、テレビ番組への出演が増えるなど、確実に人気が高まっていた。
そんな上昇気流に乗っている中でリリースされたのがアルバム『777』であった。筆者はおそらくこのアルバムを最も好んで聴いていたような気がする。
前作の『グランツーリズモ』は昭和歌謡やロックンロールなど、初期のクレイジーケンバンドの色合いが強かったが、『777』では少しずつ音楽性が変化を始めていた。
そんな変化が、筆者にとっては全く新しい音楽の扉を開いてくれたアルバムとなったのだ。
具体的に言えば、R&Bやソウルのコード進行などをこのアルバムで学んだ。「7時77分」のコード進行など、全く聴いたことがないもので非常に新鮮だった。
夏の歌でサウンドはとてもゴージャスながら、どこか宇宙的な感じがするのも少年ながらに面白かった。
アルバム前半はソウルっぽい雰囲気で固められていて、後半は良いメロディが連発するのもとても気に入っていた。
「涙のイタリアン・ツイスト」「金龍酒家」「横顔」などはたまらなく好きな曲だった。(後から知ったのは「涙のイタリアン・ツイスト」「横顔」はかなり昔に作った曲だった)
それでいてシン・ジュンヒョンのカバー「美人」はハードロックであり、人間椅子が好きだった自分にもすんなり入る曲だった。
ジャンル的にごった煮だった当時のクレイジーケンバンドの雰囲気が残っている、ほぼ最後のアルバムと言っても良いかもしれない。
そして筆者にとっては、全く未知の音楽の扉を開いてもらったアルバムである。
THEイナズマ戦隊 – 馬鹿者よ大志を抱け(2004)
- アーティスト名:THEイナズマ戦隊
- 発売日:2004年10月20日
深夜に放送していた日本テレビ系列のコント番組『メンB』を家族と録画して観ていた。当時はお笑いブームの最中で様々なお笑い番組があったが、一風変わったコント番組だった印象がある。
変わった要素の1つが、エンディング曲をバンドが演奏するというものだった。そこで毎回持ち歌を披露していたのが、THEイナズマ戦隊であった。
見た目には武骨で男臭い雰囲気である一方、そのメロディの良さに一気に引き込まれた。「パーダラ・ブギ ~後悔するにゃ若すぎる~」「雨上がり」、そして「応援歌」と名曲の宝庫だった。
すぐさま、当時リリースされていたアルバム『勝手にロックンロール』や、インディーズでリリースされていたシングル・ミニアルバム等も買い漁ったのだった。
どうやら初期に遡るほど、当時流行っていた”青春パンク”の流れに組み込まれていたようだが、”ロックンロール”を頑ななほど主張する姿勢とか、やや異質な感じがしていた。
そしてとにかく美しいメロディこそ、イナ戦の魅力であると思っていた。
『メンB』への出演は終わったイナ戦だったが、それにより知名度は上昇し、勢いに乗り始めた中でリリースされたのが2ndアルバム『馬鹿者よ大志を抱け』だった。
当時はリリース前にレコード会社のサイトで試聴できる場合があり、このアルバムも試聴して名盤の予感しかしないと思っていた。
実際に購入してからも、とにかく好きで聴きまくっていたと思う。前作『勝手にロックンロール』の粗さが、より洗練された感もあり、前作以上に美しいメロディが前面に出ていた。
特に後半の「後悔するなら反省を」からの、怒涛の名曲の連続は何度聴いても鳥肌ものだった。とりわけ「月明かりの下」のメロディ・サウンドの美しさに惚れ惚れしていた。
アルバム最後には、ボーナストラックとして「応援歌」が再び収録されていたが、これも蛇足と言う感じが一切なく、アルバムを見事に締めてくれるものであった。
歌詞の内容と当時の筆者がそこまでリンクはしていなかったが、今改めて聴いてみると興味深い歌詞が多いようにも思える。
10代を過ぎ、20代に入った頃に感じる、「何だか歳をとってしまった」と思う感覚がここには描かれている。もちろん20代など、若さのピークではないか、と後になれば思うものである。
しかし10代(あるいは子どもとして扱われた年代)から、妙に歳をとってしまったような感覚に襲われる瞬間があるのも経験がある。
そうした悲しみ・寂しさのようなものが、リアルに描かれたアルバムだと思う。
その後のイナ戦は『熱血商店街』『未来の地図』など良いアルバムもあったが、個人的には本作が最高傑作だと思っている。
ジャパハリネット – 東京ウォール(2005)
- アーティスト名:ジャパハリネット
- 発売日:2005年4月20日
THEイナズマ戦隊を聴いていた流れで、青春パンクのオムニバスを聴くことがあり、その中にジャパハリネットも入っていたのだった。
そしてヒットチャートにもジャパハリネットの曲があるのは何となく知っていたものの、最初はそこまで惹かれていなかった記憶がある。
最初に引き込まれたのは『遥かなる日々』がテレビから流れた時だった。耳に残るメロディでそこからジャパハリネットを聴くようになっていった。
イナ戦よりもさらに荒っぽい演奏だった印象ではあったが、高校生だった筆者はジャパハリネットの音や歌詞などと、絶妙にマッチしていたのだった。
と言うのも、反抗期だった当時は、何とも言いようのない怒りとか悲しみが湧いてくることがあった。ジャパハリネットの音楽はそれを良い方向に引っ張ってくれるような感じがした。
ジャパハリネットの歌詞はあまり具体的なことは書かれていないのが、むしろそのモヤモヤをそのままに、エネルギーだけ変えてくれるような、そんな快感があったのだった。
「遥かなる日々」「帰り道」と、これぞ青春パンク路線の楽曲が続いた中でリリースされたアルバム『東京ウォール』は、思っていたのとはずいぶんと違う意外な作品だった。
『東京ウォール』発売のテレビCMでは、新たな楽曲「対角線上のアリア」のMVが流れていたのだが、それが全く今までとは異なる肌触りだったのである。
アルバムを通して聴いてみても、明らかに青春パンク路線から脱却しようとしたのが分かる作品になっていた。
そのため賛否両論あった作品ではあったが、個人的には音楽としてとても好きな作品だった。
言ってしまえば、それまでのジャパハリネットに比べて音楽的にクオリティの高い作品になっていたのである。バンド主体なのは変わらずも、サウンドにも彩りがあり、プロの目が入っている感じだった。
それでいて、まだジャパハリネットらしさは失われておらず、シングル曲はもちろん「聖戦パラドックス」「Tokyo Wall」など、勢いのある楽曲も多かった。
何より、後の作品に比べれば、ジャパハリネットがバンドとして突き進んでいる感じは、本作までであったようにも思える。
しかし「音楽とはこういうものだ」「これが音楽的に良いのだ」と言うのは頭では分かっていながら、ジャパハリネットはこれで良いんだろうか、ということを考えていた気もする。
最初に書いたように、筆者がジャパハリネットに求めていた(良さだと思っていた)点は、音楽的な魅力と言うより、エネルギーやパワーのようなものだった。
プロの視点からすれば、それだけでは長続きしないのは目に見えていたので、音楽的に価値あるものを、と言う方向になるのだし、でもジャパハリネットらしさはどこに行くのだろうと思ったりした。
そんな葛藤はアルバムの作風にも表れているように思えた。前作『現実逃走記』が地元の愛媛カラーを感じさせる、どこか牧歌的で穏やかな感じがしていた。
一方の本作は東京のざらついた、ドライな感じがサウンドからも伝わって来る。『東京ウォール』という、東京が立ちはだかっているかのようなタイトルも、そのまま表現されている。
東京進出なのか、愛媛で活動するのか、そうした分裂も生じ始めていたと推測されるが、色々な意味でジャパハリネットが分裂していく感じが漂いつつ、作品としてはとても良いアルバムである。
※【ジャパハリネット】解散前までの5枚の全アルバムレビュー – ”ジャパハリらしさ”とは何か?
次ページ:後半の5枚に続く
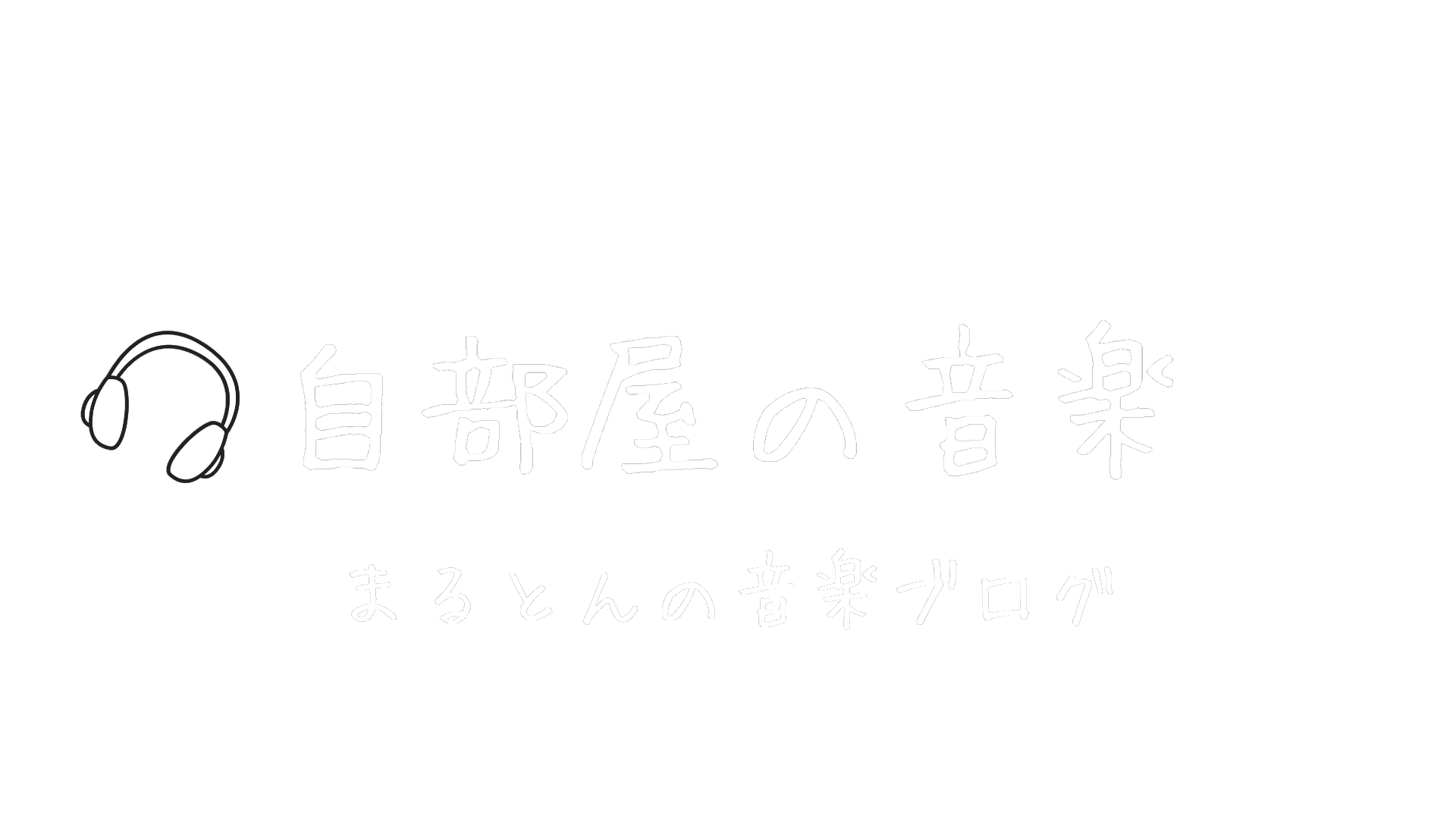






















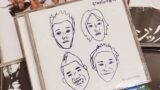


コメント