バンド生活三十五年を迎えた人間椅子の楽曲は、あまりに独自な世界観・音楽性を持つものであり、海外でも評価を得るようになっている。
人間椅子の音楽性を非常に簡単に述べれば、70年代のブリティッシュハードロックに、日本の文学的な言葉を乗せて歌う、というものである。
そうした人間椅子の音楽性は、様々な楽曲を総合的に解釈することで見出されるものではあるものの、とりわけその独自性を語る上で重要な楽曲が存在する。
今回の記事では、人間椅子の独自性を語る上で外せない重要な楽曲を15曲に絞って紹介することとした。
いわゆるオールタイムのベスト選曲とはやや異なり、人間椅子自身の音楽性を形成する上で指針となったのではないか、と思われる曲を選んでみた。
唯一無二の音楽性を語る上で外せない人間椅子の15曲
人間椅子の唯一無二の音楽性は、いったいどのように形成されたのか。それは彼らが影響された音楽もあろうが、彼ら自身が作り上げた楽曲から感じることができる。
そしてとりわけ初期の楽曲の中に、既に人間椅子の独特な音楽性を感じることができるだろう。今回そうした独自性を感じられる楽曲を選ぶにあたり、人間椅子の時期を分けて考えた。
ドラマーの在籍時期に応じて、大きく分けて以下の3つの時期に分けて考える。
- 上館徳芳・土屋巌期(『羅生門』を含む)
- 後藤マスヒロ期
- ナカジマノブ期
これらの時代の中から、人間椅子の独自性を考える上で重要な時代は、”新たな音楽性が形成された”時代であると考える。
そうすると、圧倒的に1.の時代が多く、加えて3.を取り上げることになるだろう。
1.の時代は、デビュー前からメジャーとの契約が切れて低迷期の入り口の時代と言うことである。人間椅子の音楽性の骨子は、およそこの時代までに出来上がっていると考える。
メジャーデビュー前後は、当然ながら人間椅子の怪奇的な世界観を固める時代で、1995年の『踊る一寸法師』以降はメジャーでの制約がない中で、より自由に楽曲が作られる時代になった。
またナカジマノブ氏加入後の人間椅子は、それまでと異なるタイプのドラマーと新たな人間椅子を作る必要があった。
そして年齢を重ね、ギター・ボーカル和嶋慎治氏の心境の変化とともに、人間椅子の人気が高まって状況も変わった。こうした点から、1.と3.の時代から結果的に選曲するに至った。
後藤マスヒロ氏在籍の時代は、それまでの音楽性をさらに深めた時代で、ある意味最も充実した時代だったが、既に出来上がった音楽性を広げる段階と捉え、今回は選曲に入らなかった。
各楽曲から見える人間椅子の独自性について述べるのと同時に、その前後で近い傾向を持つ楽曲も併せて紹介している。
鉄格子黙示録
- 作詞・作曲:和嶋慎治
- 収録アルバム:『人間失格』(1990)、『人間椅子傑作選 二十周年記念ベスト盤』(2009)
和嶋氏が高校時代に作曲した人間椅子の原点の1つと言っても良い楽曲である。不気味な前半部はインストであり、疾走感のある後半で歌が出てくると言う展開になっている。
それまではラブソングを中心に作曲をしていた和嶋氏だったが、UFOのアブダクション体験を経て、作風がガラリと変わってしまったことが顕著に窺えるのがこの曲だ。
実は大事なことは、時代的に考えると、ベース・ボーカルの鈴木研一氏による熱心にBlack Sabbathの啓蒙活動を受ける前に作られた曲であるということである。
つまり、Black Sabbath(あるいはBudgieなど)に影響されたヘヴィな70年代ハードロックを意図的に志向する以前に、奇しくもそれと同傾向の楽曲を作っていたと言う事実である。
それは和嶋氏の中にやはりBlack Sabbath的な精神性があったとも言えるし、自分の中から出てきた、最も初期衝動の楽曲であるとも言える。
それゆえ、”ハードロックかくあるべし”という様式には全くとらわれておらず、自由に作られている。和嶋氏の原点はやはりここにあるように思われる。
和嶋氏は作風に悩んだ時、いつも枠を取り外して作った曲が代表曲になっている。それは後の「相剋の家」や「どっとはらい」のような狂気を感じさせる楽曲にも繋がっている気がする。
ハードロック的指向性が明確化する前に作られた、和嶋氏の原点中の原点、様式に全くとらわれていない自由さがここにある。
陰獣
- 作詞:和嶋慎治、作曲:和嶋慎治・鈴木研一
- 収録アルバム:『現世は夢 〜25周年記念ベストアルバム〜』(2014)、『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)など
「鉄格子黙示録」が枠のない曲だとすれば、この「陰獣」は人間椅子という枠組みを極めて明確に示した楽曲と言える。
ご存じの通り、テレビ番組『三宅裕司のいかすバンド天国』(通称イカ天)で披露され、世に人間椅子の名前と、独特な世界観を知らしめた楽曲だ。
Black SabbathとBudgieそれぞれの不気味さや湿り気を融合させ、そこに文学作品の世界観を借りて楽曲を完成させるという、人間椅子の定番の方法論をここで確立させた。
しかも、もともと7分ほどあった楽曲を、よりコンパクトに人間椅子の魅力がテレビで伝わるように短縮した、という実は戦略的に作られたバージョンなのだ。
それゆえ、筆者としてはこの曲自体は、後の楽曲の原型としての意味合いの方が強く、”切り込み隊長”と言うのか、”広報担当”と言うのか、そう言った位置づけの楽曲になっていると思う。
和嶋氏が作り出したメインリフのようだが、後に鈴木氏がこの路線を受け継いでいる。
「陰獣」の路線を極めたのが、「死神の饗宴」であろう。その後も「東洋の魔女」「洗礼」など、人間椅子らしい渋みのあるヘヴィさの原点には「陰獣」がやはりある。
人面瘡
- 作詞・作曲:和嶋慎治
- 収録アルバム:人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)など
和嶋慎治・鈴木研一と言う2人の個性が融合して生み出されるのが人間椅子の音楽であるが、それぞれの個性が際立つタイプの楽曲もある。
初期の楽曲で和嶋氏の個性が際立つのが「人面瘡」であろう。もとからヘヴィなハードロックを志向していた鈴木氏とは異なり、和嶋氏はもう少し違う方面のロックの影響を感じる。
それはブルーステイストのロックであり、そこにプログレ風味・サイケデリック風味が加わったような音楽性である。「人面瘡」はまさにそうした音楽性を有している。
そしてロックンロールテイストの楽曲に、あえて残酷で不気味な歌詞を乗せると、より不気味さが際立つと言うものだ。
こうした路線は、後に「天国に結ぶ恋」「九相図のスキャット」などが猟奇的な歌詞の路線で受け継がれ、ヘヴィな楽曲の間にあって良い味付けになっている。
また「人面瘡」は江戸時代風の楽曲の原型としても後に影響を与え、「品川心中」などにも通じる世界観である。
針の山
- 作詞:和嶋慎治、作曲:Tony Bourge, Burke Shelley, Ray Phillips
- 収録アルバム:『人間失格』(1990)ベスト『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)など
初期の人間椅子は、オリジナル曲とともにカバー曲にオリジナル詞を乗せることも行っていた。Metallicaがカバーして有名になった、Budgieの「Breadfan」にオリジナル詞を乗せたのだ。
「Never Never」という繰り返しのフレーズと、種田山頭火の「分け入っても分け入っても青い山」がリンクしたようで、海外ヘヴィメタルと日本文学が見事に融合した。
そしてテーマは海外が”Hell”ならば日本は”地獄”であろうと言うことで「針の山」となっている。
この曲はカバーでありながら、人間椅子の歌詞・世界観を作り上げる上で非常に重要な役割を果たしたと言えるだろう。
海外のヘヴィメタルが反キリスト的な世界観ならば、日本で言えば仏教的な地獄の世界観と置き換えて、独自の歌詞の世界観を作り上げた。
そうした意味では、単なるカバーではなく、「針の山」と言う曲自体、人間椅子の曲と言っても良いくらいである。
また鈴木氏は後に”地獄シリーズ”と題して、地獄をテーマにした楽曲を多数作ることになっていく。
りんごの泪
- 作詞:和嶋慎治、作曲:鈴木研一・和嶋慎治
- 収録アルバム:『人間失格』(1990)、『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)など
和嶋氏らしさが際立つ「人面瘡」に対して、鈴木氏らしさの真骨頂は「りんごの泪」にあるように思える。
冒頭のメインリフは、鈴木氏が初めて作曲した曲から取られており、オリジナル曲を作り始めた時から人間椅子の世界観だったことは驚きである。
鈴木氏の真骨頂は、日本人に土着のリズムとハードロックの融合ではなかろうか。日本の祭りや民謡のような調子と、ハードロックサウンドがなぜか不思議と混ざり合う。
この曲に関しては、後半部では和嶋氏が作ったと思われる、あえて逆の洋楽的なファンクビートを対比的に配置することで、曲の中で変化を作っているところが面白い。
その後も鈴木氏は土着的なリズムとして、ねぷた祭りのお囃子を取り入れている。「あやかしの鼓」「ねぷたのもんどりこ」「月夜の鬼踊り」などが、後に作られていくこととなった。
また三味線奏法のギターソロもこの曲では開眼している。たとえば「辻斬り小唄無宿編」「無限の住人武闘編」など、和風の曲において使われる奏法となった。
さらには故郷である青森、津軽などを思わせると言う意味では「どだればち」などにも広がっていくこととなった。
賽の河原
- 作詞:和嶋慎治、作曲:和嶋慎治・鈴木研一
- 収録アルバム:『人間失格』(1990)、『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)など
人間椅子が描く”あの世”に関する楽曲は、単に恐ろしいだけではなく、どこか悲しげで美しいものとして描かれることもある。
それこそがまさしく仏教的な世界観であり、そうした恐怖と美しさが表裏一体となった楽曲の原型が「賽の河原」ではないか、と思う。
非常に不気味なメインリフから、和嶋氏の歌う美しいBメロへと流れていく展開、そして疾走感のある後半へと展開を続けつつも、全体に侘しさや哀愁が漂っている。
こうした楽曲は、後に「羅生門」などに受け継がれ、さらに和嶋氏単独作の「幽霊列車」「恐山」などへと受け継がれていった。
ナカジマ氏加入後は、こうした路線は徐々に少なくなった感があるが、和嶋氏の中にある悲しみややりきれなさのようなものが、浄化されたからなのではないか、と考えたりもする。
近年は「マダム・エドワルダ」でこの作風がやや復活したことは喜ばしいことであった。
狂気山脈
- 作詞:和嶋慎治、作曲:和嶋慎治・鈴木研一
- 収録アルバム:『黄金の夜明け』(1992)
日本文学から世界観を借りることの多い人間椅子ではあるが、海外の作品にも範囲は広がっている。とりわけH.P.ラヴクラフトの作品からタイトルを借りることが多い。
この「狂気山脈」はその原点にあるような楽曲であり、曲調はプログレッシブロックを感じさせるような、パワフルなハードロックとは異なる独特の格調高い雰囲気がある。
静かなパートがあり、不気味な展開、あるいは疾走感のある部分や、長いギターソロなどの特徴をがある。
こうした作風は、1992年の『黄金の夜明け』でアルバムを通して開眼したものであり、和風の人間椅子とは異なる顔として、後にも受け継がれていった。
H.P.ラヴクラフトのタイトルからは「ダンウィッチの怪」「時間からの影」「宇宙からの色」などが作られている。
またプログレ風味と長いアドリブ演奏をすると言う方向性は、「踊る一寸法師」「芋虫」と言った日本文学からタイトルを借りた楽曲にも活かされていくことになる。
ダイナマイト
- 作詞・作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『踊る一寸法師』(1995)、『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)など
1993年の『羅生門』までメルダックからリリースを行っていた人間椅子だが、契約が終了となって、1995年の『踊る一寸法師』はインディーズレーベルからのリリースとなった。
それまでは幻想的な世界観を固持していた人間椅子だったが(レコード会社の方針でもあったようだ)、『踊る一寸法師』ではその縛りから解放されている。
いわゆる”俗世間”的な曲が見られる『踊る一寸法師』の中で、とりわけ特徴的な楽曲がパチンコをテーマにした「ダイナマイト」である。
歌詞もさることながら、これまでの人間椅子にはない、本格的なスラッシュメタルソングであることも、衝撃的なものだ。
色んな意味で枠を取り去ったこの曲がもととなり、速い曲は後のアルバムにも1曲程度ずつ収録されることとなる。
また鈴木氏による”パチンコシリーズ”が定番化し、「エキサイト」「銀河鉄道777」などが作られたが、「膿物語」が少しパチンコにかすった程度で、その後は作られなくなった。
地獄
- 作詞・作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『無限の住人』(1996)、『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)など
漫画『無限の住人』のイメージアルバムとして制作された『無限の住人』は、和風の世界観で統一されたことで、結果的に人間椅子らしい作風に戻ったアルバムと言える。
コンセプトが決まっていたことでむしろ作りやすかったのか、非常に名曲が多数収録されているアルバムとなった。たとえば、後に”地獄シリーズ”となった原点の「地獄」が収録されている。
和嶋氏が描く仏教的・観念的な地獄の世界とは異なり、鈴木氏が描く地獄は、視覚的でどこかコミカルにさえ思えるものである。
その精神は漫画家水木しげる氏の作品に通じるところであり、子どもが見ても分かるような地獄の風景を描き、それゆえにかえって残酷さが際立つ内容になっているとも言える。
なお地獄シリーズは、「地獄風景」「地獄のロックバンド」「地獄の料理人」「地獄の球宴」「地獄のヘビーライダー」などが続いて作られていった。
楽曲はスラッシュメタル風の速い曲が多く、やはり怖さよりコミカルさが伝わってくるような作風になっている。
黒猫
- 作詞・作曲:和嶋慎治
- 収録アルバム:『無限の住人』(1996)、『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)など
Black Sabbath風味のヘヴィな楽曲は鈴木氏の得意分野だったのが初期であった。鈴木氏の啓蒙活動を受けた和嶋氏も、次第にヘヴィな楽曲を作るようになっていく。
Black Sabbathの「Into The Void」を和嶋氏なりに解釈したようでもあり、そこにプログレ要素も取り入れたのが「黒猫」である。
5拍のブレイクがトリッキーなイントロから、地を這うようなメインリフ、疾走感のある中間部から、左右異なるソロをダビングしたアウトロとめまぐるしい。
しかし見事な構築力で、1曲としてまとめ上げられており、人間椅子の一つの到達点を示すような楽曲である。
後にアルバムラストには和嶋氏の大作が収録されると言う流れが定番化していくこととなるが、あまりに本作の完成度が高かったからか、同傾向と言える楽曲はそれほどないように思える。
なお文学的でありつつダークな雰囲気の楽曲はしばらく受け継がれ、「黒い太陽」「相剋の家」「痴人の愛」などに通じていくこととなる。
道程
- 作詞:和嶋慎治、作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『三悪道中膝栗毛』(2004)
土屋巌氏在籍時代までの人間椅子の世界観をより深めていったのが、後藤マスヒロ氏の時代だったと考える。ただ後藤氏の脱退により、いったんその路線の人間椅子は終わりを告げることとなる。
次に加入したナカジマノブ氏は、それまでの人間椅子のドラマーとカラーが異なり、キャラクターもかなり明るかった。当初はどのように人間椅子の世界に入って行くのか、模索の時期だった。
そんなナカジマ氏がボーカルをとった「道程」は、ナカジマ氏との人間椅子の第一歩だったように思える。人間椅子流の”青春”ソングのようであり、ナカジマ氏のパワフルなボーカルとマッチした。
こうした陽のパワーに溢れたロックンロールは、それまでの人間椅子にはなかった。ナカジマ氏との人間椅子を作る上での礎となり、この路線からナカジマ氏の立ち位置を探っていくことになる。
その後はすっかり人間椅子の怪奇性とナカジマ氏のパワーが融合し、「蜘蛛の糸」「地獄小僧」など人間椅子らしい世界観の楽曲も歌うようになり、ナカジマ氏との人間椅子が確立されていった。
深淵
- 作詞・作曲:和嶋慎治
- 収録アルバム:『未来浪漫派』(2009)、『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)など
和嶋氏の作風、とりわけ歌詞の世界観の変化は人間椅子の歴史を語る上でも外せない。遡れば、2001年の『見知らぬ世界』の頃から、ただ気味の悪い歌詞を書くのとは異なる方向性を見せ始める。
それは和嶋氏の中にある素直な思いを歌詞に乗せることであったが、まだ『見知らぬ世界』当時はその表現方法に苦心していたようであった。
彼自身の人生を通じた模索により、ついに表現や生き方の軸のようなものを見出したと語られている。それが和嶋氏の楽曲には色濃く表れるようになっていく。
その代表的な楽曲が「深淵」であり、『見知らぬ世界』の頃よりも、実感のこもった説得力のある作品になっていると感じられる。
和嶋氏のこうした”覚醒”とも言える現象は、人間椅子のアルバムにおける和嶋色を強めることとなった。2009年の『未来浪漫派』以降、何作かは和嶋氏の色合いがかなり強まって感じられた。
その中心には、「深淵」と言う曲があったように筆者には感じられる。それゆえ、持ち時間が30分しかないOzzfest Japan 2013出演時にもこの大作が披露されたのではないかと思う。
なまはげ
- 作詞・作曲:和嶋慎治
- 収録アルバム:『無頼豊饒』(2014)、『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)など
Ozzfest Japan 2013への大抜擢、そして敬愛するBlack Sabbathと同じステージに立った人間椅子は、この出来事を再デビューと捉え、飛躍のチャンスと考えた。
結果的にライブへの動員も大幅に増加し、人間椅子が勢いづいた。作風にも変化が見られ、実験的な要素は減らして、人間椅子の原点である怪奇的でおどろおどろしい楽曲を増やした。
原点回帰であるとともに、当時の勢いも手伝って、結果的にはよりヘヴィメタル的な重厚感・攻撃性を持つサウンドへと変化していったように見えた。
新たなヘヴィネスの方向性を見出した人間椅子の1つの到達点であり、より方向性が明確になったのは「なまはげ」が発表された時ではないかと思う。
秋田県の伝統的な祭りを題材にした日本的な歌詞や世界観と、重低音のリフが融合し、それでいて非常に前向きなパワーも持った楽曲である。
従来の人間椅子が持っていたヘヴィさと、「深淵」などで見出した前向きなパワーが、より嚙み合ってきているのを感じる。
芳一受難
- 作詞:和嶋慎治、作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『怪談 そして死とエロス』(2016)、『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)
鈴木氏の音楽性は、デビュー以前から変わらない一貫性を持っており、作品の中でも鈴木氏の作るハードロック曲が1つの軸になっていた。
それが『未来浪漫派』頃からの和嶋氏の覚醒によって、和嶋氏の楽曲がより前面に出るようになった。結果的に鈴木氏は一歩引いて、やや軽いタッチの楽曲を増やしていたように見えた。
そのバランスがまた変わり始めたように見えたのが、2016年の『怪談 そして死とエロス』であった。やや抽象的なテーマのアルバムが続いた中、本作は”怪談”というど真ん中のテーマとなった。
リードトラックの1つとなったのが「芳一受難」である。不気味なリフと緊張感・疾走感のあるリズムに乗せ、歌われるのは耳なし芳一の物語を題材とした歌詞である。
中間部には般若心経が読まれるなど、鈴木氏の真骨頂が見られる楽曲となった。和嶋氏のヘヴィな路線に影響されたかのように、また鈴木氏にも勢いが戻ってきたのだった。
常に人間椅子は和嶋・鈴木両氏がお互いに引っ張り合って、支え合って作品を作ってきたようにも思われる。
無情のスキャット
- 作詞・作曲:和嶋慎治
- 収録アルバム:『新青年』(2019)、『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』(2019)
「無情のスキャット」のMVがYouTubeで公開され、国内のみならず海外でバズった結果、1500万回を超える再生回数となった。人間椅子最大のヒット曲と言っても良いかもしれない。
この曲は突如として生まれたのではなく、これまでの人間椅子、また和嶋氏の表現の変遷があってこそ生まれたものではないか、と筆者は考える。
古く遡れば、「見知らぬ世界」で見せたシンプルで前向きなメッセージは、「深淵」によって確たるものとなり、「なまはげ」ではさらにヘヴィなサウンドとしてパワーアップした。
そしてこの「無情のスキャット」の曲展開を見ていくと、実は「黒猫」と似ていることに気付く。
「黒猫」では心の闇を表現したが、「無情のスキャット」ではそのヘヴィさはそのままに、前向きなメッセージを乗せることに成功した。
またOzzfest Japan 2013以降の、新たなヘヴィネス路線の集大成と言っても良いかもしれない。
※【人間椅子】バズった「無情のスキャット」の魅力を徹底的に掘り下げてみた
まとめ
今回の記事は、人間椅子の唯一無二の世界観を語る上で欠かせない楽曲について15曲にまとめて紹介した。
人間椅子の独自性を形成するにあたっては、大きく分けて2つの時期があると筆者は考えた。それがいわゆる初期の頃、そしてナカジマノブ氏が加入してからの時代である。
今回の選曲も、7曲がデビュー前からメジャー初期の楽曲であった。人間椅子の場合、既にデビュー時点ではその独自性のほとんどが形成されていたと筆者は考える。
そしてインディーズとなった『踊る一寸法師』以降は、メジャーの制約から外れたことで、より自由な作風で楽曲制作を行っていくこととなる。
この時代は大きな変化はないものの、それまでの個性を磨き、洗練させていった時代として、音楽的には最も充実していた時代と言えるのではなかろうか。
そして2004年にナカジマノブ氏が加入したことは、様々な意味で人間椅子にとっては転機となった。これまでと違うタイプのドラマーであったがゆえに、新たな人間椅子を作り上げることとなった。
しかし結果的にそれは、人間椅子自体をより外に開けたものにしていった。和嶋氏の作風の変化も手伝って、よりそぎ落とされたシンプルな音楽性へと変化していったのである。
今回取り上げたナカジマ氏在籍時の5曲は、そうした変化の過程や到達点として象徴的なものを取り上げたつもりである。
人間椅子の唯一無二の世界観を一言で述べるのはとても難しい。象徴的な楽曲を取り上げることで、人間椅子の個性についていくらか迫ることができたのではなかろうかと思う。
※【初心者向け】”はじめてのアルバム” – 第7回:人間椅子 絶対おすすめの名盤と全アルバムレビューも
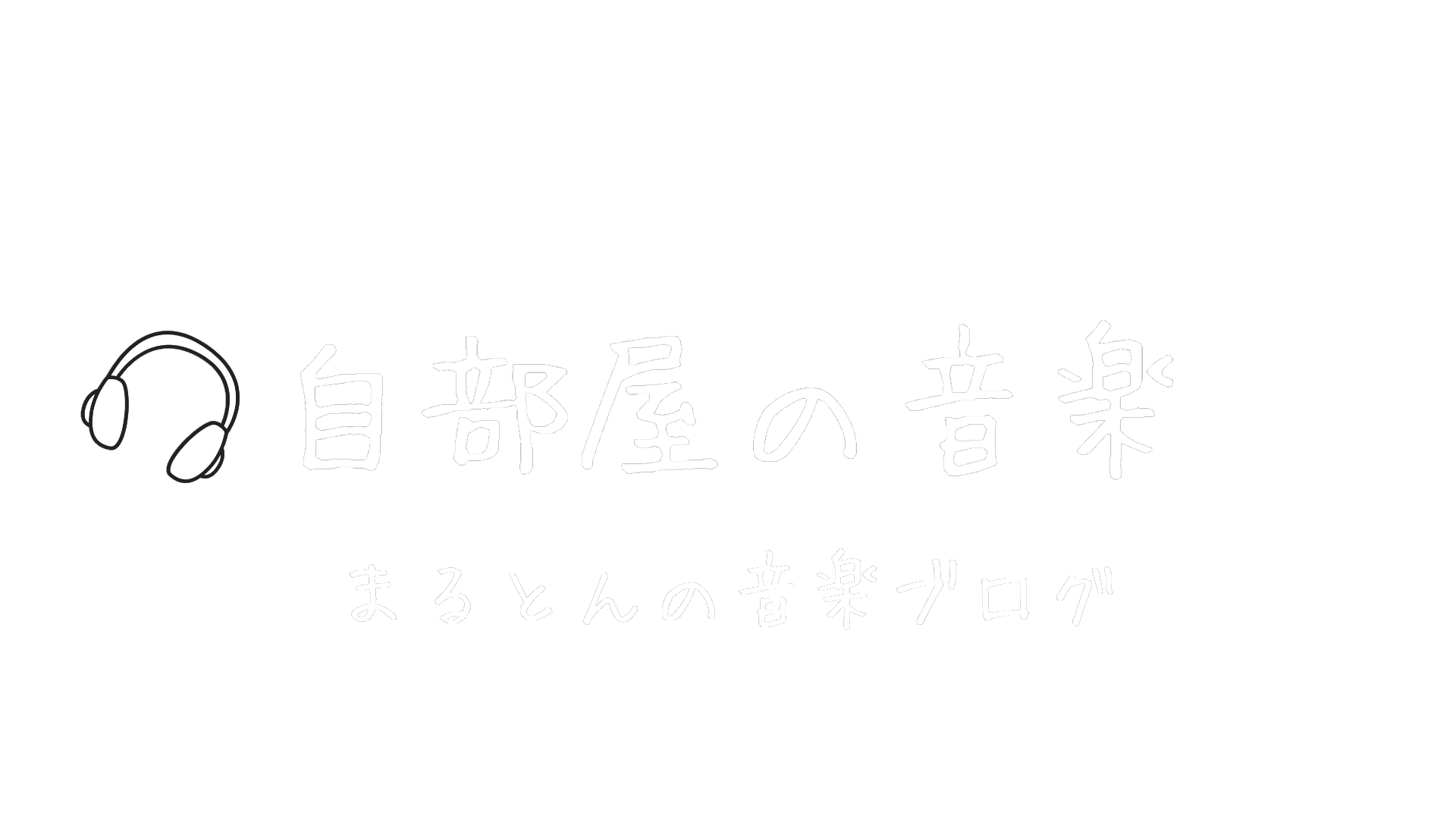


























コメント