よく聴いたアルバムの中から、”おすすめアルバム”を選んで記事にしている。
ここ最近は、ローファイ・ヒップホップを聴くことが多かった。先月に書いたL’Indécisのアルバムから、Chillhop Musicのライブ配信を聴いているタイミングも多かった。
そのためあまりアルバムを聴いていなかった。今回は新作よりも過去の作品を中心に紹介したい。
唯一の新作は、人間椅子の『苦楽』である。
Lynyrd Skynyrd – Nuthin’ Fancy (1975)
最初に紹介するのは、”サザンロック”のバンドとして知られるアメリカのバンドLynyrd Skynyrdの3rdアルバムである。
サザンロックとは、アメリカ南部の土臭い雰囲気があり、カントリーやブルースなどを前面に押し出したロックのことである。
比較的近い時期に活動したバンドに、The Allman Brothers BandやBlackfootなどがある。
Lynyrd Skynyrdは1969年にこのバンド名となり、1973年に1stアルバム『Lynyrd Skynyrd』をリリースし、100万枚を超える売上を記録した。
The Whoの前座を務めたことなどから、さらに人気は上昇。1974年に2ndアルバム『Seconed Helping』をリリースし、「Sweet Home Alabama」はチャート8位を記録する。
その後、バンドの規模は大きくなって絶頂期を迎えていた1977年、飛行機墜落事故でメンバーやバックコーラスが亡くなる。
バンドは解散したが、1987年に再結成して活動を継続している。
今回は人気上昇中の1975年の3rdアルバム『Nuthin’ Fancy』を紹介する。
Lynyrd Skynyrdと言えば、やはり1stと2ndという声もあるだろうし、筆者もよく聴いていた。売り上げ的にも下がってしまった3rd(チャートは9位で上昇)ではあるが、もちろん聴きどころもある。
まずはシングルカットされた「Saturday Night Special」は、Billboard Hot 100で27位を記録している。
基本的な音楽性は全く変わっていない気がするが、強いて言えばリフを前面に押し出して、ハードロック要素が強まったことだろうか。
しかしハードロックもブルースからの流れだとすれば、自然に聞こえてくる。
3曲目の「Railroad Song」は、ハードさよりも土臭さを感じさせる楽曲。こうしたスカスカのサウンドがバンド当初からの魅力の1つと言えるだろう。
個人的には、前2作とほとんど変わらず、土臭いサザンロックを聴かせてくれる作品だと思う。楽曲の中には、以前よりハードロックテイストなリフを用いた曲もあるが、あまり違和感はない。
前2作が気に入った人はぜひとも本作も手に取っていただきたい。
Enigma – The Screen Behind the Mirror (2000)
以前、おすすめのアルバム(2020年10月~11月)を紹介した際にも、Enigmaの作品を紹介した。その時は3rdアルバム『Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!』の紹介であった。
今回はそれに続く4th『The Screen Behind the Mirror』を聴いたのだが、こちらも良い作品だったので紹介したい。
Enigmaは1990年よりドイツを拠点に活動する音楽グループで、ヒーリング・ミュージックの先駆者としても知られている。
民族音楽などの古典音楽とダンスビートとの融合が特徴であり、初期はインスト曲のみだったが、徐々にボーカルの入った曲も登場する。
本作『The Screen Behind the Mirror』は、作曲家Carl Orffによる『Carmina Burana』をサンプリングした作品となっている。
雰囲気や作風は前作の3rdと大きくは変わっていないため、評価が高いとは言えないアルバムのようだ。と言うことは、前作が気に入った人にはおすすめの作品と言える。
導入曲「The Gate」から、シングルカットされた「Push the Limits」でアルバムはスタートする。
1stの頃の厳かな雰囲気からは多少変化があり、スリリングでリズミカルな音楽性は3rd辺りから引き継がれているように思う。
続く3曲目の「Gravity of Love」もシングルカットされた楽曲で、ボーカルを前面に出している。ここでも『Carmina Burana』がサンプリングされていることにも注目だ。
なお日本では本作の「Modern Crusaders」がアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」のエンディング曲として使用されたことでも知られている。
本作の代表曲としては、上記のような楽曲が挙げられるが、筆者が好きなのはその間に挟まれるさりげない楽曲たちである。
「Smell of Desire」や「Traces (Light and Weight)」など、1つのフレーズが繰り返され、緩やかに時間が流れていくような楽曲こそ、このグループの魅力だ。
少しボーカル曲が多く騒がしくなってきた印象もあるが、環境音楽的な要素を感じる楽曲は相変わらず素晴らしいなと感じた。
見汐麻衣 – うそつきミシオ (2017)
続いては、ジャンルを大きく変えて歌謡曲のアルバムである。今回初めて聴いた見汐麻衣氏のソロデビューアルバム『うそつきミシオ』だ。
ジャケットにセンスを感じて聴いてみたのだが、これは70年代のアルバム?と思うようなニューミュージックを感じさせる楽曲や音作りに大いに驚いた。
見汐麻衣氏は、2001年よりバンド“埋火”で活動後、ソロ・プロジェクト“MANNERS”などを経て、その他様々な音楽活動を展開している。
本作は歌謡曲と、(黎明期の)ニューミュージックを意識して作られたとのこと。そしてテーマは「会話」だと言う。
とにかく徹底した歌謡曲・ニューミュージックへのこだわりを感じる音作りが秀逸だ。シティポップやAORほどハキハキしたリズムではなく、ルーズさもありつつ跳ねるようなグルーブが素晴らしい。
ラストに配置された「1979」のMVが公開されている。ジャズを感じさせるゆったりしたグルーブと、悲しげなメロディラインが美しい。
こういったバラードも良いが、「たしかに愛を」や「はなしをしよう」など軽快なリズムの楽曲も魅力であろう。
かつて言われた”ドライブ”にぴったりの楽曲たちであり、何だか気持ちもウキウキしてくる。そしてこの隙間のある音作りが、やはり心地よさを生み出しているのだと思う。
※Mikki:見汐麻衣が語る初のソロ・アルバム『うそつきミシオ』

アルバムについては、ご本人の詳しい解説・インタビューがあるので、そちらもお読みいただきたい。
Il Paese Dei Balocchi – Il Paese Dei Balocchi ”子供達の国” (1972)
このブログではあまり書いたことがないが、70年代のイタリアのロックが好きである。プログレッシブロックが流行った70年代、イタリアのロックは名作揃いなのだ。
イタリア語は英語とは異なる語感で、母音で終わる発音はどこか日本語にも近い。そしてクラシックをベースに、少しラテンムードが漂うのが特徴である。
筆者も決して詳しい訳ではないが、プログレコーナーに行くとイタリアの作品をいつも探している。今回見つけたのは、Il Paese Dei Balocchiの唯一のアルバムである。
あまり情報がないが、60年代中期に活動していたUNDER 2000なるBeat/Psyche Rockバンドが改名したものだそうだ。
本作はイタリアンプログレらしい作品であり、時代の流れに応じて、バンドは音楽性を変えているとも言える。ちなみに邦題は「子供達の国」である。
1曲目の「Il trionfo dell’egoismo, sella violenza, della presunzione e dell’indifferenza」は、いかにもイタリアのプログレらしい楽曲だ。
荒々しさとともに、プログレッシブなフレーズから強引な展開である。クラシックのパワフルな部分をロックに持ち込んだのがイタリアンプログレの良さでもある。
3曲目の「Canzone della speranza」は、イタリアンプログレのもう1つの側面である荘厳な美しさを前面に出している。
本作はあまり歌が登場しないが、この曲では朗々としたボーカルを聴くことができる。
本作は、これぞイタリアンプログレというツボを押さえた作品だと思った。荒々しさも目立つが、クラシカルな部分とロックのバランスが絶妙である。
そしてまさにアルバム中心の音楽である。アルバム1枚で世界観が構築され、じっくりと音楽に耳を傾ける時間を作ってくれる。
隠れた名作が多数あるイタリアのプログレは、集める楽しさもある。これからもまだ知らない作品を探し続けたいと思う。
人間椅子 – 苦楽 (2021)
最後は、今月最も多く聴いたであろう人間椅子の新作『苦楽』である。
本作については、既に詳細なレビューを記事としてまとめている。ここではレビュー記事に書ききれなかったことや、その後感じたことを書いておきたい。
本作を聴いていて感じるのは、聴き飛ばすような曲が全くない、ということだ。これは、全曲がしっかりと作り込まれた楽曲である、ことを意味すると思う。
好きな雰囲気な曲であっても、作り込みが粗いとどうしても聴く頻度は下がってしまう。本作には時間をかけて、1曲ずつが丁寧に作られたことがわかる。
あまり長い曲がなくシンプル、と言う声はよくTwitterなどで聞かれる。大作である1曲目「杜子春」も、聴いているとそこまで長さは感じられない。
コンパクトにまとめられつつも、良いフレーズが凝縮されたアルバムと言う印象だ。
実は、人間椅子も無意識のうちに現代的な音楽のあり方に適応した結果こうなったのでは?とも思う。
昔ほど音楽をじっくりと聴く時間は人にはなくなっている。せいぜいテレビか新聞くらいしか眺めるものがなかった時代と、常に情報に晒される現代とでは、音楽の聴き方も異なる。
人間椅子もそんな時代の流れとともに、楽曲の組み立て方は変わってきているのかもしれない。
『黄金の夜明け』のような大作、『頽廃芸術展』のようなゆったりしたアルバムを今求めるのは、いささか無理があるだろう。
そして人間椅子は今になって売れていることを考えれば、きっと現代の音楽の聴き方にもある程度適応してきているのだと思う。
レビュー記事では、現代を描いたアルバムと書いた。本作は楽曲の長さやコンパクトさからも、現代を感じられる作品と呼べるかもしれない。
<据え置き型の音楽再生機器に迷っている人におすすめ!>
Bose Wave SoundTouch music system IV
これ1台でインターネットサービス、自身で保存した音楽、CD、AM/FMラジオを聴くことができる。コンパクトながら深みがあり、迫力あるサウンドが魅力。
自宅のWi-FiネットワークやBluetooth®デバイスにも対応。スマートフォンアプリをリモコンとして使用することも可能。
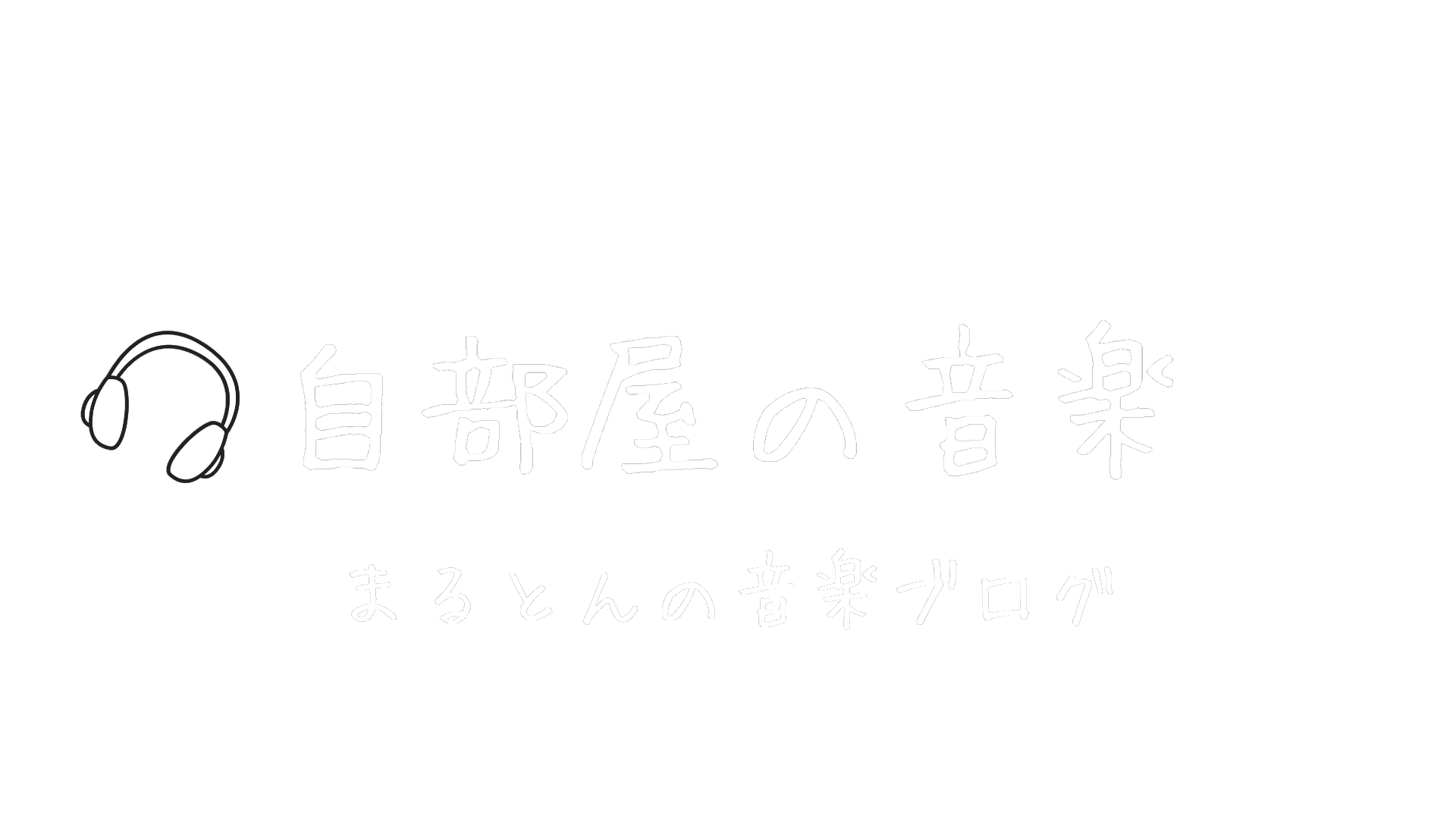























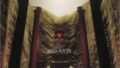
コメント