バンド生活三十五年を迎えたハードロックバンド人間椅子、その歌詞の世界観を作るのは、ギター・ボーカルの和嶋慎治氏によるところが大きい。
一方で楽曲や演奏、パフォーマンスにおいて存在感を見せるベース・ボーカルの鈴木研一氏が歌詞を作る割合は極めて小さい。
しかし何気ない一節に、思いもよらぬ味わいや深みを感じさせるのが、鈴木氏の歌詞の良いところである。
今回は、鈴木研一氏の作詞の中で、声に出して読みたくなるような、味わい深い一節を取り上げた。
声に出して読みたいベース鈴木研一の味わい深い一節のある10曲
今回取り上げるのは、人間椅子の楽曲の中で、あまり多くはない鈴木氏が作詞したものである。
観念的な内容やメッセージ性の強い歌詞を作る和嶋氏に対し、鈴木氏の歌詞は具体的な事物をテーマにしたり、視覚的な表現を用いたりすることが多い。
そのため、あまりメッセージ性がないように思えるが、実は裏側には鋭い視点やメッセージ性が隠れている場合もある。
また各自で自由に読み取れる懐の深さがあるのが、鈴木氏の歌詞の面白さである。あまり彼自身は歌詞に自信がないようであるが、非常に味わい深い一節がいくつもある。
今回は筆者が特に気に入っている表現を10個取り上げて、楽曲の紹介とともに書いている。
見かけほど強くない みんな痩せてるヘヴィ・メタル
- 楽曲名:「ヘヴィ・メタルの逆襲」
- 作詞・作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『人間失格』(1990)
1990年の『人間失格』収録の「ヘヴィ・メタルの逆襲」は、伊藤政則氏の著作からタイトルを借りた、実は文芸シリーズである。
当時は”ナンセンスソング”と呼ばれており、文学的な世界観を重視していた人間椅子にあって、鈴木氏の日常的な言葉で書かれた歌詞は衝撃であったことだろう。
歌詞は世間のイメージするヘヴィメタルと、実際にヘヴィメタルをやっている人のギャップを自虐的に書いたもの。
とりわけ好きな一節は、「見かけほど強くない みんな痩せてるヘヴィ・メタル」だ。いかにも絵が浮かんできて、思わず笑えてしまう名フレーズだろう。
そして五・五・七・五のリズムになっているから、日本人にとても馴染みやすいところがまたポイントが高い。
沼に潜むは蛙や海星や鯰
- 楽曲名:「桜の森の満開の下」
- 作詞:鈴木研一、作曲:鈴木研一・和嶋慎治
- 収録アルバム:『人間失格』(1990)
1990年の『人間失格』収録の「桜の森の満開の下」は、坂口安吾の小説からタイトルを借りている。
こうした文芸シリーズの歌詞を鈴木氏が書くことは今となっては珍しいことであるが、かなり文学の世界を描こうと、言葉巧みに歌詞が作られている印象である。
鈴木氏の歌詞は語呂と言うか、聞こえた感じがとても良い。冒頭の「桜のトンネル夜歩く旅人」なども、とても口に出して見ると心地好い表現だ。
そして取り上げた「沼に潜むは蛙や海星や鯰」も同様だ。「海星」は淡水に存在しないというツッコミを自ら入れていたが、それでもとにかく語呂が良いのである。
後にライブで演奏される時も修正されていないのは、やはり正しさより表現の良さが尊重されているからに思える。
わ、バンドのガンでねべが
- 楽曲名:「わ、ガンでねべが」
- 作詞:鈴木研一、作曲:鈴木研一・和嶋慎治
- 収録アルバム:『黄金の夜明け』(1992)
1992年の『黄金の夜明け』収録のナンセンスソングである。アルバム全体にプログレ色があるためか、この曲もプログレッシブな雰囲気が漂う。
歌詞の中身は、体調不良を並べて「わ、ガンでねべが」と津軽弁で歌い、後半ではバンド内における”ガン”ではないか、とバンドの話にすり替わっている。
自虐を歌詞に入れるのがお得意な鈴木氏であるが、「わ、バンドのガンでねべが」と絶叫するところは、妙に真実味があって思わず笑えてしまうものである。
しかし鈴木氏あってこそ人間椅子がここまで続いてきたことを考えると、今となっては微笑ましい感じのする歌詞でもある。
おやすみ前にブラック・サバス
- 楽曲名:「三十歳」
- 作詞:鈴木研一・和嶋慎治・土屋巌、作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『踊る一寸法師』(1995)
1995年にインディーズでリリースされた『踊る一寸法師』は、メジャー契約の制約がなく、これまでにない日常的な歌詞が出たりと、変化があったアルバムだった。
「三十歳」はタイトル通り、メンバーが30歳を迎えたのを記念し、メンバー紹介ソングのような形で、3人がそれぞれボーカルを取って自身について歌っている。
ここでも三者三様の個性があるが、鈴木氏はまさに当時の実生活そのものである。そして「おやすみ前にブラック・サバス」と言い切るところが、いかにも鈴木氏らしくて良い。
鈴木氏のこの歌詞を見ていると、やはりずっと変わらないのが鈴木氏であるし、1番人生を謳歌しているのが鈴木氏ではないか、と思えてくる。
痛みより何よりも 死ねないのがこれ地獄
- 楽曲名:「地獄」
- 作詞・作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『無限の住人』(1996)
1996年の『無限の住人』は漫画作品のコンセプト作であるが、人間椅子の世界観を楽しめる作品になっている。
鈴木氏が”地獄”をタイトルにつけた第1弾であり、地獄の光景を残酷でありながら、コミカルに描いた、鈴木氏らしさに溢れた傑作である。
歌詞の内容は、まさに地獄で受ける苦しみを具体的に記述したものであり、次々と責め苦が襲ってくるのだが、「痛みより何よりも 死ねないのがこれ地獄」と締めくくられる。
地獄の恐怖は終わらないところにある。逆に言えば、人生には終わりがあるからこそ、儚く美しいものなのだ、と思えてくる。
分かりやすい言葉で真理をついているのが、鈴木氏らしい歌詞だ。
死ぬまで続く運だめし
- 楽曲名:「エキサイト」
- 作詞・作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『頽廃芸術展』(1998)
1998年の『頽廃芸術展』は前作と異なり、コンセプトにはあまり縛られず、自由な作風のアルバムとなっている。
「エキサイト」は鈴木氏のパチンコシリーズの楽曲であるが、この曲では単にパチンコだけでなく、ギャンブル全般、そして人生論まで広がる歌詞となっている。
とりわけ気に入っている一節は「死ぬまで続く運だめし」という部分だ。全くその通り過ぎて、ぐうの音も出ない言葉である。
鈴木氏の歌詞は一言の中で、人生に通じる真理を言い当ててしまうことがある。この曲の「死ぬまで続く運だめし」もそうで、最後に繰り返し歌われると、ますます大事な言葉に聞こえてくるのだ。
あしながぐもだろう 明日があるだろう
- 楽曲名:「あしながぐも」
- 作詞・作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『怪人二十面相』(2000)
2000年の『怪人二十面相』は、江戸川乱歩の小説「怪人二十面相」の世界観をアルバムを通して描くコンセプト作である。
「あしながぐも」は、鈴木氏の虫シリーズとも言える作品である。曲調は「死神の饗宴」の習作とも言えるもので、”いなたい”雰囲気のハードロックに仕上がっている。
歌詞はあしながぐもと人生を重ね合わせたような内容になっている。サビにあたる「あしながぐもだろう 明日があるだろう」は言葉遊びのようでありつつ、実に味わい深い一節である。
虫たちに向けられる鈴木氏のまなざしは、とても温かいものがある。虫たちがどんな一生を送るのか、まるで少年のような見方をしているようにも思える。
後半に登場する「あしながぐもにも 明日はあるけど」という言い回しもまた味わい深い。
締めのラーメン忘れずに
- 楽曲名:「肥満天使(メタボリックエンジェル)」
- 作詞・作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『真夏の夜の夢』(2007)
2007年の『真夏の夜の夢』は、人間が見る夢の世界をテーマに、怪奇・幻想の世界を幅広く取り上げたアルバムとなっている。
「肥満天使(メタボリックエンジェル)」はついつい食べ過ぎて太ってしまう鈴木氏自身をテーマにした楽曲とも言える。悪魔ではなく、天使としているところがなんとも微笑ましい。
歌詞はとにかく太りそうな食べ方についてひたすら書かれている。それにしても「締めのラーメン忘れずに」と歌うハードロックバンドも人間椅子くらいのものだろう。
お酒を飲まない鈴木氏であるが、「締めのラーメン」とは何に対する締めなのか気になるところである。
それまで続いていた”ナンセンスソング”の系譜は、本作辺りで徐々になくなっていくのが寂しいところである。
風が吹いたら元通り
- 楽曲名:「地獄の球宴」
- 作詞・作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『怪談 そして死とエロス』(2016)
2016年の『怪談 そして死とエロス』は、抽象的なテーマではなく、人間椅子らしい怪奇的な世界観を分かりやすく提示したアルバムとなった。
鈴木氏は唯一の作詞曲で、地獄シリーズの楽曲を作った。今回は地獄での野球をテーマにしたもので、罪人に罰を与えつつも、それを野球になぞらえているコミカルな歌詞である。
しかしその歌詞を見てみると、かつて「地獄」で描いたより、さらに残虐な光景である。そして何より恐ろしいのは「風が吹いたら元通り」と言う一節だ。
先ほどの「死ねないのがこれ地獄」に通じるもので、風がサッと吹けば、頭から拷問はやり直しで終わりがないのである。
さらりと恐怖を与える鈴木氏らしい歌詞で、「しゅるんしゅるん」などの擬音語も面白い。
喰われてもこんなに有難いのは
- 楽曲名:「恍惚の蟷螂」
- 作詞・作曲:鈴木研一
- 収録アルバム:『苦楽』(2021)
2021年リリースの『苦楽』とは、仏教における人間界の”苦楽なかば”を思わせる、私たちの世界のあり様をこれまで以上にメッセージ性強く描いた作品となった。
和嶋氏の歌詞がかなり世相を反映したものであった半面、鈴木氏はあえて自然界に目を向け、カマキリの交尾を題材にした「恍惚の蟷螂」で歌詞を書いている。
鈴木氏が注目したのは、交尾においてオスがメスに食べられてしまう、という習性だ。人間に置き換えれば、こんなに恐ろしいこともないが、究極のマゾヒズムと言えなくもない。
そこに「喰われてもこんなに有難いのは」という歌詞をあてたことに、和嶋氏は感心していた。確かに人知を超えた習性への畏敬のようなものが読み取れる。
そして性の快楽と喰われてしまう、という苦楽がトレードオフのカマキリを知ることで、苦楽なかばの人間界の有難さを知る、というなかなか味わい深い歌詞でもあるのだ。
苦楽と言うタイトルにもぴったり、そもそも苦楽半ばの人間ではなく、快楽のために喰われてしまう
まとめ
今回は人間椅子の楽曲の中で、鈴木研一氏が作詞した楽曲を取り上げ、味わい深い一節を紹介した。
観念的・文学的な和嶋慎治氏の作る歌詞とは良い意味で反対に、視覚的でシンプルな言葉を多用しているのが鈴木氏の歌詞である。
しかし時に和嶋氏の歌詞以上に深みを持って聞こえてくることもあるし、やはり鈴木氏の歌詞があってこそ、それぞれの歌詞の良さが際立つものだと思った。
そして鈴木氏の歌詞は音の良さと言うか、口に出して読む良さのようなものがある。選んでみると「死ぬまで続く運だめし」「風が吹いたら元通り」など、七五調なのも日本人に馴染みやすい。
改めて鈴木氏の歌詞も再評価されても良いのではないか、と思っている。
※【人間椅子】ベース・ボーカル鈴木研一に迫る! – おすすめの鈴木氏の楽曲、ライブパフォーマンスと素顔
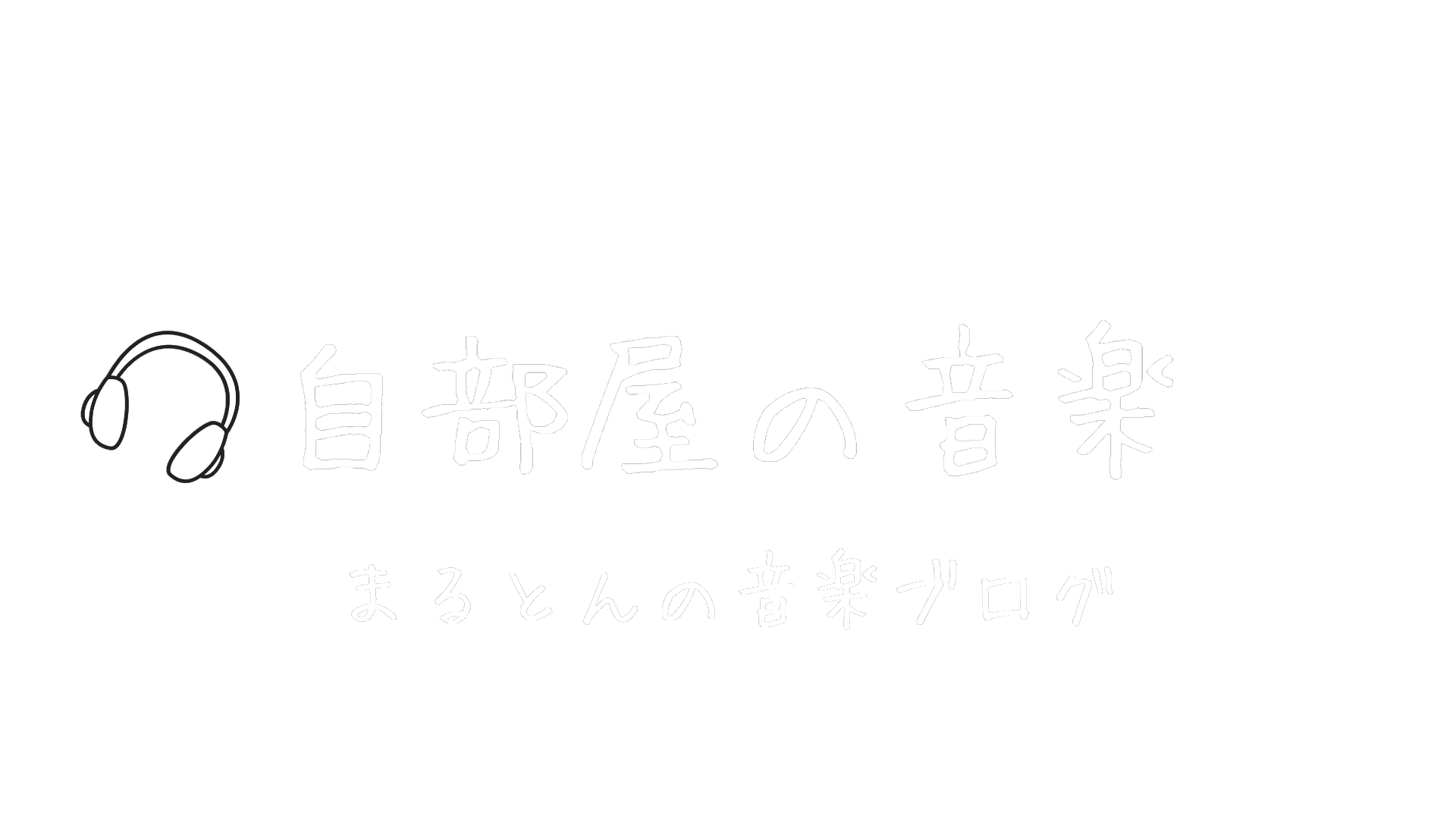






















コメント