2021年に活動40周年を迎えたミュージシャンの角松敏生。現在はニューアルバムに向け、配信シングル『MILAD #1』『MILAD #2』をリリースしたところである。
本日から『MILAD #2』配信スタート!
— 角松敏生_OFFICIAL (@kadomatsu_info) May 18, 2022
是非チェックしてくださいね。https://t.co/z3xxcvX5B7
角松氏の活動歴を振り返ると、決して順風満帆という訳ではなく、幾度となく困難な時期もあった。中でも1993年に自身名義の音楽活動を休止する”凍結”は大きな出来事であった。
しかし凍結中もプロデュースや別名義での活動で多忙を極め、1998年の長野オリンピックでの「WAになっておどろう」の歌唱など、音楽的にはむしろ目立った活動をしていた。
そして活動を凍結する直前の時期に遡ると、90年代始めの角松氏の作品群には非常に魅力的な楽曲が多いことが分かる。
しかも他の時期にはない味わいと言うべきか、角松敏生という人間性が前面に出た生々しさがかえって魅力になっているとも言える。
今回はそんな活動凍結前夜、1991~1993年頃の角松敏生氏の魅力について迫ってみようと思う。
デビューから80年代後半までの角松敏生
最初に、デビューから80年代終り頃までの角松敏生の作品について触れておこう。
1981年、角松氏は日本大学在学中にシングル『YOKOHAMA Twilight Time』、アルバム『SEA BREEZE』でデビュー。
当時レコーディングやアレンジの知識はなかったと語る角松氏は、プロで活動しながらそうした技術も磨いていったようだ。
そして1983年の『ON THE CITY SHORE』よりセルフプロデュースを行い始めた。同時期に杏里への楽曲提供やプロデュースにより、商業的な成功を博す。
80年代前半の角松氏の作品は、いわゆるシティポップ的な夏・海といったテーマの楽曲が多かったが、1984年の『AFTER 5 CLASH』より、夜の街をイメージさせるファンクナンバーが増える。
さらには1985年の『GOLD DIGGER~with true love~』よりダンスミュージックや打ち込みサウンドを取り入れ始める。
80年代後半には中山美穂への楽曲提供・プロデュースで大きな成功を収めた。ダンス・ファンク色の強いアルバム『CATCH THE NITE』がチャート1位となった。
角松氏自身は、打ち込みサウンドのアルバム『BEFORE THE DAYLIGHT』やインストゥルメンタル作品『SEA IS A LADY』など音楽的な実験を続けていた。
80年代前半までの角松氏はいわゆるAORやシティポップの影響下にあった。80年代中期にはダンスミュージック・ファンクに傾倒し、この頃までの楽曲に熱烈なファンも多い。
2010年代以降には、シティポップの再評価により80年代の楽曲は再び注目が集まっている。
しかし角松氏本人は、当時の歌唱には納得いっておらず、アレンジも直したいところばかりだとインタビューで述べている。作り手からすれば、まだ未熟な時期だったと考えているようだ。
とは言え、昔からのファンにとっては”AOR全盛の角松”と言えば、それぞれの思い出とともに煌めきのあるものであろうし、クオリティ云々という作り手側とは別の評価があろうとは思う。
また後に詳しく触れるが、ベスト盤『角松敏生1981-1987』が、活動”凍結”に影響を及ぼさなかった楽曲群とのことで、1987年までが1つの区切りになっているようである。
アルバムで言えば1987年の『SEA IS A LADY』までと、1988年『BEFORE THE DAYLIGHT』以降では、”凍結”を決めた当時の角松氏の中では異なる意味を持っていたようだ。
音楽的に見れば、1988年以降の80年代の角松氏の作品は、打ち込み主体でやや暗いトーンになっている。中山美穂氏への提供曲で見せる弾け感と比較すると、それはさらに如実に見えてくる。
90年代に起きるさらなる作品の変化の兆しは、88年以降に既に始まっていたということである。
※【初心者向け】”はじめてのアルバム” – 第9回:角松敏生 各年代のおすすめ名盤を1枚ずつ選出!
1991年~1993年と言う時期の角松敏生の魅力
今回じっくりと書きたいのは、「1991~1993年」の角松敏生の作品である。
最初に「1990年」を入れなかったのはなぜか言っておくと、これはインストゥルメンタル作品『Legacy of You』しかアルバムリリースしていないためだ。
サウンド的にも1980年代のインストゥルメンタル作品『SEA IS A LADY』の雰囲気を思い起こさせる、まさに”Legacy(遺産)”のような作品だからである。
そして1991年~1993年のアルバム・ミニアルバムは下記の作品群である。
- 『ALL IS VANITY』(1991年、フルアルバム)
- 『TEARS BALLAD』(1991年、バラードベストアルバム)
- 『あるがままに』(1992年、フルアルバム)
- 『君をこえる日』(1992年、ミニアルバム)
- 『角松敏生1981-1987』(1993年、ベストアルバム)
オリジナル作品としては、アルバム2枚・ミニアルバム1枚をリリースしている。
この時期には内省的な楽曲が増え、80年代のリゾート感・きらびやかなイメージは弱くなっている。
そして自身の音楽への絶望感から、1993年の日本武道館公演をもって活動の”凍結”を行った。自身の離婚や女性関係などが影響したとも語っており、公私ともに疲弊していた状況だったようだ。
そんな状況だったにもかかわらず、楽曲としては非常に魅力的なものが並んでいる。それは”そんな状況だったからこそ”書けた楽曲群のようにも思われる、この時期特有の魅力がある。
筆者としては、1991年~1993年の角松氏の楽曲が最も気に入っている。この時期の楽曲や漂う雰囲気になぜこうも惹かれるのか、分析してみたい。
追いつめられたからこそありのままをさらけ出せた歌詞・楽曲
最大の理由が、表現者としての角松敏生が最も輝きを放った時期だから、というものである。
角松氏が80年代~凍結までの時期、どのような思いで創作していたのか、について、ブログ『あるがままに』の「角松敏生の音楽はなぜ変わったのか?」という素晴らしいまとめがある。
ぜひそちらをご一読いただきたいが、筆者なりにも表現者としての角松氏についてまとめておきたい。
角松氏は、自らの表現を「自分の血で書いた音楽」と、1993年当時のインタビューで語っている。それは単に実体験をもとに曲を作る、というだけのことではない。
彼の実際に体験したリアルな喜び・悲しみと言った感情や、受けた傷までもそのままに表現とするという意味なのだ。
特に凍結までの彼の表現は、その傾向が強かった。そして特定の女性への思いが、創作の原動力になっていたというのが特徴である。
80年代半ば頃までの弾けるようなキラキラ感は、女性へのある種の憧れや、素直な欲望から生まれたポジティブなパワーがもとになっていたのだろう。
追い求める理想的な存在としての女性が、次第に深く愛し現実に彼の横にいる存在となっていった。角松氏は2人の女性を同時に愛し、そのうち1人(Mさん)と結婚したのだった。
彼のこうした女性との関係は、80年代後半の楽曲の歌詞に暗に描かれているようで、こちらの記事などにそうした解釈が書かれている。
89年にMさんと結婚した角松氏だったが、結婚生活は最初から上手くいかずにすぐに離婚したようである。そしてもう1人の女性Sさんとの同棲生活も上手くいかず、Sさんは別の男性と結婚した。
『ALL IS VANITY』収録の「ただ一度だけ 〜IF ONLY ONCE」ではSさんの結婚式に出席した時の気持ちが生々しく綴られていると読んで良いだろう。
そんな悲痛な叫びのようなアルバム『ALL IS VANITY』の後にリリースされたのが『あるがままに』であった。
『あるがままに』は1人の女性への尽きぬ思いを純粋に描いたアルバムである。どうやら離れていったSさんに向けたアルバムだったようである。
アルバムのブックレット最後に”If my music cannot change your mind、Music does no longer make sense to me”と手書きのメッセージが書かれている。
それほどまで覚悟をもって制作した角松氏だったが、その思いが女性に届くことなかった。それが彼の活動凍結の要因の1つになっているということだそうだ。
角松氏のプライベートな内容にも踏み込んだが、それほど私生活と楽曲がリンクしていた時期だったと言うことなのである。
彼の頑固で職人肌の音楽家の側面だけを見ていると、これほどまでに人間味のある表現者だったのかと驚かされるほどである。
彼は凍結に到るまで、女性と言う存在に憧れつつ、愛し、そして最後には裏切られた思いを、ありのままに描き続けてきた。
そして80年代末の結婚・離婚、そして2重生活と離別が、角松氏の人生を揺るがすほどの経験として作品に大きく影響したのだった。
だからこそ1991~1993年に作られた作品は、追い詰められたからこそ、彼の傷つきや悲しみを、凄まじいクオリティの作品としてアウトプットできたように思える。
しかもそれが彼のもともと持っていた哲学的な思想や言葉と結びつき、80年代前半のシティポップの角松とは違う、深みのある角松流ポップスが出来上がったのだった。
しかしそれも危ういバランスの中で保たれ、これ以上作り続ければ、愛していたはずの女性への恨み言ばかりになってしまうと感じ、活動を凍結したのだった。
自分の血で音楽を作ってきた角松氏は、最も追い詰められた時に、皮肉にも最も輝かしい作品群を残すことになったのである。
自らの”セラピー”とも言える楽曲
もう少し作品ごとに特徴を見てみると、彼の心理学的な観点も垣間見える点が興味深い。
つまり1991~1993年の作品には、角松氏がどのように生きてきたのか、また困難からどう立ち直るのか、という心理的プロセスが表れているように思える。
具体的には『ALL IS VANITY』と、それ以降の作品では彼の心理的なプロセスにおいては違いが見られる。
先ほど振り返ったように、89年~90年頃にかけて角松氏の女性関係の様々な出来事が起こった時期だったようである。
『ALL IS VANITY』では、まだ傷が癒えないどころか、血が滴り落ちているかのような不穏な空気が漂っている。
抑えきれない心の闇がそのまま登場したり、隠そうとしたり、アルバムの中でも作風が分裂しているかのような印象がある。
そして1992年の『あるがままに』になると、明らかにステップが進んでいる。それは別れた女性への一途な思いへと昇華することで、無理やりにでも前に進もうとする段階である。
まだ深い悲しみは後から追いかけてくるような状況だが、一縷の望みを託しつつ、あえてもう1度ポジティブな表現として、愛した女性への思いを客観的に描こうと試みた作品に思える。
その後の『君をこえる日』は、望みも尽きて深い悲しみが後ろから迫ってくる中の、自分の現在地と未来を歌ったものであった。
いつの日か「I’ll be over you」と言えるように、今度は自分自身に歌いかけるのである。
こうした作風の変化を見ると、一方でその渦中で苦しむ表現者としての角松氏がいて、もう一方でそれを立ち直りのプロセスとして音楽に仕上げる音楽家の角松氏が存在しているように思える。
音楽家としての彼は、まるで自分自身がどのように傷つき、何を感じ、そしてどのように立ち直ろうとしているのか、心理的に分析しながら曲にしているように感じられるのだ。
また別の見方をすれば、表現者として苦しむ角松氏を、自分自身で音楽を通じたセラピーをしているかのようなのである。
それが顕著に感じられるのは、『あるがままに』『君をこえる日』の2作である。だからなのか、この2作には悲壮感よりも温かみを感じられる作風になっている。
角松氏が自分自身を癒すかのように音楽を作ったからこそ、この時代の楽曲はファンの心に悲しくも優しげに入っていくのではないか、と思った。
彼は「自分のために歌っている」と語っていたが、まるで自身へのセラピーのようなこの時期の楽曲群は、ファンの心の深いところに刺さる曲になっているように思える。
音楽家としての成熟・オリジナリティの確立
角松氏の中には、表現者としての角松氏と、音楽家としての角松氏がいると、先ほど書いた。
角松氏自身は、「自分は表現者で音楽バカにはなれない」とかつて語っていたようだが、それは80年代に彼の作った作品が過小評価であることへの皮肉のようにも聞こえる。
確かにデビューした当時は、表現したいものがあって、それを音楽で表現しようと思ったのだろう。しかし彼の中で音に人一倍こだわり、職人のような音楽家の角松氏が徐々に大きくなっていった。
80年代前半は先達のAORなどに倣い、レコーディングを通じてアレンジなどを学んでいった。そして80年代後半には打ち込みサウンドなど、新たな音を求め続けていた。
そして90年代に入り、そうした目新しい音への探求も一通りやりつくしたのだろうか。再びバンドサウンドへと回帰していった。
90年代は、角松氏がようやく自身が納得できるサウンドを掴み始めた時期で、角松敏生という音楽のオリジナリティが確立されつつある時代だったのではないか、と思う。
レコーディングメンバーも、これまで海外の名プレーヤーをゲストに呼ぶなどしていたが、『あるがままに』の頃には青木智仁・浅野祥之という盟友が名前を連ね始めている。
こうした”角松サウンド”の確立とともに、メロディメイカーとしても脂の乗った時期に突入しようとしていた。
表現者としての彼は”凍結”の道を選んだが、角松氏の作るメロディはますます磨きがかかっているのが90年代である。
その証拠に凍結後の1997年に角松氏が作曲した中で最も有名と言って良い「WAになっておどろう」がリリースされている。
※筆者による「WAになっておどろう」について詳しく書いた記事
このように、90年代は角松氏が音楽家として成熟し始めた時期としても魅力的である。
しかしこれは表現者としての角松氏の時間的な流れとは、関わりながらも別物だと思っている。93年で角松敏生としての表現は止め、音楽家としての彼だけがその後も時間を刻んでいくことになった。
ただ1991~1993年という時代は、たまたま表現者・音楽家の2つの側面において、ともにクオリティの高い状態だった、ということなのである。
角松氏は解凍した1998年以降の作品が、音楽家としてより成熟したものだから、そちらを聴いてほしいと発言している。
しかし角松敏生が、あそこまで追い詰められたからこそ表現できた1991~1993年の頃の楽曲こそ、表現者であり音楽家でもある彼の作品のピークに思えてならない。
【まとめ】表現者と音楽家の2つの顔 – 活動”凍結”~”解凍”、その後の角松敏生へ
ここまで1991~1993年の角松敏生がいかに魅力的なのか、について書いてきた。これまでの話をまとめつつ、解凍後の彼の音楽性と絡めて、角松敏生という人物について書いてみよう。
彼の中で、表現者としての角松と、音楽家としての角松がいる。この2つは彼の中では切ってもきれないもので、それは角松敏生と言う名義においては特にその傾向が強いと思っている。
彼は93年に表現者として絶望してしまったが、音楽家としてはピークをこれから迎えようとしていた。だからこそ、音楽家人生は止まることなくむしろ90年代後半に向けて活動は加速していく。
90年代初頭は、表現者・音楽家の2つの要素が、最も良いバランスで、かつ高いレベルで表現のアウトプットになっていたから、ここまで惹かれるのだろうと書いた。
しかし98年に解凍した時、つまり角松敏生という表現者としてカムバックした時、音楽家・表現者との歯車が微妙にかみ合わなくなっていた。
良い音楽を作る音楽家として5年間を生きてきた角松氏である。表現者として何を表現すれば良いのか、彼にとって模索の状況がやってきたのではないか、と想像する。
1991~1993年の時期に、女性への思いを描くという方法論は『君をこえる日』で完結させてしまった。そして1度その手法は手放し、新たに表現するものを見つけなければならなくなった。
2000年代前半頃までの彼の楽曲には、凍結前の気持ちを昇華させるような歌詞も見られ、まだ地続きであるように感じられる部分もあった。
そこに新たな表現の可能性を広げ始めた矢先、盟友である青木智仁・浅野祥之の2人が相次いで亡くなるという悲劇があった。
音楽家として、そして表現者としても角松敏生の土台を大きく揺るがす事態となってしまった。
確かに凍結までの彼の表現のあり方は、自らを痛めつけるものであり、望ましい在り方ではなかったのかもしれない。
しかし音楽家としては職人気質で、その一方で表現者としては奔放なやり方をしていたことが、角松敏生としての魅力だったようには思う。
奔放な表現者であることは、解凍後には若気の至りとして手放してしまったようだ。
ただ彼が音楽家として素晴らしい地位を築きつつ、角松敏生として何か成しえていない感じがするのは、やはり表現したくて堪らないものが見つからなかったからなのではなかろうか。
決して元に戻ることはないが、新たに彼の表現したいものを探す旅はまだ続いているように思う。
デビュー40年を迎え、次の新作が最後になるかもしれないという発言も聞かれる。しかしまだ角松敏生として、表現する何かははっきり見つかっていないようにも感じられるのだ。
ファンの願いとしては、それが見つかってもう一旗揚げる角松氏を、やはり願ってしまうのである。
次ページには、1991~1993年にリリースされたアルバム・ミニアルバムのレビューを書いている。
次ページ:1991年~1993年にリリースされた全アルバム・ミニアルバムレビュー
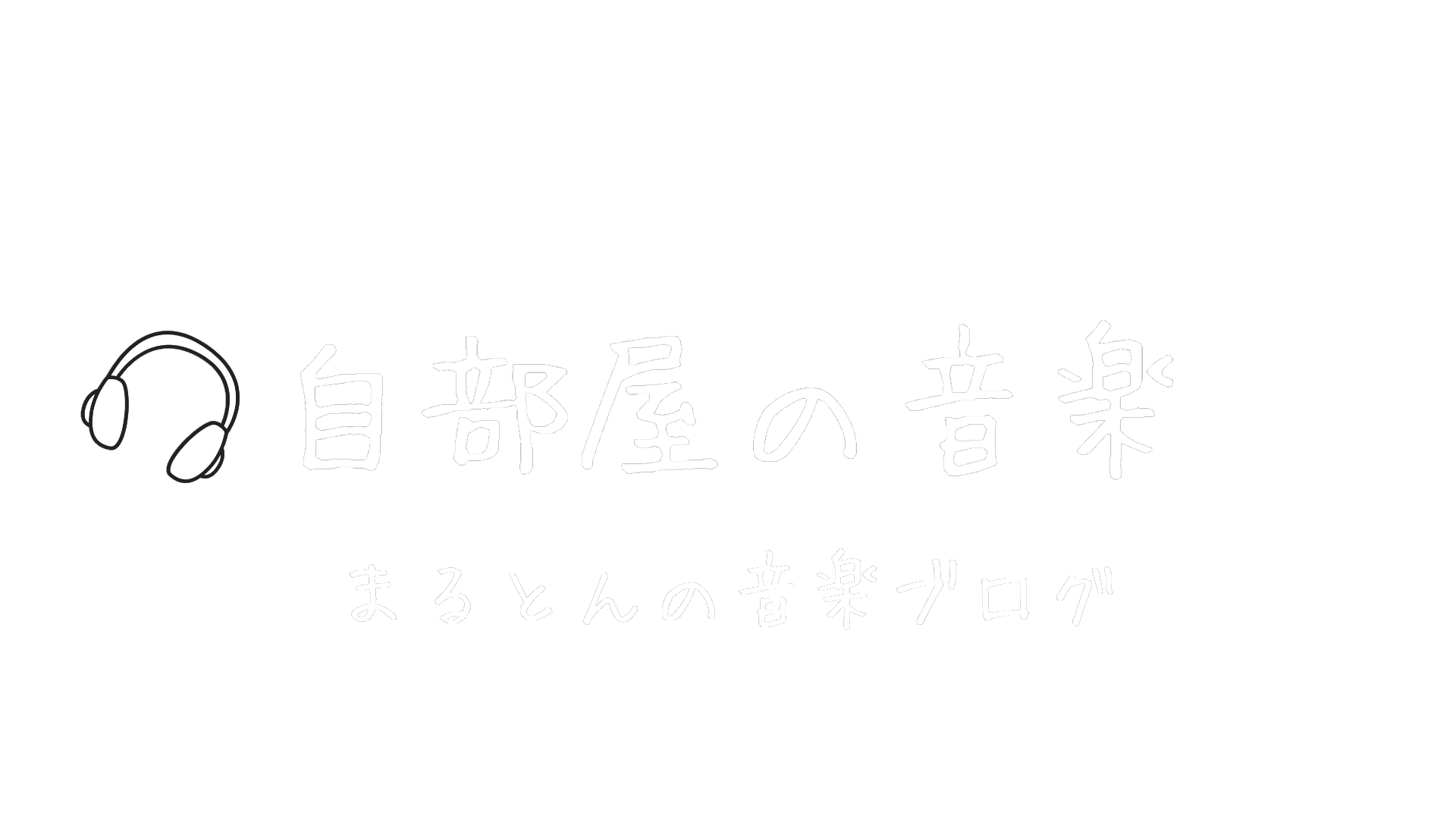























コメント