名盤の定義は実に様々である。アルバム全体の完成度の高さや個々の楽曲の良さもあるが、水が流れるように最後まで進むアルバムが個人的には好きだ。
近年はストリーミングで音楽を聴く人が多くなり、アルバムと言う単位自体にもこだわりのない人もいるのだろう。
しかしアルバム単位の良さは、レコードやCDという時間枠の中で、世界観を構築し、聴く者にとって心地好い流れを作り出すことであると思っている。
そこで今回は流れが良過ぎるあまり、気付くと最後まで聴いてしまうハードロック・ヘヴィメタルのアルバム10枚を紹介する。
流れが良過ぎて気付いたら最後まで聴いているハードロック・ヘヴィメタルのアルバム10選
今回は流れが良いアルバムとして、ハードロック・ヘヴィメタルのジャンルから10枚を選んだ。
「流れが良い」とは、途中で止めたくなるポイントがなく、展開も見事なアルバムのことを指している。
ハードロック・ヘヴィメタルの場合、スピーディーに展開するアルバムが多くなるが、必ずしもそれだけではなく、ヘヴィな作品でも時間を忘れて聴けてしまう作品が存在する。
とりわけ筆者がよく聴くアルバム10枚を選んで紹介しようと思う。作品はアルファベット順に並べている。
また「流れの良さ」「トータル完成度」の2点について3段階で評価した。流れの良さは今回の主目的であり、トータル完成度はそれに加えて作品の完成度が高いほど名盤と言える。
Black Sabbath – Sabbath Bloody Sabbath(1973)
- 流れの良さ:★★★
- トータル完成度:★★★
ヘヴィメタルに多大な影響を及ぼしたBlack Sabbathの5枚目のオリジナルアルバムである。ギターのトニー・アイオミが作るヘヴィなリフが特徴のバンドだが、本作は過渡期の作品と言える。
それはシンセサイザーやストリングスを用いて、これまでの野性味が抑えられて、より洗練されたサウンドに仕上がっている点が変化である。
そうした変化の兆しは前作『Black Sabbath Vol.4』にもあったが、これまでの路線との折り合いがまだつかず、楽曲が拡散している感じもあった。(名盤ではあるのだが)
一方で本作は楽曲の方向性がまとまり、ヘヴィなリフとシンフォニックな部分が見事に融合し、トータル的に分かりやすく、一気に聴ける作品に仕上がった。
冒頭のタイトル曲「Sabbath Bloody Sabbath」の印象的なパワーコードリフから美しいBメロ、そしてダークな後半へと素晴らしい展開の楽曲で掴みは満点である。
そして全8曲のうち「Fluff」「Who Are You?」がやや流れを変える楽曲として機能しながら、前後2曲ずつをセットにして聴くと、非常に流れが分かりやすいのが良い。
「Killing Yourself to Live」など楽曲の中でもヘヴィ一辺倒ではない、野性味とクラシカルな部分のバランスも絶妙で、それがアルバムトータルでも同じことが言える。
Budgie – Bandolier(1975)
- 流れの良さ:★★★
- トータル完成度:★★☆
3ピースによる70年代B級ハードロックの帝王とも言われるBudgieの5枚目のアルバムである。あまりブルース色がない上でヘヴィなブリティッシュハードロックと言う珍しいバンドだ。
人気が高いのは前作の『In for the Kill!』までのようだが、ドラムがスティーヴ・ウィリアムズになってからの本作は、ヘヴィ一辺倒ではないファンクっぽいビートが加わるようになった。
結果的に本作はそれまでのBudgieが持っていたハード・ヘヴィな部分と、より洗練されたサウンドや陽気な曲調が開眼して、バラエティ豊かなアルバムとなっている。
そしてそれだけでなく、非常にアルバムトータルとして聴きやすい作品になり、流れも抜群である。
陽気なリフながら展開が凝っている「Breaking All the House Rules」から始まり、新機軸の洗練された「Who Do You Want for Your Love?」などを挟んで前半が進んでいく。
後半はロックンロール的なノリもある「I Ain’t No Mountain」で盛り上げつつ、ラストはBudgieらしい重厚な「Napoleon Bona-Part 1 & 2」で締める。
Budgieらしさは少し薄まった作品であるが、流れの良さは素晴らしいものがある。
※Budgie(バッジー)のトニー・ボージ在籍後期における真のB級の魅力・作品紹介
Dizzy Mizz Lizzy – Alter Echo(2020)
- 流れの良さ:★★★
- トータル完成度:★★★
デンマークのバンドDizzy Mizz Lizzyが2020年にリリースした4thアルバムである。オルタナティブロックの佇まいとハードロックのリフを持ち、プログレ的展開が加わるバンドだ。
わずか2枚のアルバムを残して1998年に解散したが、2014年の二度目の再結成で本格的にバンド活動を再開し、よりヘヴィで豊潤なサウンドになって復活している。
前作『Forward in Reverse』では彼らの復活を告げるに相応しい、ハードさと泣きのメロディが詰まった分かりやすい作品となっていた。
それに対して本作は、まるで70年代のプログレ全盛期のような構成のアルバムとなっている。しかし前作以上にトータル感が見事というほかない出来栄えになっている。
基本的にアッパーな楽曲はなく、ゆったり~ミドルテンポの楽曲が占められている。導入的な「The Ricochet」から「In the Blood」で重厚にアルバムは幕を開ける。
基本的にはヘヴィなサウンドの中に、「The Middle」のような美しいメロディ、さらにはアンビエントなどに通じるような広がりのあるサウンドが本作の新境地とも言えるところだ。
そして何と言っても本作では、レコードで言えばB面いっぱいを使い、20分以上の組曲形式での「Amelia」が圧巻と言うほかない。
この組曲の中にDizzy Mizz Lizzyの魅力が全て詰まっていると言っても過言ではない出来であり、長い曲なのに目まぐるしく一気に聴けてしまう。
本作の心地好さはハードロックやプログレ、あるいはオルタナティブロックの枠をさらに飛び越え、アンビエントやドローンなども含むように思える。
より立体的で広がりのあるサウンドを目指した結果、古典的なロックの範疇には収まらなかったところが、本作の魅力とも言えるだろう。
人間椅子 – 踊る一寸法師(1995)
- 流れの良さ:★★★
- トータル完成度:★★★
ブリティッシュハードロックと日本文学が融合したバンド人間椅子の5thアルバムである。メジャーレーベルとの契約が切れ、インディーズからリリースされたのが本作だ。
本作の特徴は、メジャー時代に頑なに守ってきた幻想・怪奇の世界観を、少し打ち破るような自由な作風が全体を満ちているところである。
もちろんタイトル曲「踊る一寸法師」は江戸川乱歩の小説であり、人間椅子としての核は守りつつも、我々の日常に近いことや心の闇を描くような、これまでと異なる作風も見られる。
曲調としてもダークなヘヴィメタルだけでなく、フォークロックやスラッシュメタルなど、ハードロックの枠を超えた楽曲も存在している。
多様な楽曲がありながら、見事に1枚にまとまっている要因がアルバムの流れの良さにあると思う。シリアスな曲の合間に「ギリギリ・ハイウェイ」「羽根物人生」など箸休め的な曲が上手く機能している。
特にシリアスな路線も多い前半から「羽根物人生」「三十歳」と私たちの日常に近い文脈の楽曲が入って来ることで、『踊る一寸法師』というアルバムの旅のちょうど良い途中下車と言う感じがする。
これがあることで、終盤の「時間を止めた男」~「踊る一寸法師」まで新鮮な気持ちでまた聴くことができる。
そのため前半をじっくり聴いた後は後半があっという間に感じられ、気付いたら「踊る一寸法師」が終わっている、という感じである。
長過ぎず短過ぎず、ほど良いバランスで作られたアルバムとしては人間椅子の中でも随一の作品だろう。
※【人間椅子】ついに復活の大名盤『踊る一寸法師』レビュー+UHQCDとオリジナル盤の音質比較
Riot – Thundersteel(1988)
- 流れの良さ:★★☆
- トータル完成度:★★★
アメリカで長きにわたり活動し、ハードロックからスピードメタルに転身したバンドRiotの6thアルバムである。
ボーカルの交代に応じて音楽性が変化するバンドだが、1984年に1度解散を経験している。そしてボーカルにトニー・ムーアを迎えた再結成第1弾アルバムが本作だ。
それまでの野性味を感じさせるハードロックから一転し、当時の潮流でもあったスピードメタルを取り入れた作品となっている。
デビュー時から哀愁あるメロディラインは一貫しており、本作ではメロディの美しさに加えて、疾走感や攻撃性を兼ね備えた楽曲となっており、人気の高い作品でもある。
何と言ってもアルバム幕開けの表題曲「Thundersteel」は、スピード感のあるヘヴィメタルの教科書のような楽曲である。
疾走感とテクニカルなリフ、ツインペダルに速弾き・ツインによるソロと、この曲が好きにならなければ、おそらくヘヴィメタルは向いていないだろう、というくらいメタルの要素が詰まっている。
本作の魅力は、このタイトル曲に決して負けない楽曲がしっかりと次に続いていくところだ。疾走感のある「Fight Or Fall」にミドルテンポの「Sign Of The Crimson Storm」とバランスも良い。
「Johnny’s Back」までは一気に聴ける爽快感で、ようやく「Bloodstreets」でパワーバラードの登場である。終盤の流れは若干惜しいところもあるが、それがあってもなお名盤と言える。
楽曲の充実度では、実は次作『The Privilege Of Power』の方が濃密だったりするが、ストレートに聴けるのが本作の魅力だ。
聖飢魔Ⅱ – THE OUTER MISSION(1988)
- 流れの良さ:★★★
- トータル完成度:★★★
悪魔教の布教のために立ち上がった教団、聖飢魔Ⅱの第5教典である。1999年に当初の公約通り解散し、その後は周年ごとに再集結を行ってきた。
初期は創設者であるダミアン浜田殿下(当時)によるおどろおどろしいヘヴィメタルであり、その印象が後の活動においても強烈に影響を及ぼした。
ジェイル大橋代官脱退後は、構成員全員で曲を書く体制になり、音楽的にも広がりを見せた。本作はプロデューサーにレベッカの土橋安騎夫氏を迎え、音楽として売れるものを目指して作られた。
本作の特徴は、まず楽曲がポップなメロディを持ち、非常に分かりやすいということだ。先行シングルとなった「WINNER!」も分かりやすいハードロックナンバーであり、本作を象徴している。
そして壮大で宇宙的なサウンドを目指された通り、シンセサイザーなどを用いつつ、それだけにとどまらない非常に工夫を凝らした丁寧な音作りも魅力だろう。
これだけバラエティ豊かな内容なのに、アルバムとしての流れが抜群に良い。前半は一気に聴けて、「害獣達の墓場」でいったん落ち着いて、中盤戦へと入って行く。
エース清水長官色全開の「RENDEZVOUS 60 MICRONS’」やこれまでの聖飢魔Ⅱらしい「THE EARTH IS IN PAIN」などを見せつつ、後半はアップテンポな楽曲で一気に聞かせる。
そしてラストの荘厳な「THE OUTER MISSION」が見事にすべてをまとめてくれる。
聖飢魔Ⅱらしさと言う意味では他にも魅力的な作品はあるが、音楽的な意味で、またアルバムと言う単位として完璧に構築された作品ではないかと筆者は思う。
Slayer – Reign in Blood(1986)
- 流れの良さ:★★★
- トータル完成度:★★☆
アメリカのスラッシュメタルバンド、Slayerの3rdアルバムである。デビュー時から一貫したアグレッシブなスラッシュメタルで、2019年に解散するも、2024年に再結成が予定されている。
彼らの音楽性はエクストリームなメタルと言う印象があるが、本作以前の2ndまではまだNWOBHMの影響も感じられるようなスピード感のあるヘヴィメタル、という感じだった。
より速く、そしてより轟音で極悪なサウンドになったのが本作である。とにかく過激さが前面に出た本作はSlayerとしても、スラッシュメタルとしても1つの金字塔と言える。
何と言っても1曲目の「Angel of Death」の勢いと過激さは強烈である。まるで何かに急き立てられるような緊迫感とスリルは唯一無二と言うほかない。
基本的に本作は2分台の楽曲が多く、ジェットコースターのように展開していく。まるでパンクロックのようであるが、しっかりパンクとは異なるスラッシュメタルの質感になっている。
とにかく息つく間もなく進んでいくが、それが最高の心地好さであり、これまで紹介したアルバムの流れの良さとはやや異なる、展開のスピーディーさによる良さだ。
気付いた時には、雨の降る音が聞こえてきて「Raining Blood」まで到着する。一時の静寂が訪れたと思ったら、切り裂くような極悪なリフがやって来て、烈火のごとく本作が終了する。
作品のクオリティと言う意味では、ヘヴィな『South of Heaven』を経た後の『Seasons in the Abyss』を最高傑作に挙げる人も多い。
しかし流れの良さと言う意味において、最高の快感を与えてくれるのは本作である。
Tank – Honour & Blood(1984)
- 流れの良さ:★★★
- トータル完成度:★★☆
NWOBHMの時代に活躍したヘヴィメタルバンド、Tankの4thアルバムである。MotörheadとともにNWOBHM期にスピーディーなメタルを展開させたバンドの1つである。
Tankの魅力は大きく分けて2つあり、1つがNWOBHMらしい疾走感と、もう1つは哀愁を感じさせる泣きのメロディである。
デビュー時から2nd辺りは前者の魅力が強く、より荒々しい印象がある。3rd『This Means War』から4人編成になり、それまでに見られなかった抒情的なメロディが表に出てくるようになる。
そして本作『Honour & Blood』では、哀愁のメロディが最も目立つ作品となり、男らしい野性味と泣きのメロディが融合した、ファンに愛される作品となっている。
初期に顕著だった疾走感はやや引っ込んでいるが、それでもアルバム全体のまとまりと流れは素晴らしいものがある。
「The War Drags Ever On」では轟音で疾走しながらも、メロディやギターでは泣きの要素を見せる。
「When All Hell Freezes Over」で王道ハードロックを見せた後、最も泣きの要素が強い「Honour and Blood」への流れが素晴らしい。「Honour and Blood」はギターソロも泣きまくっている。
後半はややダークな雰囲気で進み、なんとAretha Franklinのカバー「Chain of Fools」も全く違和感なく収まっている。
中盤どっしりと聞かせて、「Too Tired to Wait for Love」「Kill」で加速させてアルバムは終了する。
疾走感から哀愁のメロディ、そしてヘヴィメタルとしての重厚感と、Tankの重要な要素を詰め込みつつ、見事にアルバムの流れとして作り上げた名作だと筆者は思っている。
Thin Lizzy – Thunder and Lightning(1983)
- 流れの良さ:★★☆
- トータル完成度:★★★
アイルランドにおける国民的バンド、Thin Lizzyの12thアルバムで彼らのラストアルバムである。ツインリード、特徴的なベースボーカル、フィルライノットの個性が光るバンドだ。
初期はアイリッシュフォークとロックの融合した音楽性で、ハードロックと言う雰囲気でもなかった。ツインリード体制になり、1976年にリリースされた『Jailbreak』でハードな路線が確立される。
70年代後半に絶大な人気を誇ったThin Lizzyであったが徐々に人気が低下した。一方でNWOBHMの時代にさしかかり、バンドはかつてTygers of Pan Tangにいたジョン・サイクスを加入させた。
こうして制作された本作は、彼らのラストアルバムながら、決して守りに入るのではない、新たなThin Lizzyのロックを作り上げることに成功している。
いわゆる”ヘヴィメタル”な雰囲気ではなかった彼らだが、1曲目「Thunder and Lightning」ではまさにヘヴィメタルの雷が落ちたような激しいサウンドに仕上がった。
本作はこれまでのThin Lizzyと、ジョン・サイクス加入に伴う新しい風が絶妙にブレンドされ、風通しの良さと流れるような配置が見事な作品である。
ハード一辺倒ではなく、味わい深い「The Sun Goes Down」やメロディアスな「The Holy War」など、聴かせる楽曲が配置されることで深みが増している。
ジョン・サイクスも作曲に参加した「Cold Sweat」もストレートで熱いハードロックである。本作では「Bad Habits」が昔ながらのThin Lizzyを思わせる楽曲で、これも良い味付けである。
ラストはストレートに「Heart Attack」で締められ、緩急のついた流れが見事である。
これまでの総決算的にまとめるだけでなく、新しい要素も含んだ意欲作は見事に成功した。この路線を続けるという選択肢が既になかったことで、かえって自由に作れたのかもしれない。
Venom – Black Metal(1982)
- 流れの良さ:★★★
- トータル完成度:★★☆
後のエクストリーム・メタルに絶大な影響を与えたバンド、Venomの2ndアルバムである。サタニックな世界観と、音質の悪さやがなり立てるボーカルなど、特徴的過ぎるスタイルが魅力である。
クロノス・マンタス・アバドンという3人によって、絶妙なバランスで成り立っていたのが初期のVenomである。そして危うさの上に成り立っていた最高のバランスは長続きはしなかった。
しかしそうしたバンドほど、ごく一部の期間に、あまりに優れた作品を残す。その中でも屈指の名作と言えば、本作『Black Metal』ではなかろうか。
タイトル自体が後にジャンル名となったほどであるから、相当なインパクトである。表題曲「Black Metal」は、謎の騒音のような音からイントロが始まっていく。
そしてクロノスの荒々しいボーカルとともに、スラッシュメタル的なビートが心地好く始まっていくのだ。
Venomの特徴として「音質の悪さ」があるが、実は酷いのは1st『Welcome to Hell』であり、本作はいくぶんか改善されている。
とは言え、地を這うようなおどろおどろしいサウンドであり、それが心地好い人にとっては最高の音質なのである。
しかし勢いや荒々しさだけでなく、本作は流れが非常によくできている。最初2曲で飛ばして、3曲目では「Buried Alive」でダークに聴かせる流れがまずは良い。
そして続ける形で「Raise The Dead」からはテンポ良く次々と曲が展開されていく。似たような曲が並んでいるように見えて、リズムパターンを巧みに変えながら、飽きさせない流れになっている。
「Countess Bathory」はエクストリーム・メタルのまさに祖とも言える楽曲で、不気味な「Don’t Burn The Witch」で締めくくられる。
おまけ的に次作「At War With Satan」のイントロだけが収録されているが、溢れんばかりのアイデアが本作には詰まっていることが窺える。
残念ながらこのバランスは次作の3rdでは徐々に崩れ始めていくのだが、奇跡的なバランスで成り立つ本作はぜひとも聴いてほしい名作である。
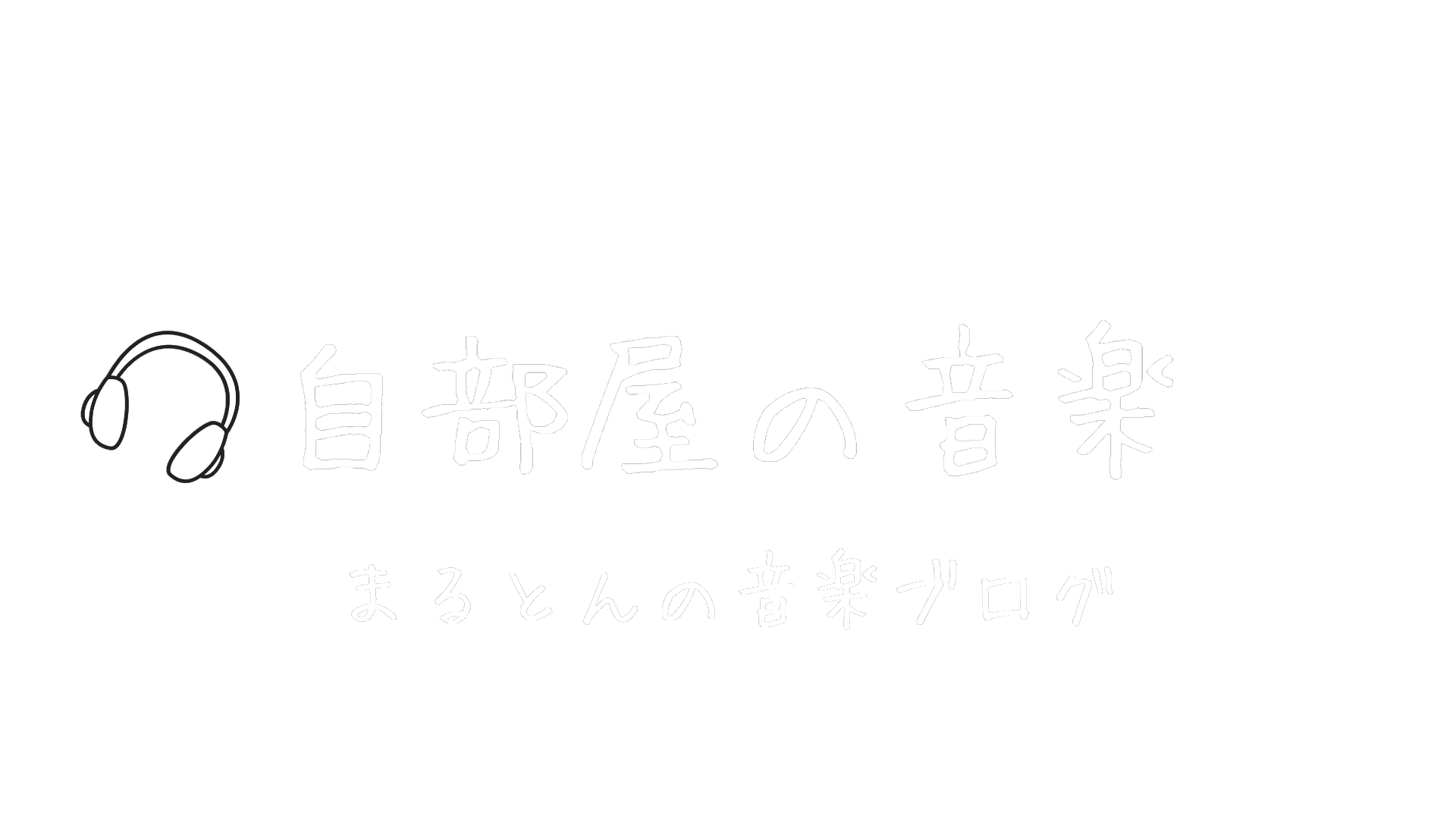























コメント