ここ数年、海外のロックバンドの来日公演ラッシュが続いている。ロック不毛の時代とも言える現代ではあるが、ベテランロックバンドの来日にファンは熱狂している。
筆者の好きなハードロック(ヘヴィメタルも含む)バンドの場合、いわゆる活動の”黄金期”のメンバーでずっと変わらず続いていることは、ほとんどない。
バンドの中心人物が1~2人残っていて、他のメンバーは代わっている場合が多い。
それでも往年の楽曲を披露してくれれば嬉しいのであるが、黄金期のメンバーで来日公演を観たかった、と思うバンドも多数ある。
今回は、”黄金期”のメンバー、さらにはその黄金期の時期に来日公演を筆者が観てみたかったバンドを特集する。
”黄金期”のメンバーで来日公演が見たかったハードロックバンド
今回の記事では、筆者が観てみたかった、”黄金期”のメンバーでの来日公演を考える記事である。
以下に7つのバンドを取り上げた理由について先に書いておくと、筆者がもし来日公演があったら、是非とも観てみたいと思うバンドであることがまずは条件である。
それととともに、黄金期に来日公演が実現していないバンドを優先的に選んだ。
来日の機運が高まらなかった以外にも、メンバーの脱退や死亡などにより、その実現が困難・不可能となったバンドなども含めている。
なお筆者の年齢的に70~80年代のハードロックバンドの黄金期を生で観ることが不可能であるため、実際に黄金期のメンバーで来日公演を行っているバンドは割愛したものもある。
加えて”黄金期”の定義も非常に難しいものである。筆者の主観がかなり入るが、最もバンドとして勢いがあり、優れたアルバムを残している時代を選んでいる。
各バンドの”黄金期”について、そして実際の来日の有無などをまとめることにした。
順番はアルファベット順である。
Black Sabbath
イングランドのバーミンガム出身、1970年にデビューしたBlack Sabbathである。
彼らの黄金期と言えば、ボーカルにOzzy Osbourneが在籍し、Tony Iommi(ギター)、Geezer Butler(ベース)、Bill Ward(ドラム)の4人だった時代で異論はないだろう。
つまりデビューから、1978年に『Never Say Die!』をリリースした後にOzzy Osbourneが解雇されるまでの時期である。
彼らの音楽性は、後のヘヴィメタルと呼ばれるジャンルの土台となったもので、ヘヴィなTony Iommiのギターリフを中心に、おどろおどろしい世界観とサウンドが特徴である。
やはりOzzy Osbourne脱退後のBlack Sabbathにおいては、この独特のヘヴィさは再現されることがなく、オリジナリティ4人でしか出せない唯一無二のサウンドとグルーヴであった。
なおオリジナルメンバーでの来日公演は実現しておらず、1980年にRonnie James Dioがボーカルの時代、1989~1995年にかけてTony Martin時代に合計4回の来日ツアーが行われていた。
唯一、ドラムのBill Wardを除く3人で再結成した際の、2013年Ozzfest Japan 2013での来日公演があった。筆者はこの公演には参加することができ、3/4のオリジナルBlack Sabbathを目撃できた。
なお2025年7月5日には最後の公演として、英バーミンガムのヴィラ・パークにて、キャリアを締めくくる『Back To The Beginning』を開催し、多数のミュージシャンがゲスト出演した。
その後、同22日にはボーカルのOzzy Osbourneが死去した。まさにOzzy Osbourneがこの世界にお別れを告げる、伝説的な公演となった。
この時が最後のオリジナルメンバーでのコンサートとなり、ついにオリジナルメンバーでの来日公演は実現しないままとなった。
YouTubeで公開されている1970年のライブ映像を見ると、やはりこのメンバーでの演奏のタフさやスリリングさなどを感じることができる。
ヘヴィメタルの元祖とも言われるものの、もともとブルースバンドから始まったバンドだけに、活動初期のライブでの生っぽいグルーヴを体感してみたかったものだ。
※【初心者向け】”はじめてのアルバム” – 第19回:Black Sabbath オリジナルメンバーの名盤紹介
Budgie
ウェールズのカーディフ出身、1971年にデビューを果たしたのがBudgieである。
セキセイインコを意味する口語をバンド名にしたが、その可愛らしいバンド名に反して、Black Sabbathと同様、ヘヴィで湿り気のあるサウンドで独特の魅力を持つバンドである。
彼らの場合、爆発的なヒットを果たしたという意味での”黄金期”ではなく、後進のバンドへの絶大な影響力を持つと言う意味では、活動初期が”黄金期”と言えるのではないか。
それはオリジナルメンバーである、Burke Shelley(ベース・ボーカル)、Tony Bourge(ギター)、Ray Phillips(ドラムス)の3名の時代(1968~1973年)である。
デビューアルバム『Budgie』、2nd『Squawk』、3rd『Never Turn Your Back On a Friend』の3枚の時代であり、とりわけ3rd収録の「Breadfan」が彼らの有名の楽曲である。
Metallicaがカバーしたことで注目され、日本のハードロックバンド人間椅子はオリジナル詞をつけて「針の山」としてカバーしている。
Budgieはブルース的な重さとは異なる、シンプルながら独特のヘヴィさが魅力であり、1stアルバム収録の「Guts」などに象徴される。
Budgieは来日公演を行ったと言う情報はなく、日本での注目度は低かったことが窺える。3rdアルバム頃の時代に3人のヘヴィな演奏を聴いてみたかったものである。
後に名だたるヘヴィメタルバンドの面々が熱狂したBudgie節を生で堪能してみたかった。
個人的にはドラマーがSteve Williamsに代わった70年代中盤のBudgieも、ファンクっぽいビートの渋いハードロックが味わい深いので、この時代も聴いてみたかったところだ。
なお2011年にバンドの中心人物であったBurke Shelleyが大動脈瘤の緊急手術により、事実上の解散となっており、2022年にBurke Shelleyは死亡している。
※【初心者向け】”はじめてのアルバム” – 第8回:Budgie 名曲”Breadfan”の入っているアルバムを最初に聴くのが本当に良いのか?+全アルバムレビュー
Captain Beyond
1972年にアメリカで結成されたハードロックやプログレッシブロックのバンド、Captain Beyondである。
スタジオアルバムは3枚しか残しておらず、1972年から1978年が主な活動時期で、メンバー変更も多いバンドであった。
結成当時のメンバーからしてスーパーバンドだった。
初代Deep PurpleボーカルのRod Evans、Iron Butterflyに在籍したLarry Reinhardt(ギター)、Lee Dorman(ベース)、Johnny Winterらと活動していたBobby Caldwell(ドラムス)の4人である。
この第1期メンバーで録音された1st『Captain Beyond』が1972年にリリースされた。短い活動期間ではあるが、やはりこの時のメンバーが”黄金期”と言って良いだろう。
Captain Beyondに関する詳しい情報を知らずとも、この1stアルバムはハードロック好きの間では傑作とした語り継がれているアルバムである。
単なるハードロックではなく、変拍子を巧みに使ったプログレッシブロックのアプローチが上手く取り入れられ、緊張感が保たれたアルバムとなっている。
やはり1曲目の「Dancing Madly Backwards (On A Sea Of Air)」がこの時期のCaptain Beyondを象徴しており、ヘヴィでありながら技巧的なリズムが非常にスリリングでカッコいい。
アルバムも曲が続いている部分があるなど、トータル感も非常に良い作品で、高い充実度を誇る。
ドラマーが交代した1973年の2nd『Sufficiently Breathless』も隠れた名盤ながら、ブラックミュージックの色合いが強まって、また違った味わいになっている。
やはりライブで観てみたかったのは、古き良きハードロックを感じられる第1期のメンバーの時代である。
きっとライブでは、よりスリリングな演奏で1stアルバムの世界観を表現してくれたのではないか、と想像するところである。
Riot
アメリカ出身で1977年にデビューしたヘヴィメタルバンドがRiotである。
創設メンバーであったMark Reale(ギター)を中心として長らく活動したバンドであるが、メンバーの交代も多く、時代によって音楽性も異なるバンドである。
デビュー時のメンバーは、Guy Speranza(ボーカル)、Mark Reale(ギター)、Lou A. Kouvaris(ギター)、Jimmy Iommi(ベース)、Peter Bitelli(ドラムス)であった。
Riotの”黄金期”を決めるのは非常に難しいが、筆者としては2つの山があったように感じている。1つはデビュー時、Guy Speranzaがボーカルの時代である。
デビューアルバム『Rock City』はアメリカンなハードロックが主体にはなっている。
しかし「Warrior」で見せる疾走感と哀愁あるメロディ、そしてツインギターという後に王道メタルと言わしめる要素がここで開眼している。
続く2nd名盤『Narita』におけるタイトル曲にしてインストナンバー「Narita」においても、ツインリードによる哀愁が漂い、アメリカンなハードロックにはない独特な魅力がある。
もう1つの山は、Tony Mooreが在籍し、ヘヴィメタルの王道とも言える1988年の『Thundersteel』の頃である。
既にスラッシュメタルやパワーメタルが登場していた時代、Riotがもともと持っていた哀愁やメロディの美しさと、攻撃的なヘヴィメタルのサウンドが融合した名盤である。
デビュー時のようなアメリカンなハードロック要素はなくなり、かなり音楽性において変化を遂げたバンドであると言える。
それゆえ、どちらの時期のライブも観てみたかったが、個人的にはその時代に来日は実現していなかったGuy Speranza時代が観てみたいところである。
70年代の終わり、ヘヴィメタルの時代に入ろうとする頃にあって、ハードロック的なサウンドや佇まいを持った最後の世代のバンドでもあったように思える。
なお筆者がRiotの来日公演を観たのは、創設メンバーのMark Reale亡き後、RIOT Vとして来日した際のコンサートだった。
Thin Lizzy
アイルランド出身のハードロックバンド、Thin Lizzyである。
初期こそハードロックではなかったが、ツインリード体制となり、アイリッシュ音楽を取り入れた独特なハードロックは多くのファンを魅了した。
ベース・ボーカルであるPhil Lynottの個性こそThin Lizzyの魅力である。
しかし彼は1986年に若くして亡くなっており、結成の1969年から1983年のラストアルバム『Thunder and Lightning』までが主たる活動期間である。
やはりThin Lizzyの黄金期と言えば、ツインリード体制となり、アイリッシュ音楽を取り入れつつ、ハードなサウンドを確立した時代である。
具体的には1974年頃から、Phil Lynott(ベース・ボーカル)、Scott Gorham(ギター)、Brian Robertson(ギター)、Brian Downey(ドラムス)の時代である。
1975年の『Fighting』でスタイルを確立し、1976年の『Jailbreak』が1つの到達点となった。「The Boys Are Back in Town」など、どこか陽気な雰囲気のあるハードロックが魅力である。
そしてバンドにはたびたび参加していたGary Mooreが在籍していた時期も魅力的だ。1979年の名盤『Black Rose a Rock Legend』では正式メンバーとして音源にも参加していた。
ケルト音楽と融合したタイトル曲「Black Rose: A Rock Legend」は、非常に完成度の高い楽曲でありつつ、Thin Lizzyの持つ優しげな雰囲気も健在の名曲である。
Thin Lizzyはこの『Black Rose a Rock Legend』の時代に来日ツアーを行っており、もしその時代を生きていたら絶対に観に行きたかったコンサートである。
ただそれ以前の時代は来日公演がないため、個人的には1974年の『Nightlife』の時代、つまり後のハードロック路線と、それ以前の渋いロックの過渡期の時代のライブも観てみたかった。
そして何よりPhil Lynottのプレイやボーカルを聴いてみたかったものである。
Venom
イングランド出身、1981年にデビューしたバンドVenomである。
いわゆるNWOBHMのムーブメントにあるバンドながら、悪魔的な歌詞と粗削りで不気味なサウンドが独特な立ち位置のバンドである。
バンド自体はあまりセールス的に成功しなかったが、その独特なスタイルが、エクストリームなメタルに多大なる影響を与えたバンドなのだ。
Venomの黄金期はとても分かりやすい。まさにオリジナルメンバーである、Cronos(ベース・ボーカル)、Mantas(ギター)、Abaddon(ドラムス)の3人による初期の頃である。
Venomの唯一無二の個性は、この3人が1980年代前半に生み出した独特な楽曲の中にこそあり、そのバランスはとても危ういものだったのが分かる。
とりわけデビューアルバム『Welcome to Hell』と2nd『Black Metal』にVenomの良さのほとんどが詰まっていると言ってもよい。
1stにはスラッシュメタルの元祖ともいえる不気味な爆速チューン「Witching Hour」のインパクトは絶大であり、軽快な「Welcome to Hell」も良曲である。
また2ndにはタイトル曲「Black Metal」もまたスラッシュメタルの快感を詰め込んだ楽曲であり、エクストリームな「Countess Bathory」など名曲ぞろいだ。
3rd『At War with Satan』も力作ではあったが、既にバンドのバランスは崩れ始めており、後にはメンバー交代を繰り返すことになる。
Venomが来日したのは、1987年のツインギター体制となった『Calm Before the Storm』リリース前のことだったと言う。(これはこれで実は名作なのであるが)
やはりVenomは初期のオリジナルメンバーで、『Black Metal』リリース後のセットリストで来日公演を観てみたかった。
きっと恐ろしいほどに荒々しく、ライブ会場の雰囲気もめちゃくちゃになるのだろうが、そうしたロックの”いかがわしさ”のようなものを醸し出せるバンドは、今となってはとても貴重である。
※【初心者向け】”はじめてのアルバム” – 第11回:Venom 最強のB級メタルバンドの歴史的名盤は?
Wishbone Ash
イングランド出身、1970年にデビューしたツインリードが魅力のバンドがWishbone Ashである。
彼らの音楽性は、ブギやブルースなどを出発点にしながら、プログレ風味やフォークなどを感じさせるロックであり、ツインリードギターによる美しくも味わい深い楽曲が魅力的である。
まさにブリティッシュロックというクラシカルで美しい部分を持ちながら、アメリカンロックにあるブルース色のどちらも楽しめるところも、個人的には魅力である。
そうした魅力に満ちているのが、やはりデビューから名盤3rd『Argus』までの時代であり、ここを”黄金期”としたいと思う。
Martin Turner(ベース・ボーカル)、Andy Powell(ギター)、Ted Turner(ギター)、Steve Upton(ドラムス)の4人による編成である。
先ほども述べた通り、ブリティッシュな雰囲気の美しい楽曲が魅力であり、たとえば3rdアルバムの「The King Will Come」などはコーラスとギターの美しさが前面に出ている。
一方でハードブギと言った感じの、2ndアルバムから「Jail Bait」などはシンプルに身体が動き出すような楽曲で素晴らしい。
Wishbone Ashは1970年代に来日公演が実現しており、その注目度は高かったことが窺える。ただし初期のメンバーでの来日公演は実現しなかった。
70年代中盤以降のWishbone Ashはポップな作風になったり、またロック寄りになったりと方向性を模索していくことになる。
やはり3rdアルバム頃までの、ロックバンドとしての荒々しさを残しつつも、叙情的で繊細なメロディやアレンジに気高さすら覚える雰囲気のライブを観てみたかったものである。
まとめ
今回は”黄金期”の頃に来日公演が実現していたら、観に行ってみたかったハードロックバンドの紹介を行った。
時代が合えば観られたバンドもあるが、なかなか日本において評価がそれほど高くなかったために、来日公演に至っていないバンドも多かった。
改めてコンサートにおいて生演奏を観られる、ということは奇跡的なことなのだと思う。ぜひ観たいと思ったバンドは、万難を排してでも観に行くべきなのである。
とりわけ機会の少ない国外のバンドについては、琴線に触れたものはチャンスを逃さないようにしたいところだ。
※ハードロックとヘヴィメタルの違いは結局何なのか? – 歴史的変遷からざっくりと理解する
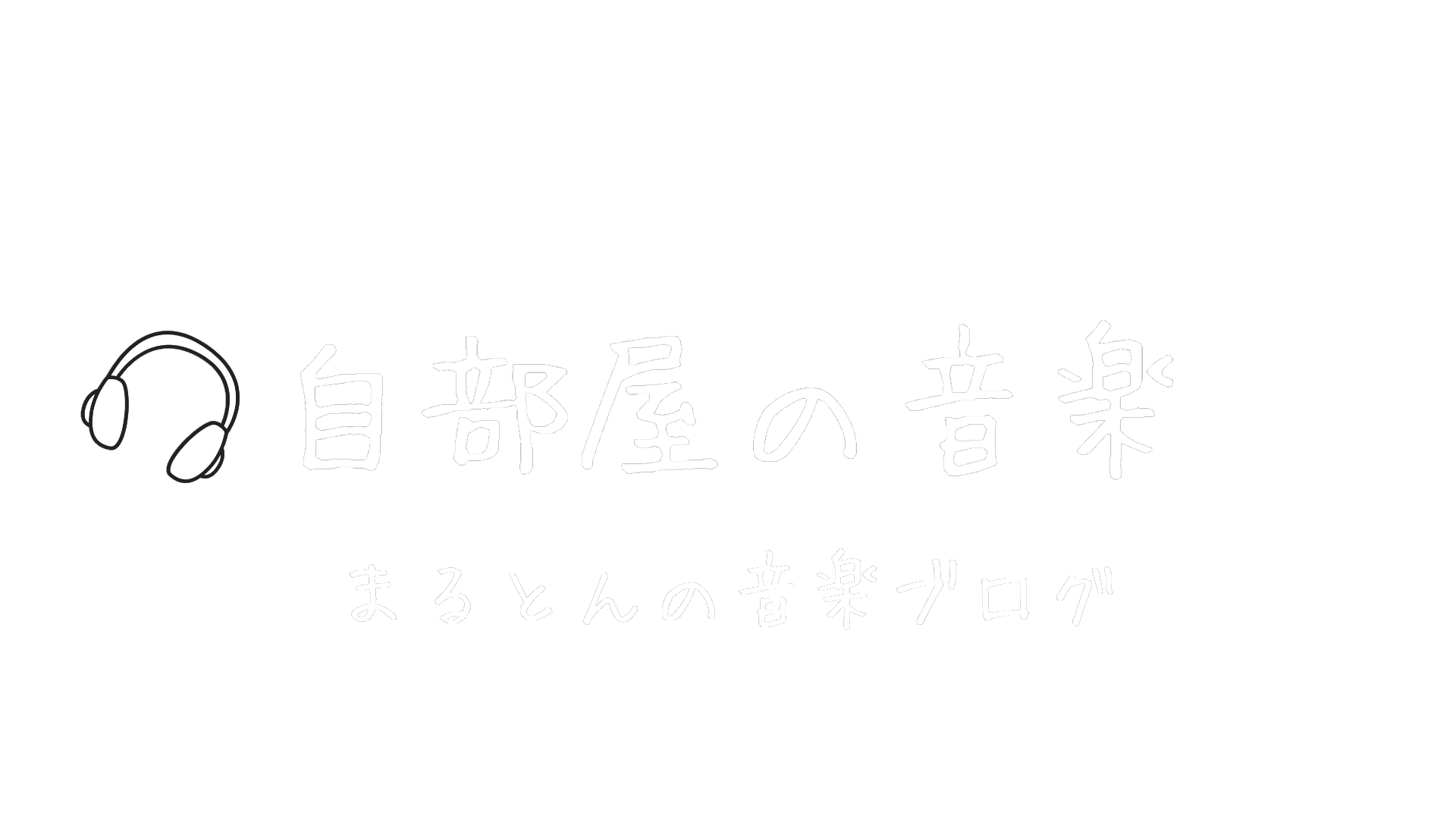


















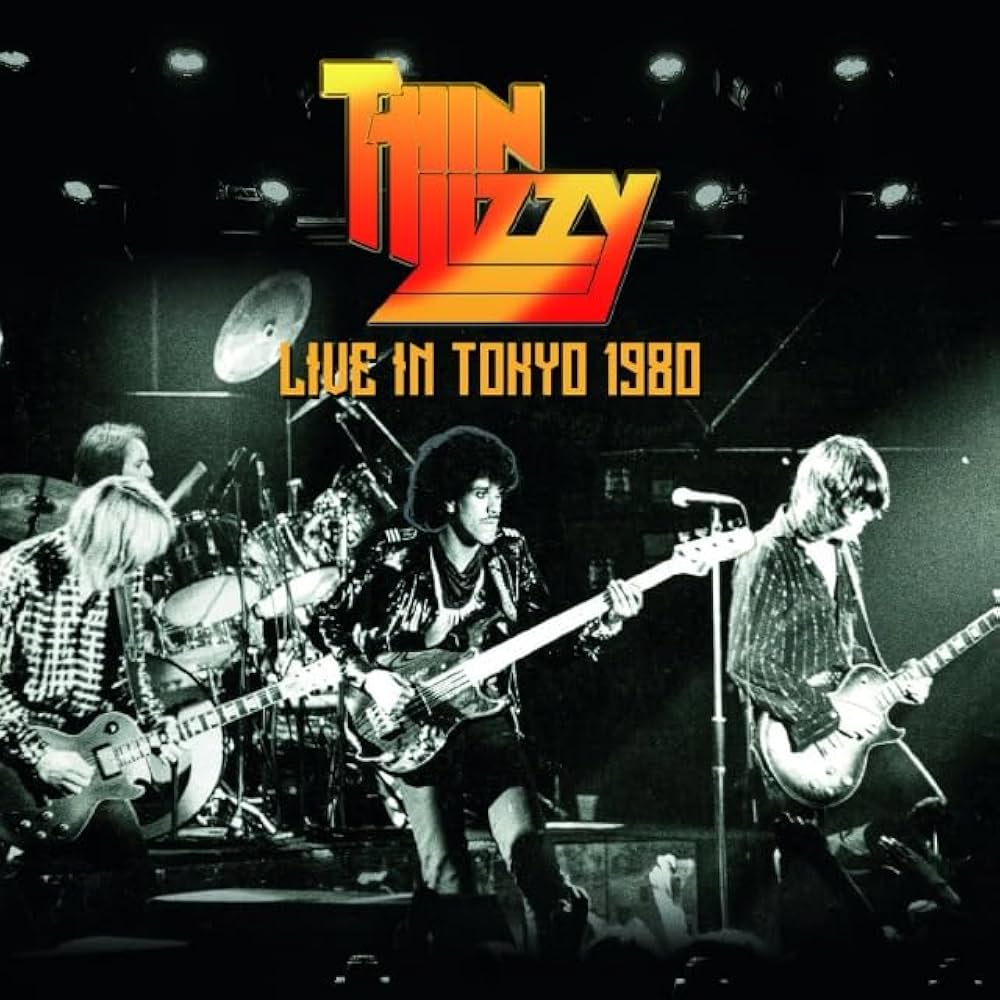






コメント