2025年7月5日にラストコンサート『Back to the Beginning』を開催し、イギリスのハードロックバンドBlack Sabbathは50年以上にわたるキャリアを締めくくった。
そのわずか17日後、オリジナルメンバーのOzzy Osbourne氏が亡くなり、正真正銘のラストコンサートとなった。
そんなBlack Sabbathの代表曲を1曲だけ挙げるとしたら、どの曲が選ばれるだろうか。多くの人の間で「Paranoid」で一致するのではないか、と思う。
『Back to the Beginning』でも最後に披露されたこの曲、なぜここまで愛される楽曲なのだろうか?
コアなファンであれば、他にもBlack Sabbathの中には優れた楽曲が多数あると言いたくもなろうが、やはりこの曲が真っ先に挙がる理由は何なのだろうか。
今回はBlack Sabbathの「Paranoid」がこれほどまで愛される理由について、楽曲の考察を試みた記事である。
「Paranoid」について
- 作詞・作曲:Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward, and Ozzy Osbourne
- 時間:2分52秒
- 収録アルバム:2nd『Paranoid』(1970)
まずはBlack Sabbathの「Paranoid」について概要をまとめておきたい。
「Paranoid」は、1970年リリースの2ndアルバム『Paranoid』のタイトル曲である。(もともとは「War Pigs」がアルバムタイトルになる予定だったという)
なおシングルカットされており、イギリスでのシングルチャート(1970-1971)では最高4位であった。
アルバム制作にあたり、既にできていた曲だけで尺が余ったため、3分ほどの曲が必要なって作られたという。
Tony Iommiがリフを作り、Geezer Butlerが歌詞を書き、Ozzy Osbourneが歌いながら歌詞を読んで出来上がったのだそうだ。
”つなぎ”の曲として作られたのだが、圧倒的な人気を誇る楽曲であり、近年はライブの最後に披露されることが多かった。
その人気はサブスクやMVの再生回数に表れており、Spotifyの再生回数は2024年3月に10億回を突破し、現在(2025年8月)は14億回を超えており、Black Sabbathの中でダントツ1位である。
またYouTubeに公開されている公式のMVは、3億4000万回以上(2025年8月時点)再生されている。
なおタイトルの意味は、偏執症(患者)であり、被害妄想のある人物について歌ったものである。
Tony Iommiのパワーコードが主体となった曲であり、ギターソロは左チャンネルのドライ信号で、リングモジュレーターを通して右チャンネルに送られることで、あの金属的なサウンドが出来上がる。
「Paranoid」はなぜこれほどまでに愛される楽曲なのか?
冒頭にも書いた通り、Black Sabbathの代表曲を1曲だけ挙げるとすれば、多くの人が「Paranoid」を挙げるのではないか、と思う。
一方でBlack Sabbathを深く愛するファンであれば、「Iron Man」「Snowblind」「Sabbath Bloody Sabbath」など、フェイバリットな楽曲は様々に挙げられることだろう。
しかしやっぱり「Paranoid」がより広い層にまで受け入れられ、愛されるには理由がありそうである。言い換えれば、ここまで再生回数が多く、たくさん聴かれる理由のことである。
もちろん「ヘヴィメタルの元祖となるような曲」とか「リフのカッコよさ」など、Black Sabbathとしての魅力やヘヴィメタルとしての良さは、大前提としてあり、語り尽くされてきたことだろう。
ここでは少し角度を変えて、楽曲としてなぜここまでたくさん聴かれるのか、と言う点に注目してみたい。
そうすると「とにかく繰り返し聴きたくなる」という要素が見えてくる。それは中毒性と普遍性の2つである。
耳に残る歌とメロディの中毒性
音楽において、楽器の演奏ができなくても、まず耳に入って心を掴むのが歌とメロディである。「Paranoid」の歌・メロディにはどうやら中毒性がありそうである。
まず「Paranoid」のメロディは、あまり上下が大きくない平坦なものではあるが、そこはかとない哀愁が漂うようなメロディである、と筆者は考える。
いわゆるポップス・歌謡曲のような彩り豊かなメロディラインではなく、鼻歌で歌えるような気軽さのあるメロディであるところに、妙な中毒性があるような気がしている。
そしてそのメロディを、ボーカルのOzzy Osbourneが歌っているところにも不思議な魅力がある。彼の歌はあまりビブラートをかけず、平坦に歌うのが特徴だと言われている。
この曲の淡々としたメロディが、彼の歌と見事にマッチしているところも良かった点であろう。
またそこはかとない哀愁は、Tony Iommiの作り出したリフやコード進行にありそうだ。Em→C→Dというヘヴィメタルの王道進行を上手く取り入れて、哀愁を漂わせている。
歌うのに難しすぎず、それでいて耳に残って離れないメロディと言うのは、ジャンルに関わらず人の心を掴むのではないか、と思っている。
似たような形で代表曲となっているのは、Judas Priestの「Breaking The Law」である。実はジューダスバージョンの「Paranoid」ではないか、と思っている。
「Breaking The Law」もメロディは比較的平坦であるが、リフやコード進行でそこはかとない哀愁を醸し出している点で、「Paranoid」に似ている。
そして多数の代表曲がありながら、何だか上位に挙がって来る点においても似ているのだ。
両者ともにコアなファンは「もっと良い曲もあるのだが」と付け加えたくなるのだが、この中毒性はライトなファンを強く巻き込める力を持つものである。
平たく言えば、”とっつきやすさ”があり、平坦でそこはかとない哀愁のあるメロディは、ハードロック・ヘヴィメタルにおいて特につい何度も聴きたくなるものだろうと思う。
”ハードロック過ぎない”演奏による楽曲の普遍性
「Paranoid」の歌とメロディの中毒性とともに、楽曲の普遍性の要素も大きいのではないか、と思う。言い換えれば、1970年代のハードロック”過ぎない”演奏や佇まいである。
1970年代のハードロックから、ヘヴィメタルへの架け橋となるような名盤『Paranoid』にはBlack Sabbathらしいハードロックが多数収録されている。
何をもって”ハードロックらしさ”とするのか様々な議論はあろうが、たとえばハードかつヘヴィな演奏と、巧みな展開で見せる「War Pigs」などはその典型であろう。
また「Iron Man」のようなキャッチーなリフもハードロックらしいものであり、中間にはやや唐突な展開があり、これもまたハードロックらしいスタイルと言える。
あるいは不気味でおどろおどろしいリフも特徴であり、「Electric Funeral」などがその真骨頂である。
このようにリフを主体とし、ハードかつヘヴィさのある演奏と、作り込まれた展開などのアート性を持つものがハードロックの1つの様式と言えそうだ。
一方の「Paranoid」は、その成り立ちが”つなぎ”の曲であり、あっという間に”できてしまった”曲であるためか、実は”ハードロック過ぎない”演奏や展開なのだ。
非常にシンプルで淡々としたビートで、展開はほぼなく、パワーコードを用いた簡素な演奏に終始している。言ってしまえば、非常にミニマルな音楽なのだ。
こうした簡素でいて、攻撃的な部分を持った「Paranoid」は、後にスピードメタルなどに影響を与えたものとは思われる。しかしまだそうしたジャンルに比べれば、落ち着いた演奏と言えなくもない。
こうしたいかにも70年代ハードロック然としていない、簡素でミニマルな演奏が、むしろ古さを感じさせない普遍性に繋がっているような気がしている。
またこのミニマルさがクセになって、中毒性をもたらしている、とも言えるだろう。
変な想像かもしれないが、「Paranoid」はニューウェイヴやテクノのようなビートに乗っけたとしても、成立しそうな楽曲なのではないか、と思っている。
ダンスミュージックのようなビートにも乗せられそうであるし、そうした楽曲としての間口の広さとでも言うべき要素が、より幅広い層に受け入れられる土台になっている気がする。
まとめ
今回はBlack Sabbathの「Paranoid」がなぜこんなに愛される楽曲なのか、について書いた。
まとめると、”つなぎ”の曲として作られたこの曲は、ややBlack Sabbathの他の曲とも異なる位置づけにあるように、筆者には思われる。
たとえばそれは平坦で口ずさみやすいメロディと歌であり、ハードな演奏よりも、そちらに耳が行きやすく中毒性のある曲になっている。
こうした傾向はJudas Priestの「Breaking The Law」にもあることを指摘した。
加えて、70年代ハードロック然とし過ぎていない、ミニマルな演奏が古さを感じさせず、ジャンル的にも普遍性を持った楽曲になっている点も指摘できる。
Black Sabbathの中で、彼ら”らしい”曲やハードロックとしてのカッコよさであれば、もっと別の曲も出てこようが、何だか耳から離れなくて聴いてしまう、そんな曲が「Paranoid」なのだ。
これが音楽的にライトなファンも巻き込んでいる点であり、それがけた外れの再生回数に繋がっているように思われる。
※【初心者向け】”はじめてのアルバム” – 第19回:Black Sabbath オリジナルメンバーの名盤紹介
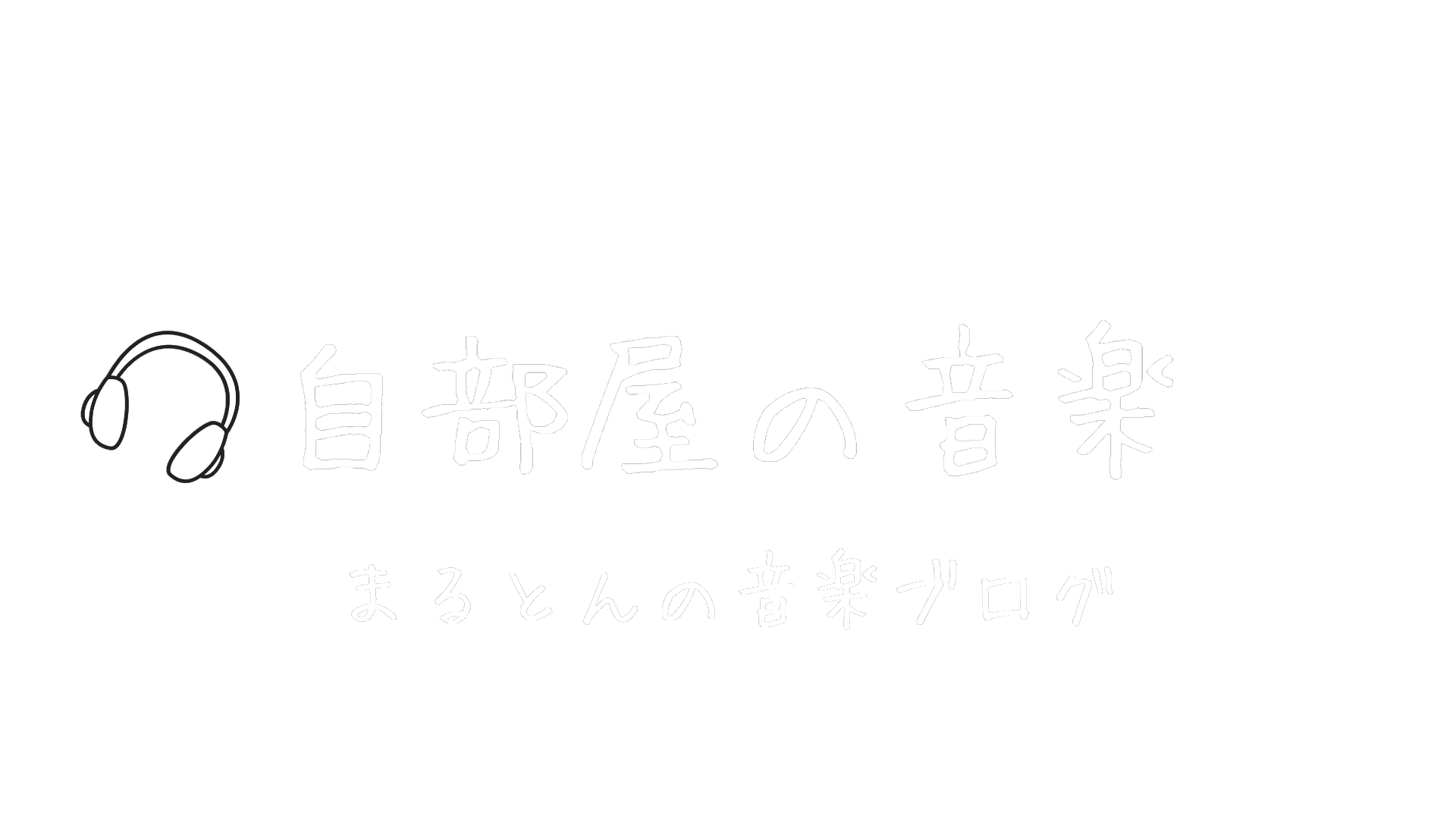




















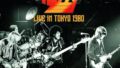

コメント