バンド生活三十五周年を迎えたハードロックバンド人間椅子は、これまで23枚のオリジナルアルバムをリリースしてきた。
今年2025年で発売から25周年を迎えるアルバムが、2000年発売の9thアルバム『怪人二十面相』である。
バンド名である『人間椅子』を書いた小説家江戸川乱歩の『怪人二十面相』をタイトルに冠したところから、まさに原点回帰とも言える。
一方であまり人間椅子の歴史をバンドメンバー自らが語る中ではあまり名前の登場しないアルバムのように思える。
それは必ずしも作品の質が低い、という意味ではない。むしろ隠れた名作であり、人間椅子の作品の中ではもっと評価されても良いと感じる名盤である。
今回は人間椅子の『怪人二十面相』のレビューを行い、その魅力とともにあまり話題に上がらない理由についても触れてみることにした。
アルバム『怪人二十面相』について
前半では、人間椅子の『怪人二十面相』について、アルバムの基本情報に加えて、当時の人間椅子の雰囲気についてまとめることにした。
作品の概要
- 発売日:2000年6月21日、2016年11月2日(UHQCD再発)
- 発売元:メルダック、徳間ジャパンコミュニケーションズ(UHQCD再発)
- メンバー:和嶋慎治 – ギター・ボーカル、鈴木研一 – ベース・ボーカル、後藤マスヒロ – ドラムス・ボーカル
| no. | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怪人二十面相 | 和嶋慎治 | 鈴木研一 | 6:45 |
| 2 | みなしごのシャッフル | 和嶋慎治 | 和嶋慎治 | 4:22 |
| 3 | 蛭田博士の発明 | 和嶋慎治 | 鈴木研一 | 5:46 |
| 4 | 刑務所はいっぱい | 和嶋慎治 | 和嶋慎治 | 5:25 |
| 5 | あしながぐも | 鈴木研一 | 鈴木研一 | 5:08 |
| 6 | 亜麻色のスカーフ | 和嶋慎治 | 後藤升宏 | 4:31 |
| 7 | 芋虫 | 鈴木研一 | 鈴木研一 | 8:41 |
| 8 | 名探偵登場 | 和嶋慎治 | 和嶋慎治 | 2:39 |
| 9 | 屋根裏のねぷた祭り | 鈴木研一 | 鈴木研一 | 7:22 |
| 10 | 楽しい夏休み | 和嶋慎治 | 和嶋慎治 | 6:01 |
| 11 | 地獄風景 | 鈴木研一 | 鈴木研一 | 3:29 |
| 12 | 大団円 | 和嶋慎治 | 和嶋慎治 | 8:15 |
| 合計時間 | 68:24 |
『怪人二十面相』は、2000年6月21日にリリースされた人間椅子の9枚目のオリジナルアルバムである。当時のメンバーは和嶋慎治・鈴木研一・後藤マスヒロの3人だった。
なお2016年にUHQCDとしてリマスター再発が行われている。
帯惹句は、「人間椅子が描く「音楽による犯罪」あの怪人二十面相がここに復活した!」であった。
タイトルになった『怪人二十面相』は、バンド名の『人間椅子』を書いた江戸川乱歩による小説である。アルバム名に小説のタイトルを借りるのは1995年の5th『踊る一寸法師』以来だった。
江戸川乱歩を取り上げたことで、当時としては”原点回帰”のテーマと語られることもあった。
本作がやや異色であるのは、『怪人二十面相』の世界観でアルバムの世界観が緩やかに統一されたコンセプトアルバムであるということである。
これまでも小説のタイトルを冠した作品はあったが、楽曲同士の統一感はあまりなかった。本作では登場人物をイメージさせる楽曲が散りばめられている点が異色である。
また1999年の前作『二十世紀葬送曲』でも、20世紀の終わりを題材にしたが、本作こそ真に20世紀最後の作品となった。そのためタイトルに”二十”を入れた意図もあったようである。
ジャケットのイラストは漫画家大越孝太郎氏によるものである。大越氏によるイラストは3rd『黄金の夜明け』以来で、5th『踊る一寸法師』のジャケットのフィギュア以来であった。
『怪人二十面相』当時の人間椅子について
『怪人二十面相』は、人間椅子にとってメジャーに復帰して2作目のアルバムだった。
1995年の『踊る一寸法師』以降は単発契約が続いたが、1999年の8th『二十世紀葬送曲』で古巣のメルダックに戻っていた。
作品の売り上げ自体は厳しい状況ではあったが、デビュー時にメルダックにいた頃よりは、マイペースに制作をさせてもらえる状況のようだった。
1996年に加入した後藤マスヒロ氏とのコンビネーションも脂が乗っていた頃である。テクニカルなプレイに加え、よりどっしりと重みのあるドラムになり、人間椅子らしいサウンドが生まれていた。
また編曲面では後藤氏のアレンジ力がかなり光っていた時代だったようにも思う。
作曲面においては、鈴木氏が人間椅子のおどろおどろしさやハードな部分など、楽曲の中核を担っていた印象である。現在の人間椅子とは異なり、鈴木氏がインタビューでも口火を切る役割だった。
一方の和嶋氏はヘヴィな要素を担いつつも、逆にロックンロールテイストの軽いタッチの楽曲など、鈴木氏の作らない部分を補っている、という印象だった。
なおこの当時の和嶋氏は結婚生活を送り、奥さんの稼ぎで生活しながら、自作エフェクターに凝っていたと振り返っている。
あまり作品の制作に魂が入っていない感じもする、という自己評価をしており、それがあまり『怪人二十面相』について語らない理由の1つになっているのかもしれない。
※【人間椅子】和嶋慎治の結婚時代に作られた『二十世紀葬送曲』『怪人二十面相』に漂う大人の色気とその魅力
全曲ミニレビュー
ここでは収録されている各楽曲について、優れている点や魅力などについてレビューを行っている。
全体的に演奏レベルの高さやアレンジの妙が光る楽曲が多いのが『怪人二十面相』の特徴ではないかと思っている。
怪人二十面相
アルバムタイトル曲が1曲目に配置されるのは、1992年の3rd『黄金の夜明け』以来のこと。かなり気合いの入った楽曲である。
メンバーが『怪人二十面相』の登場人物に扮してストーリー仕立ての凝ったMVが制作されたことからも窺える。
半音ずつ下がっていく不気味なイントロ、何重にもダビングされたギターサウンドから、一気に開放的なメインリフへの流れが素晴らしい。
変幻自在の怪人二十面相のごとく、不気味なBメロから哀愁漂うサビ、さらにはへヴィに展開する中間部とかなり作り込まれた楽曲になっている。
ベスト盤には漏れることの多い楽曲だが、現在もライブでの演奏頻度がそれなりに高いことからも、自信作だったことは窺える。
そして当時の鈴木氏の作曲の絶好調ぶりが分かる曲でもあり、人間椅子の編曲能力の高さが顕著な曲である。もっと注目されても良いのではないか、と言う出色の出来である。
みなしごのシャッフル
和嶋氏作曲による2曲目の「みなしごのシャッフル」は、あまり後にも先にもないタイプの、洗練されたアレンジと哀愁漂う雰囲気の楽曲である。
シャッフル調のハードロックであり、どことなくフィンガー5の「個人授業」を思わせるビート感である。ライブでは時々披露されることからも、自信作ではあるようである。
よく聴いてみると凝った展開になっており、Aメロ・BメロまではF#mのキーで、サビでGmに転調している。そしてコード進行により、再びF#mに戻る部分に違和感がない。
また当時この曲が和嶋氏の中でイチオシだった理由として、エフェクターを多用している点があるのだろう。イントロのフェイザー、Aメロでの揺れの速いトレモロなどが使われている。
蛭田博士の発明
タイトルにある「蛭田博士」は、江戸川乱歩の小説で少年探偵団が活躍するシリーズ(『妖怪博士』)に登場する。やはり「怪人二十面相」に絡んだテーマで緩やかに結ばれているのが分かる。
不気味な洋館にいる魔術師、という設定をそのままに、鈴木氏らしいヘヴィかつややコミカルなテイストのハードロックナンバーである。
基本的にはメインリフ1つだけで進む曲であり、そのリフを変形させながら展開させていく。そういう意味では、編曲を行う人間椅子全体の構築力が光る曲と言えるだろう。
冒頭のアルペジオから始まり、不気味なメインリフ、そしてサビ後のコード進行はイントロに似ている。中間にはオートワウを使ったり、後半ではアップテンポになったりと細かく展開する。
シンプルに思えて、細かい工夫の光るこうしたアレンジは、この時期の人間椅子の編曲の成熟を物語っている。
刑務所はいっぱい
続く和嶋氏の楽曲も、「蛭田博士の発明」の流れで、ややコミカルなもの。刑務所に入ったばかりの受刑者が語っているような歌詞が面白い。
曲に注目すると、まるでハードロックギターの教科書のような、コピーしたくなるようなリフやフレーズのオンパレードと言った印象である。
メインリフはハンマリングを利用したリフで、随所にパワーコードが用いられ、中間部では転調してパワーコードリフになっている。
ギターソロはファズが用いられ、アウトロではメインリフの変形が用いられるなど、色んな技法が散りばめられている。
確かにこうした技法がメインの曲であるため、今の和嶋氏からすると魂で曲を作っていない感じがするのかもしれない。しかしこうした技術的に優れた曲もまた聴いていて楽しいものである。
あしながぐも
割と爽快に進んだ前半から中盤の流れへの入り口が「あしながぐも」である。鈴木氏の作る”いなたい”雰囲気の楽曲で、この時代にはよく見られるテイストの曲である。
このアルバムでは初登場のダウンチューニングの楽曲であるが、おどろおどろしさと言うよりは、気だるさやどことなく憂鬱なムード作りに貢献している。
歌詞になっているのは、「あしながぐも」の視点から人生を語ると言うもの。人生を語るシリーズも鈴木氏の定番であり、虫シリーズでもあるところから、鈴木氏の個性が出まくっているのだ。
曲のリズムは、次のアルバムに登場する「死神の饗宴」の習作とでも言えるもの。ただ曲全体で見ると、「死神の饗宴」より渋く、より作り込まれている印象がある。
前半ではベースがずっと同じルートを弾いて重苦しさがあるが、後半では転調してベースがコード進行を弾いて、哀愁(とわずかな希望)を感じさせている。
亜麻色のスカーフ
前作より後藤マスヒロ氏も作曲に加わる流れが始まり、本作では「亜麻色のスカーフ」1曲のみ作っている。
歌は軽快なロックンロールという感じながら、演奏は非常にプログレッシブという後藤氏らしいテイストの楽曲である。まずは冒頭のリフが非常に複雑であり、いかにもプログレである。
一方で歌の部分はストレートな70年代ハードロックだ。サビにあたる「亜麻色のスカーフ」の部分ではギターがクリーンになってアルペジオを弾く、など細かい芸が光る。
ギターソロではジミー・ペイジ風の和嶋氏らしいソロが聴けるし、スイッチング奏法にスクラッチと、ソロでも様々な技法が教科書のように使われているのが、本作の特徴とも言える。
和嶋・鈴木両氏にはないタイプの楽曲が中盤に挟まれることで、アルバムの良い味付けになっている。
芋虫
アルバム中盤の1番の聴きどころが、この「芋虫」と言っても良いのではないか。イントロから一気に暗黒の中に引きずり込まれるような衝撃である。
江戸川乱歩の小説「芋虫」の世界観を借りたこの曲は、いわゆるヘヴィメタル的な重さではなく、70年代のハードロック・プログレッシブロックの魅力を継承するような楽曲である。
トレモロのエフェクトがかかったベースのリフから、ピンクフロイド風の泣きのスライドギターで幕を開ける。そして同じリフをギターが弾く形で歌へと入って行く。
メインリフはコードを分解したもので、コード進行に応じて運指が変化している。歌の部分ではギターとベースがハモると言う、非常に凝ったアンサンブルを作り上げている。
中間部ではベースは一定のルート音を弾きながら、ギターのみマイナーからメジャーに転調するなど、ここも秀逸なアレンジだ。Amの循環コードで単調になりがちだが、中間部で変化を見せている。
長めのギターソロは非常にブルース色の強い渾身のソロ、そしてテルミン風エフェクトからハードな終盤へと展開も目白押しである。
よくぞここまで1曲の中に詰め込んだ、という見事な構築ぶりであり、隠れた名曲だったのが、2019年の『人間椅子名作選 三十周年記念ベスト』で初めてベスト盤に収録された。
名探偵登場
大作「芋虫」の後に、箸休め的なコンパクトな楽曲「名探偵登場」が配置されている。『怪人二十面相』の世界観の中では、ようやくここで明智小五郎が登場と言ったところである。
メインリフのギターは、ワウの中止め音であり、独特なサウンドである。最近の人間椅子ではこのエフェクトそのものを用意しているが、当時はワウペダルで作り出していたのが懐かしい。
短い曲ではあるが、やはり芸は細かい。サビの部分ではやや不気味なコード進行が入ることで、ストレート過ぎない印象を与えている。
またギターソロは転調を重ねることで、ここでも短い時間で複雑さを盛り込むことに成功している。やはり人間椅子の編曲センスが際立って素晴らしいのが本作と言う印象である。
屋根裏のねぷた祭り
アルバムは終盤への流れへ向かう中、本作で最も恐怖体験な楽曲「屋根裏のねぷた祭り」が配置されている。
人間椅子が得意としてきた中盤で静かになるパターンの曲で、古くは「人間失格」や「黄金の夜明け」、さらに「踊る一寸法師」「春の海」と伝統的に続いてきたものである。
しかしこの曲はこれまでに比べても屈指の恐怖感で、絞り出すようなボーカルのAメロから「ヤーヤドー」の狂気めいた叫びが恐ろしい。
中間部のギターソロは、いわゆるバイオリン奏法と呼ばれるもの。当時の和嶋氏はエフェクターではなく、実際にギターについているボリュームを動かしながらソロを弾いていた。
後半のメインリフの変形からアップテンポな展開は非常に秀逸である。津軽三味線ギターも登場し、本作ではあまり出て来なかった東北カラーが楽しめる。
楽しい夏休み
和嶋氏によるスラッシュメタル風の珍しいタイプの楽曲である。歌詞の内容は、幼児退行のような子どもの心を大人が歌うという、倒錯したものとなっている。
歌やメロディに関しても、どこかヤケクソと言うか、不思議な印象である。Aメロも上下移動の激しいメロディラインで、Bメロはギターの和音とのアンサンブルが独特である。
スラッシュ曲なのに6分もあるのは、中間部のギターソロまでの展開があること、さらにはアウトロで歌のない展開があることによる。
終盤の展開は「時間を止めた男」(『踊る一寸法師』収録)を思わせる。こうした倒錯した楽曲を入れずにはいられない、当時の和嶋氏の心の闇を察するところである。
地獄風景
鈴木氏による”地獄シリーズ”の楽曲であり、お得意のスラッシュメタル曲である。和嶋氏も「楽しい夏休み」でスラッシュ調だったので、2曲続くと言うパターンは割と珍しい。
定番の地獄シリーズながら、これは江戸川乱歩の小説からタイトルを借りている。鈴木氏お得意の視覚的な地獄の運動会の様子を、コミカルかつ残酷に描いている。
運動会なので、冒頭は三三七拍子のリズムがとられている。全体にコミカルタッチなのに、狂気を感じさせる要因の1つが、後藤氏による怒涛のドラムがある。
前の「楽しい夏休み」と併せて、後藤氏の手数の多さを楽しむことができるので貴重である。ベスト盤に入ることの多い曲で、ライブのアンコールで披露されることの多い楽曲だった。
大団円
アルバムラストを飾るのは、和嶋氏によるダウンチューニングの大作である。ただおどろおどろしい楽曲と言うより、どこか洒落た雰囲気と不気味さが交錯する独特な曲だ。
歌詞で描かれるのは、舞台演劇の世界であり、演劇の終盤からカーテンコールを描きつつ、アルバム自体の幕を閉じると言う仕掛けになっている。
そうした時間の流れを、悲壮感のある前半、明るい雰囲気の中間部、そして幕が閉じるラストはBlack Sabbathテイストの不気味なリフで表現している。
和嶋氏自身は「あまり表現したいことが明確ではない」と語っている曲だが、メッセージよりも曲調を巧みに変化させていくところに魅力がある曲だと思っている。
この時期の人間椅子の編曲センスが光っている曲の1つだろう。
全体の評価 – 原点回帰のテーマと原点から最も離れた音楽性?
今回の記事では、2000年リリースの人間椅子9枚目のオリジナルアルバム『怪人二十面相』についてレビューを行った。最後に全体的な感想をまとめておきたい。
人間椅子としてはバンド名の由来でもある、原点の江戸川乱歩の小説からタイトルを借りた作品だった。そしてコンセプト作としたところにも、意気込みを感じるところである。
『頽廃芸術展』『二十世紀葬送曲』と、アルバム自体のコンセプトは緩やかな作品が続いていた。タイミング的には1999年で活動10周年を迎え、1つの区切りと言う感じでもあったようだ。
テーマは原点回帰ながら、楽曲の方向性はデビュー前後の作風とは最も離れていたのではないか、と思うところだ。それは良い意味で、非常に洗練された大人のロックという感じである。
そう感じさせる要因として、1つは技巧や編曲の妙が光る楽曲が多い点にある。前後の作品を見ても、各楽曲の作り込み度合いと言うか、よく出来た曲が多いと言う印象である。
技巧的な感じがするのは、『怪人二十面相』と言うコンセプト作だった点も影響しているかもしれない。物語の登場人物をなぞるように作られており、音楽性も多様なものが盛り込まれた。
結果的には、人間椅子の原点であるBlack Sabbathテイストの薄さが、洗練された雰囲気の要因と感じられるのだろう。
「あしながぐも」「大団円」と言ったダウンチューニングの曲で少しサバスらしさを感じるものの、もう少し広義のハードロックを扱った曲が多いのが本作の特徴である。
多様な音楽性の影響を消化し、洗練された雰囲気を持ちつつも、ポップでありヘヴィである、という当時の人間椅子の最先端を示した作品と言えるのではないか。
おどろおどろしいBlack Sabbathテイストの薄さが、ある意味で音楽的には人間椅子の原点から最も離れた作品と言っても良いのかもしれない。
また和嶋氏は自身の本作の楽曲について、魂を削って作っていないと、あまり肯定的な評をしないことがある。それは和嶋氏の私生活に由来するもののようだ。
確かに結果的にはセールス的に厳しい時代であったことは間違いない。売れるためには、何かしら作っている側に輝きのようなものがなければ、そこに人が集まって来ないということがあるのだろう。
人間椅子は変わっていないように見えて、作品で伝えたいものは結構変わっていると思う。初期や近年の作品は、おどろおどろしい世界観やスピリットのようなものが中核にあった。
言い換えれば、音楽的に高度なことを知らずとも、感覚的に”ハマる”体験ができるようなものであり、それゆえに初期や近年の作品は”売れる”と言う現象が起きている。
しかしインディーズ時代の『踊る一寸法師』から後藤マスヒロ氏が在籍した時代の人間椅子は、どちらかと言えば技巧的に優れたものや、音楽的に高度なものを目指していた感がある。
やはりその方がマニアックな作品となり、セールス的には一部のファンにしか受け入れられない、ということになってしまう。
和嶋氏の感覚としても、そうした技巧的に優れた作品を作っていると言う自負はありつつ、もっと多くの人に届く作品を作っていない感覚も同時にあったゆえの、自己評価なのではないかと推測する。
しかしそれとは別に、音楽的な成熟度は最も高い作品だと感じる。マニアックであろうと、とにかくあの時代にここまでクオリティの高い作品を作り上げたことはもっと評価されて良いだろう。
人間椅子の評価は随分と後になってようやくついてきた。
あまりに時代を先取りし過ぎたと言うべきか、あるいは完成度の高い作品過ぎたと言うべきか、結果的に影に隠れてしまう、と言うもったいない作品なのだと思う。
※【2000年~2001年】人間椅子日記その1(怪人二十面相~見知らぬ世界)
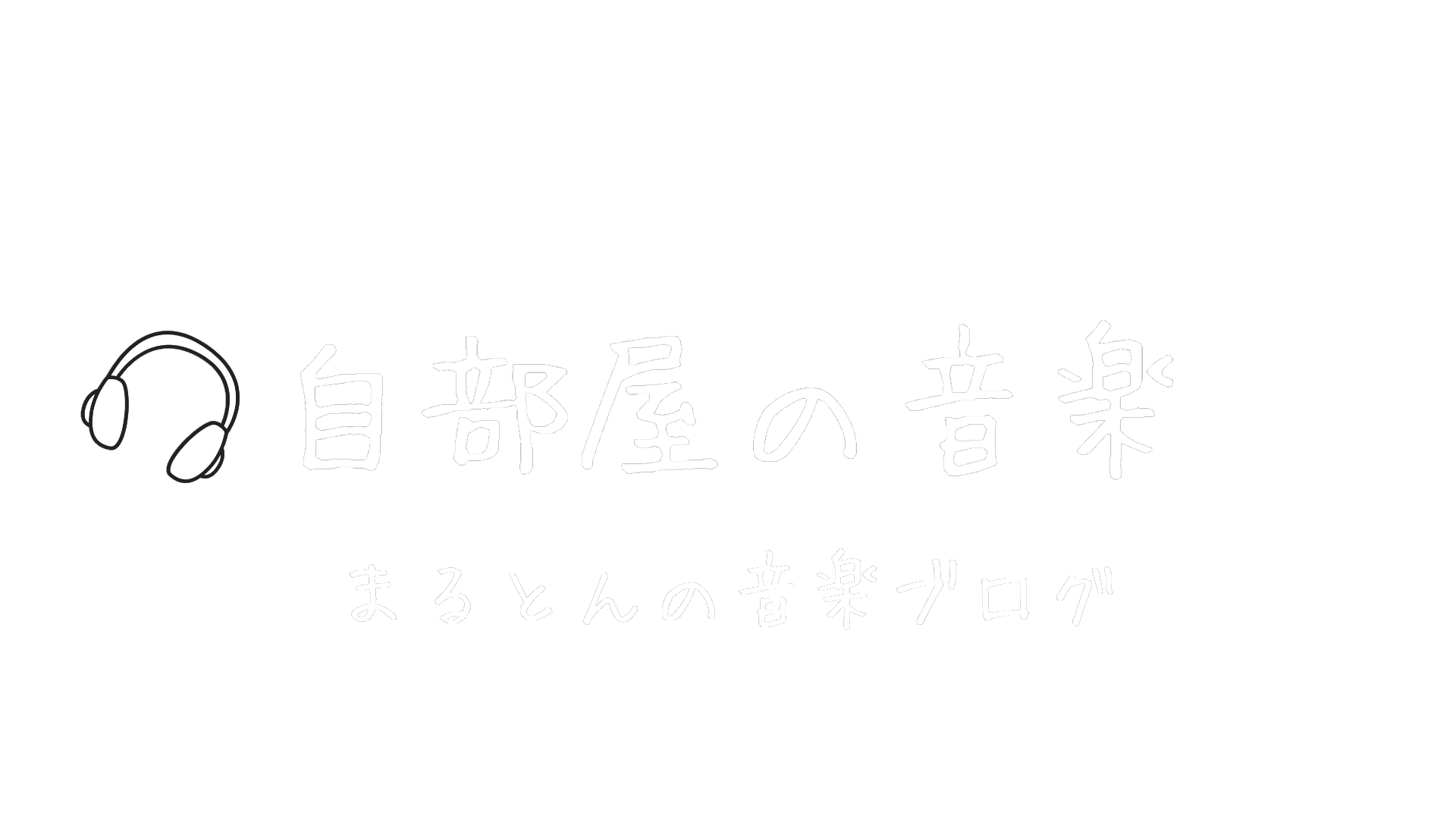




















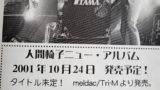


コメント