デビューから40年以上を迎えるロックバンド安全地帯は、1980年代を中心に多数のヒットシングルを有する。
最初の大ヒットとなった1983年の「ワインレッドの心」を始めとして、歌謡曲を意識した楽曲が広く知られることとなった。
安全地帯のシングル曲を細かく聴くと、定番の楽曲展開があることに気付く。メロディや歌だけでなく、楽曲の展開がもたらす効果も重要な要素なのではないか、と考える。
今回の記事では、安全地帯のシングル曲にある定番の展開を取り上げ、楽曲に与える効果とともに、それが前後の時代でどのように変化しているのか、についても考察した。
安全地帯のシングル曲の定番の展開 – 「真夜中すぎの恋」「熱視線」「プルシアンブルーの肖像」
安全地帯のシングル曲をよく聴いていると、楽曲の展開(Aメロやサビなどのこと)が非常によく似ている楽曲が存在する。
数が多い訳ではないが、非常に印象的な展開ゆえに、安全地帯のヒット曲の1つの様式である、と感じている。
それが「真夜中すぎの恋」「熱視線」「プルシアンブルーの肖像」の3曲に通じる展開である。多少の違いはあるが、およそ以下のような展開になっている。
イントロ×2(a・bに分かれる場合も)→A→B→サビ→イントロ(aあるいはbのみのことも)→A→B→サビ×2→間奏(→Bメロ)→サビ×2(→イントロ)でフェードアウト
これの一体何が特徴的なのか、ということなのだが、ポイントは大きく分けると3つある。
- 1番ではサビは繰り返さないこと
- 2番ではサビを繰り返し、その後に間奏へと展開すること
- イントロのフレーズが、1番終わりやアウトロなどで繰り返されること
展開ではないのだが、いずれもマイナー調であることも共通した要素である。各楽曲の具体的な展開、この展開の3つのポイントがもたらす効果について順に述べたい。
各楽曲の展開
「真夜中すぎの恋」「熱視線」「プルシアンブルーの肖像」の3曲は、安全地帯のシングル曲の中でも、割とロックらしいビート感を持つ楽曲である。
バラードと言うよりは激しめの3曲であるが、非常に展開においては似ていると言える。順に展開と、補足情報を載せている。
真夜中すぎの恋
- 作詞:井上陽水、作曲:玉置浩二
- 発売日:1984年4月16日
イントロ×2→A→B→サビ→イントロ→A→B→サビ×2→間奏→サビ×2→イントロの繰り返しでフェードアウト
3曲の中では最も早くリリースされた(1984年)楽曲である。ドラムから始まった後の印象的なギターフレーズ部分をイントロとしている。
この「真夜中すぎの恋」の展開こそ、安全地帯のシングル曲の展開の最も典型例であると筆者は考えている。
熱視線
- 作詞:松井五郎、作曲:玉置浩二
- 発売日:1985年1月25日
イントロa→イントロb→A→B→サビ→イントロa→A→B→サビ×2→イントロa→間奏→B→サビの繰り返しでフェードアウト
「熱視線」の展開は、「真夜中すぎの恋」から膨らましたものになっていると言える。イントロについては、アルペジオのリフをイントロa、歪んだギターが入ってきた部分をイントロbとしている。
1番はサビが1回のみ、イントロを挟んで2番へ、2番はサビの繰り返し、などは「真夜中すぎの恋」と共通している。間奏の後にBメロが登場すること、サビの繰り返しで終わることなどが異なる点だ。
プルシアンブルーの肖像
- 作詞:松井五郎、作曲:玉置浩二
- 発売日:1985年1月25日
イントロa→イントロb→→A→B→サビ→イントロbの短縮→A→B→サビ→間奏→サビ→イントロa→イントロbの繰り返しでフェードアウト
この曲については、サビを繰り返すという要素がないのが特徴である。「はなさない」という言葉の繰り返しが多いためか、サビは1回ずつだけになっている。
和音部分をイントロaとし、ピアノのフレーズが入って来る部分をイントロbとした。細かい工夫としては、1番終わりのイントロbは長さを半分にすることで、すかさず2番に入る効果を出している。
定番の展開がもたらす効果
筆者の中では「真夜中すぎの恋」「熱視線」「プルシアンブルーの肖像」の3曲が、安全地帯の定番の展開と考えるのだが、この展開には楽曲にもたらす効果がしっかりあるように思える。
いずれの曲も、非常に印象的なイントロのフレーズ、そして同様に耳馴染みの良いサビのメロディが繰り返される訳だが、ただ繰り返すのではなく、定番の展開では配置の絶妙な工夫がある。
結論から言えば、その配置によって、楽曲への中毒性を増すのではないか、と思っている。
まずは冒頭ではイントロをしっかりと繰り返して印象付けるところから始まるのだが、1番ではサビが繰り返されず、さらにはイントロの短縮版が挿入されて、すぐに2番に進むと言う展開になっている。
このように1番をコンパクトにすることで、楽曲にスピード感や緊張感を持たせる効果がある。
あるいはサビの回数を減らすことで、もっと聴きたい、と言う渇望感のようなものが残る。そして2番ではしっかりとサビを繰り返すことで、一気に充足感がやって来る。
間奏で一休みした後に、畳みかけるようにサビを繰り返すことで、もう頭からサビのメロディやイントロのフレーズなどが頭から離れられなくなり、もう一度聴きたくなるのである。
そもそも素晴らしいメロディやフレーズがあってこそではあるが、流れるように楽曲に引き込まれ、そして何度も聴きたくなるような中毒性をもたらす効果が、この定番の展開にはあるように思える。
定番の展開の派生形 – 前後の時代の楽曲たち
安全地帯の定番の様式とも言える「真夜中すぎの恋」「熱視線」「プルシアンブルーの肖像」の3曲だが、その前後の楽曲を見てみると、変化が分かって面白い。
ここでは前後の楽曲について、定番の展開との類似点や、変化の過程が読み取れるものを中心に取り上げてみた。
取り上げた楽曲は「ラスベガス・タイフーン」「ワインレッドの心」「悲しみにさよなら」「好きさ」「じれったい」の5曲である。
”普通”の展開だった以前の曲 – 「ラスベガス・タイフーン」「ワインレッドの心」
まずは定番の展開3曲以前の楽曲がどうだったのか、ということである。「萠黄色のスナップ」など、アマチュア時代の曲は音楽性がかなり異なったので、その後に繋がる楽曲で比較してみたい。
そこで「ラスベガス・タイフーン」「ワインレッドの心」と言う2曲の展開を見てみよう。各曲の展開を示すが、2曲ともほとんど同じ展開になっている。
「ラスベガス・タイフーン」
- 作詞:松尾由紀夫、作曲:玉置浩二
- 発売日:1983年4月1日
イントロ→A→B→サビ→イントロ→A→B→サビ→間奏→サビ×2→イントロでフェードアウト
イントロからAメロ、Bメロ、サビを2回繰り返し、間奏を経てサビの繰り返し、という非常にオーソドックスな展開である。
厳密には間奏後のサビ×2について、1回目の終わりには「俺は砂漠より~」の部分がない。
「ワインレッドの心」
- 作詞:井上陽水、作曲:玉置浩二
- 発売日:1983年11月25日
イントロ→A→B→サビ→イントロ→A→B→サビ→間奏→サビ→イントロ(ギターソロ)でフェードアウト
「ワインレッドの心」も「ラスベガス・タイフーン」とほぼ同じで、違うのは間奏後のサビが1回だけであることと、アウトロはイントロのフレーズではなくギターソロになっている点である。
上記2曲は、定番の展開に比べると、オーソドックスな展開である。平坦であるために淡々とした印象を与えるものと言える。
それぞれ、「ラスベガス・タイフーン」はどっしりとした印象を与え、「ワインレッドの心」はその平坦さが冷ややかな雰囲気として効果的に働いている気もする。
深読みであるが、これら2曲はスリリングな安全地帯を演出する以前の、素朴さが残っている楽曲だったのかもしれない。
※安全地帯の音楽性の正体とは? – 『萠黄色のスナップ』~『ワインレッドの心』に見る変化から探る
部分的に受け継いだ曲 – 「悲しみにさよなら」
「ワインレッドの心」以降、とりわけヒットした「恋の予感」「熱視線」の後、安全地帯の頂点とも言って良い楽曲が「悲しみにさよなら」である。
スリリング・スキャンダラスな雰囲気の楽曲が多かった安全地帯だが、「悲しみにさよなら」はメジャー調で穏やかな雰囲気のバラード曲である。
かなり「熱視線」などと方向の違う曲に思えるが、展開を見ていくと、共通する部分がない訳ではない。
「悲しみにさよなら」
- 作詞:松井五郎、作曲:玉置浩二
- 発売日:1985年6月25日
イントロ→サビ→A→B→サビ→A→B→サビ×2→間奏→サビ×2→(転調)サビ×2→(さらに転調)サビでフェードアウト
「悲しみにさよなら」に関して、それまでのシングル曲と大きな違いは、印象的なイントロフレーズがなく、いきなりサビから曲が始まると言うことである。
ある意味で飛び道具のように、不意をつかれてこの素晴らしいサビのメロディが入って来るのは、イントロよりも強力である、と判断したのであろう。
そして定番の展開と似ているのは、1番ではサビの繰り返しをせずに、すぐに2番に進んでいるところである。冒頭がサビであるため、ここは1回分引き算している、とも言える。
その分、間奏明けのサビの繰り返しは4回にも及ぶ。ただ工夫されているのは、半音ずつ2回の転調が挿入されている点である。
平坦にならないように、どんどんせり上がっていくような効果で、空高く飛び上がっていくような開放感がある。
「熱視線」のような緊張感やスピード感ではなく、よりサビへの没入感をもたらすために、サビの繰り返し箇所に工夫が凝らされていると言えるだろう。
部分的に受け継ぎつつシンプルになった曲 – 「好きさ」「じれったい」
「悲しみにさよなら」以降は、「碧い瞳のエリス」「プルシアンブルーの肖像」など、いかにも安全地帯らしい曲が続いて行くが、徐々に方向性にも変化が見られるようになる。
マイナー調の楽曲ながら、変化が見られた2曲として「好きさ」「じれったい」を取り上げておきたい。
印象的なイントロフレーズから、Aメロ・Bメロ、明確なサビ、と言った歌謡曲的な展開ではないのがこの2曲である。しかし部分的には、それまでの定番の展開を受け継ぐ部分もある。
結論から言えば、よりシンプルでそぎ落とした展開の曲が増えた、ということなのだ。
「好きさ」
- 作詞:松井五郎、作曲:玉置浩二
- 発売日:1986年12月3日
サビ→A→サビ→A→A→間奏→サビの一部を歌いながらギターソロでフェードアウト
「好きさ」については、2つのメロディのパートしかなく、どちらをAメロ、サビとするのかも定かではない。ただタイトルを歌詞にした部分をサビだとすれば、サビから始まる曲である。
イントロがないのも斬新であり、さらにはどこまでが1番なのか、というのもはっきりしない。非常にロック的な展開である、と言えるのかもしれない。
面白いのは、Aメロ部分が最初は1回、サビの後には2回繰り返されるところだ。ここは定番の展開を部分的に引き継いでいるのではないか、と考えられる。
終わり方も間奏のギターソロのまま、「好きさ」だけが歌われる形で、フェードアウトで終わるところである。これはこれで、ある種の切迫感をもたらす展開である。
「じれったい」
- 作詞:松井五郎、作曲:玉置浩二
- 発売日:1987年4月21日
イントロ→A→サビ→イントロ→A→サビ×2→間奏→サビ×2→(一部変形の)サビ
「じれったい」はデジタルファンク的な楽曲であり、シンプルな構成になっている。Bメロがなく、Aメロとサビのみという構成だ。
なお、1番でサビを繰り返さないところは、定番の展開を受け継いでいるポイントにはなっている。1番が終わってイントロに戻るところで、ベースが目立つポイントがあるなど、工夫されている。
ラストはサビの歌詞を一部変えた変形バージョンのサビが1回歌われて、イントロのフレーズで終了する。なおいくつかのバージョンが存在し、間奏明けにベースのないバージョンがある。
上記2曲については、歌謡曲らしいAメロ、Bメロと展開していくやり方を脱し、ロックやファンクなどルーツミュージックに根差してシンプルになっているのが分かる。
ただ細かなところでは、定番の展開の技が活かされているようでもあった。
まとめ
今回の記事では、安全地帯の定番とも言える展開について分析し、展開における変化を追いかけてみた。
安全地帯は勝負曲であった「ワインレッドの心」がヒットし、その後はよりヒット曲路線を明確化したものと思われる。
バンドサウンドを前面に出した「真夜中すぎの恋」は、「ワインレッドの心」ほどヒットはしなかったが、この曲の展開が安全地帯のロック寄りの楽曲の定番になった点は意義深い。
この展開を活かしつつ、「熱視線」で大きなヒットに結実させることができた。そして超売れっ子バンドとなった時期にリリースされた「プルシアンブルーの肖像」で安全地帯”節”を見せることができた。
前後の時代を見ると、この様式に沿いつつ、いかに離れるか、というバランスを変えながら、楽曲がリリースされていった。
そしてこの流れが永遠に続くことはなく、「好きさ」「じれったい」の辺りから模索が始まっていたように思える。
展開から楽曲を見る、というのはなかなかマニアックな視点ではあるが、意外とその当時の雰囲気などが読み取れて面白いものである。
※【初心者向け】”はじめてのアルバム” – 第18回:安全地帯 – アルバムとしての名作とは?
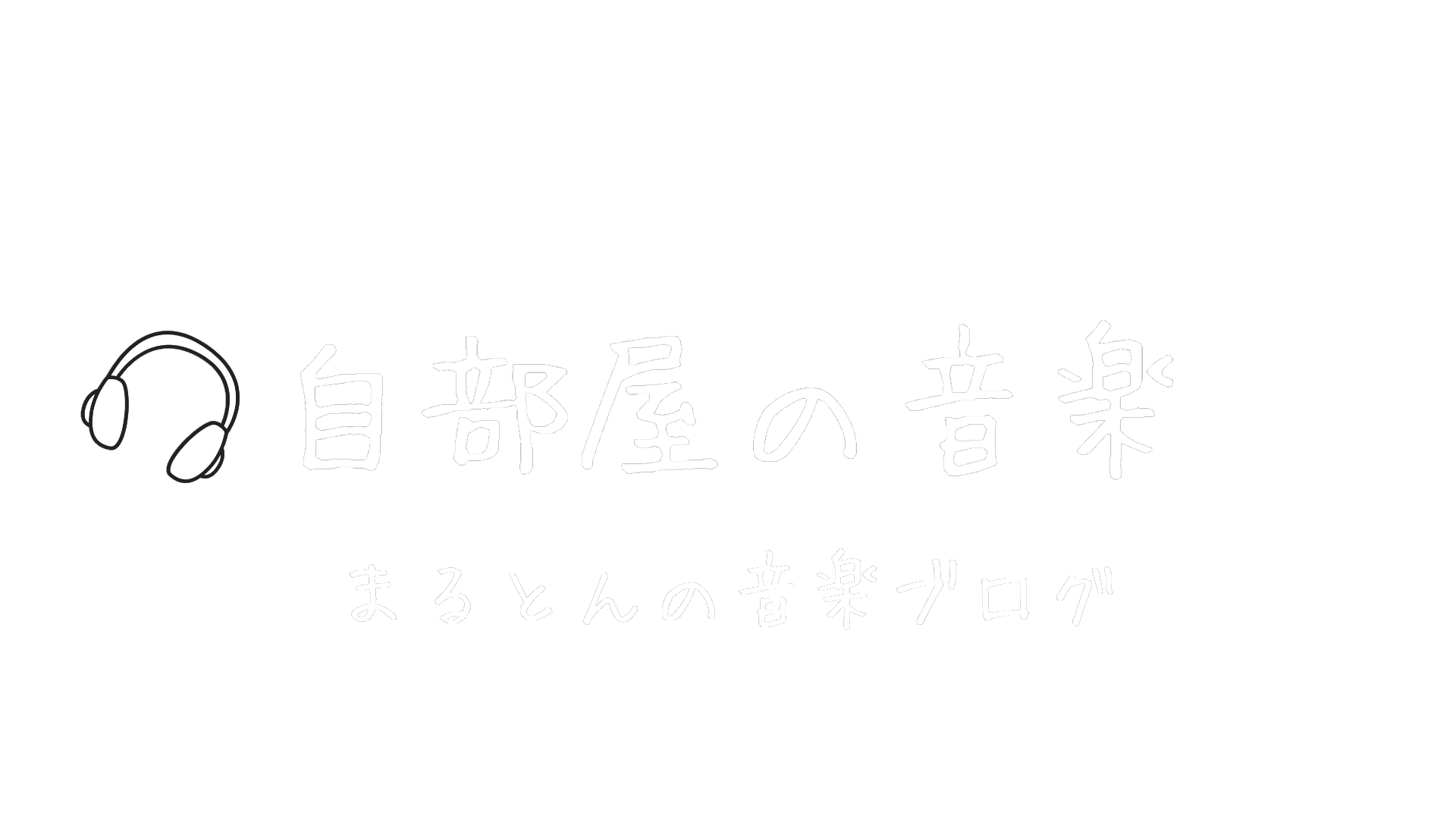



















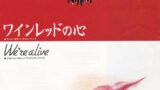



コメント