バンド生活35年の人間椅子はずっと変わらないと言われているが、表面的には結構変わったところもあるし、変化がない訳ではないと感じている。
当ブログでは人間椅子における変化を様々な角度から記事にしてきた。とりわけナカジマノブ氏が加入してからの人間椅子について、その変化時期をこちらの記事に詳しく書いたことがある。
ナカジマ氏加入からずっとリアルタイムで追いかけ続けてきた感触としては、それまでの人間椅子と大きく変わったところが多いと感じている。
今回の記事では、ナカジマノブ氏加入後の人間椅子が変化してきたこと、その激動のポイントを4つの観点から語ってみようと思う。
またそれが、歳を重ねてなおロックバンドとして続けていく上で必要な変貌だったのではないか、と言う点から考察も試みた。
ナカジマノブ氏加入後の人間椅子の激動の4つのポイント
今回取り上げるのは、人間椅子にドラマーとしてナカジマノブ氏が加入してからの変化である。ナカジマノブ氏は2004年に前任の後藤マスヒロ氏に代わって人間椅子のドラマーとなった。
ナカジマ氏が加入後もしばらく低迷を続けていた人間椅子であったが、徐々に動員が増加し、2013年のOzzfest Japan 2013への出演も話題となり、再ブレイクとも言える状況となった。
後から振り返れば、綺麗に話をまとめることもできるが、リアルタイムでその変化を追っていると、それまでの人間椅子との違いに戸惑う事さえあったのが、この20年間であった。
今回の視点としては、リアルタイムに追っていた筆者から見た、ナカジマ氏加入以前の人間椅子といかに変わったのか、ということをメインに4つのポイントを取り上げた。
4つのポイントは、緩やかに時系列の古い順に並んでいる。
ドラムのスタイル・キャラクターの変化
まずドラマーとして加入したナカジマノブ氏のドラムのプレイスタイル・キャラクターがあまりにそれまでの人間椅子と違ったのが衝撃的だった。
人間椅子はそれまで上館徳芳氏、後藤マスヒロ氏、土屋巌氏の3人のドラマーが担当していた。それぞれの個性はもちろんありつつ、ハードロックやプログレなどに根差したプレイヤーが多かった。
それゆえにドラマー交代によって劇的な変化があったとまでは言えなかった。一方でナカジマノブ氏は人間椅子がイカ天を経てデビューした同時期にGENで活動していた。
人間椅子加入直前はドミンゴスで活動していたが、いずれも人間椅子の音楽性とは大きく異なる、ロックンロールのジャンルで活動していた。
そのためそれまでのドラマーのようなどっしりとしたプレイではなく、前に転がっていくような疾走感がありつつ、爽快なプレイが持ち味だった。
やはり彼のドラムスタイルが人間椅子に馴染むまでには時間がかかった。
2004年の『三悪道中膝栗毛』こそ、おそらく後藤氏と作り始めていた作品だけに、それまでの世界観を壊さない形で、ナカジマ氏の個性がそれほど前に出ないプレイだった。
ただいつまでもかつての人間椅子に合わせるだけでなく、ナカジマ氏の個性も生かした人間椅子に変わっていくこととなる。
続く2006年の『瘋痴狂』は、逆にナカジマ氏の個性が際立つ、軽快さが前面に出た作品となり、今度は人間椅子らしさがどこにあるか、という意見も出るような作品となった。
またナカジマ氏の陽気なキャラクターも、加入当時はファンの間でもなかなか受け入れ難い雰囲気もあり、それに馴染むのにも相応の時間がかかった記憶がある。
和嶋・鈴木両氏がナカジマ氏の陽気さに慣れ、ナカジマ氏は2人の作り出す世界観に馴染んだところで、ようやく3人の一体感が生まれてきたのは、2007年の『真夏の夜の夢』の頃だったと思う。
それまでの時期は、それまでの人間椅子のサウンドやプレイを再構築する上で激動の時代だった。
和嶋氏の歌詞・作風の変化
ようやく人間椅子らしい怪奇性やダークさが戻ってきた『真夏の夜の夢』であったが、既に和嶋慎治氏の中では表現に対する考え方の変化が起き始めていた。
彼の著書『屈折くん』にも詳しく書かれているが、和嶋氏の中でバンドで表現することの軸のようなものを獲得したのがこの時期であった。
遡れば2001年の『見知らぬ世界』頃から和嶋氏の作風は模索を続けてきた過程があった。その間、鈴木氏が昔ながらの人間椅子ワールドを展開していたので、何とか人間椅子らしさを保ててはいた。
和嶋氏の中でついにたどり着いた答えによって、和嶋氏の作る楽曲は結果的に非常に明るいものになった。
それは『見知らぬ世界』の時のような、単にメロディや曲自体が明かるいと言うより、救いのない表現をしなくなったとでも言おうか。
顕著に変化があったのが、2009年の『未来浪漫派』である。中でもラストに配置された『深淵』は人間椅子らしいヘヴィさを持ちつつ、非常に前向きな歌詞が明らかにこれまでと異なる肌触りだった。
それまでの和嶋氏は、どこまで行っても暗いところがあり、それは内面から湧いてくる精神的な意味での暗さだった。時にそれは呪詛のようでもあり、それこそが人間椅子の世界観の1つでもあった。
誰かや何かを呪うのではなく、救いになるようなものを、という世界観に変わった『未来浪漫派』は実に清々しい作品であるが、当時としてはまたその変化に驚いたものである。
鈴木氏の不調とバンド内のバランスの変化
2009年の『未来浪漫派』の頃、和嶋氏は迷いの中から吹っ切れて生き生きとしていた半面、ベースの鈴木研一氏はあまり調子が良くなさそうな印象だった。
それは精神的なものと言うより、体調面だったように思う。ライブを見ていても、それまでのような縦横無尽のステージングではなくなっていた時期があった。
後に体力的な面では回復していった印象であるが、曲調やバンドにおける立ち位置も併せて変化が起きた時期であった。
まずはアルバムの中の曲のバランスとして、これまでは鈴木氏の楽曲がどちらかと言うと多めで、人間椅子らしい音楽性を担当していた感じがした。
その役割を徐々に和嶋氏が担い始め、和嶋氏の打ち出すコンセプトと楽曲がアルバムの中心になった。和嶋氏が大作を作るので、鈴木氏はそれとぶつからないコンパクトで軽めのロックが多くなった。
アルバムの中のバランスは、和嶋氏の作風の変化によるところも大きいが、2011年の『此岸礼讃』頃までは、あまり鈴木氏自身の調子が良くなかったようにも見えた。
加えて、かつてはインタビュー等で口火を切る・司会進行をするのは鈴木氏の役割であったが、和嶋氏の作風が変わり、和嶋氏の口数が圧倒的に増えたのもこの頃からだ。
以降、現在に至るまで、人間椅子の音楽性や作品について語る役割は和嶋氏が担うことが多くなっている。
音楽性が集約されてシンプルな路線に
和嶋氏の作風が前向きになり、鈴木氏とのバランスも変化が見られていたが、『此岸礼讃』辺りまではアルバムの中で音楽的な実験があり、難解で複雑である、と言う従来の人間椅子の特徴が残っていた。
人間椅子の音楽性は、単におどろおどろしい、Black Sabbathに影響を受けたドゥーミーなハードロックだけではない。
遡れば、土屋巌氏時代の『踊る一寸法師』(1995年)辺りから、ハードロックと他の音楽ジャンルをいかに融合させるかという音楽的な実験を行ってきたバンドであるとも言える。
しかしその実験的な要素が一気に薄れたのが、2013年の『萬燈籠』からである。本作リリースの前に何があったかと言えば、Ozzfest Japan 2013への出演である。
彼らの当時の立ち位置からすれば、かなりの大抜擢である。人間椅子をより多くの人に知ってもらう大チャンスだったのだ。
ライブに向けて、改めて”人間椅子らしさ”とは何かがきっと考えられ、セットリストにそれが反映されていると思われる。
選ばれたのは「相剋の家」「死神の饗宴」「深淵」「人面瘡」「針の山」というわずか5曲であるが、ここに人間椅子の重要なエッセンスは詰め込まれているように思える。
やはり重厚でおどろおどろしいハードロックを軸に、時にプログレ風味を加えたり、ハードロック・ロックンロールの豪快さ・軽快さを加えたり、と言う音楽性こそ、人間椅子が変わらなかった部分だ。
『萬燈籠』は、おそらくOzzfest Japan 2013出演が決定する以前から制作が決まっていたアルバムだとは思うが、出演によって方向性が明確になったのではないか、とも思う。
それは人間椅子が原点に返ること、おどろおどろしいハードロックに戻ることで、それ以外の要素はあえてそぎ落としたシンプルな路線がしばらく続くこととなった。
それまでは複雑で凝った展開やアレンジを足し算することも多かったが、よりシンプルにヘヴィで不気味なハードロックを、という引き算のやり方を感じるところがある。
その結果として、音楽的に玄人な楽しみ方をする一部のファン向けだった人間椅子が、より間口を広げて、多くの人に楽しめる音楽に変化したと言うことでもある。
こうした変化はOzzfest Japan 2013だけではなく、2009年リリースのベスト盤『人間椅子傑作選 二十周年記念ベスト盤』以降、ライブの選曲のやり方の変化にも表れていた。
それまではどんなに難しい、あるいはマニアックな曲も選曲に入れていたが、2009年頃からよりライブで映える・盛り上がる曲は何かと言う視点で、選曲を絞っていた節がある。
その結果、人間椅子のエッセンスが濃い楽曲がライブの中核に据えられるようになり、そうしたエッセンスをふんだんに盛り込んだ作品が、『萬燈籠』以降の作品とも言える。
その後は徐々に音楽的な広がりも多少見せてはいるが、基本的には『萬燈籠』で確立した方法論やスタイルを継承しているのが、現在の人間椅子である。
まとめ – 歳を重ねたロックバンドとしての変貌
今回はナカジマノブ氏が加入後の人間椅子は激動の時代であったことをまとめた。
こうした歴史を振り返ってみれば、再ブレイクに向かうための歩みだった、とまとめることもできる。実際に筆者はそういう方向性で記事を書いてきたことも多かった。
しかしもう少し別の見方もできるように最近思う。それは若者からベテランのロックバンドへと向かう過程で起きる、一種の葛藤であり、超える壁のようなものである。
筆者が最初に聴いた、後藤マスヒロ氏がドラマーだった時代の人間椅子は、やはり若かったのだ。精神的な暗さを抱え持っていたことも、一つは若さの表れとも言える。
また音楽的実験を試みていたのも、バンドの初期衝動から、いかに可能性を広げていけるのかという、まだまだ若いからこそできる・やりたい方向性だったのだろう。
しかし音楽的実験はいずれ終わりが見えてくるし、精神的な暗さの解決は歳を重ねればいずれ向き合う時がやってくるものだ。
そしてロックバンドという存在自体が若者と結び付いたものだと考えるので、歳を重ねればそのバンドごとに独自のあり方を模索する必要が出てくるのだろう。
人間椅子の場合は、和嶋氏の作風の変化を軸に大きく動いたが、そこにナカジマ氏が加入していたことが、より良い縁を引き寄せていった感じがある。
根底にある音楽性は変えることなく、若さゆえにあった実験的な要素や、精神的な暗さのようなものを良い形で手放していくことに成功できた。
その結果、歳を重ねたロックバンドとして非常に良い形となったことも、人間椅子が再ブレイクに至った要因の1つではないか、と思うようになった。
※【人間椅子】和嶋慎治の表現の変化から考えるバンドの若い頃の良さ・歳を重ねた良さとは?
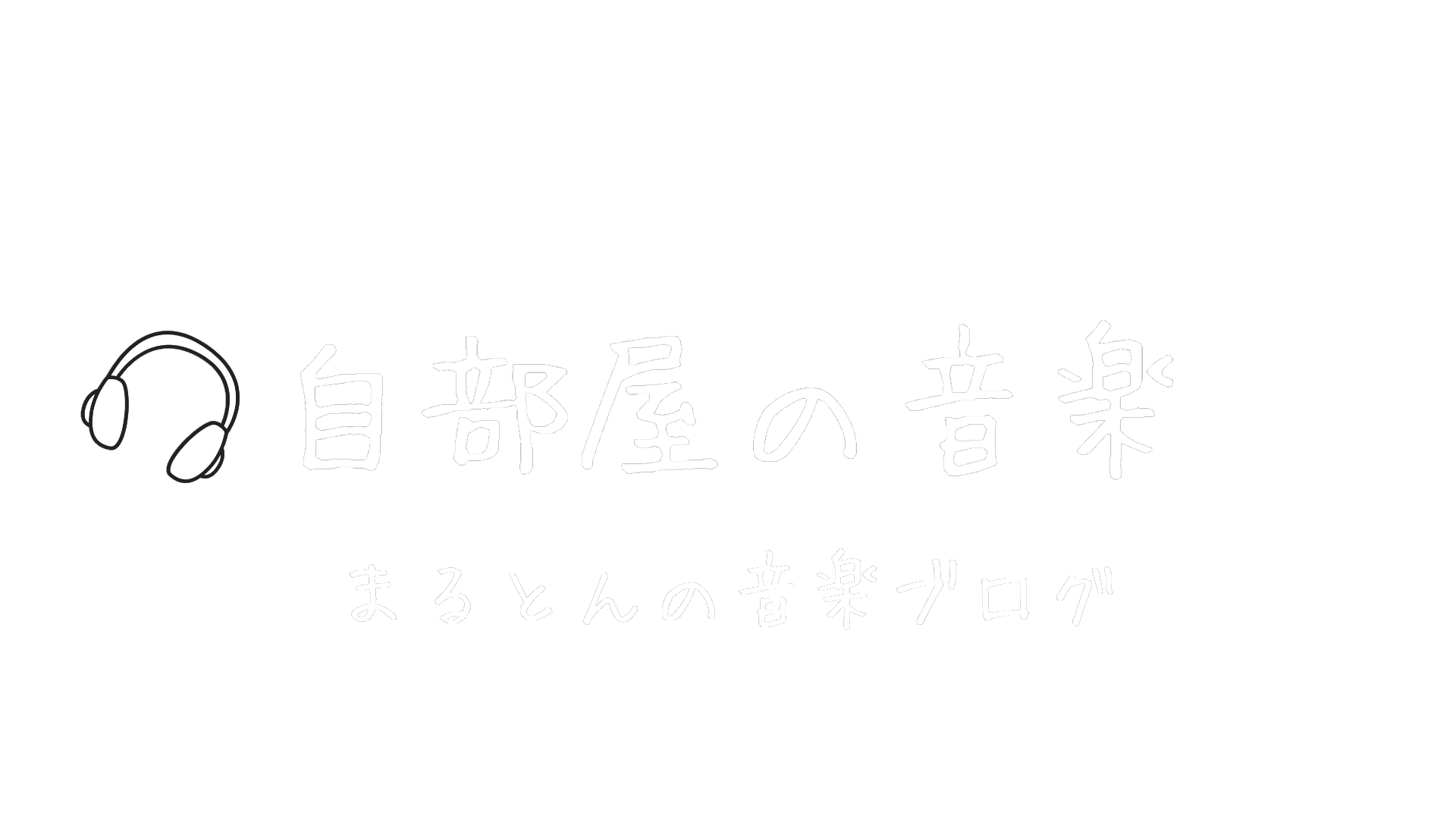























コメント