近年はボーカルの宮本浩次氏のソロ活動が増えたが、バンドとしての活動も継続しているエレファントカシマシである。
エレカシと言えば長年続けてきた日比谷野外音楽堂でのコンサートが風物詩である。このたび2025年10月の建て替え工事を前に、現在の野音での最後のステージに立つこととなった。
タイトルは『〜日比谷野音 The Final〜 俺たちの野音』と、それだけで胸がいっぱいになるのであった。雨の野音や外で聴いた経験も含めて、思い出いっぱいの野音でのコンサートである。
さてエレカシの野音は日が暮れていく中で、彼らの楽曲を聴くという特別な体験であり、野音公演で魅力が倍増する楽曲たちがある。
普段から定番の楽曲もあれば、野音だけで定番の楽曲など、いくつか思いつく楽曲がある。今回の記事は、日比谷野音でこそ聴きたい楽曲を15曲にまとめて紹介する。
エレカシ日比谷野音で聴くと魅力が倍増する15曲
エレファントカシマシ 日比谷野外大音楽堂公演の開催が決定いたしました。さらに公演当日の全国18館の映画館でのライブ・ビューイングと、オンライン生配信実施もあわせて決定いたしました。
— エレファントカシマシ (@elekashi_ofcl) August 28, 2025
〜日比谷野音 The Final〜 俺たちの野音
2025/9/28(日)#エレファントカシマシhttps://t.co/LkDPaMo5iB pic.twitter.com/9wLvYXjvaZ
エレファントカシマシは1990年に初めて日比谷野外音楽堂でのコンサートを行い、それ以来日比谷野音での公演数最多の41公演を行っている。
コロナの時期や宮本氏のソロ活動が本格化してから行っていない年もあるが、ほぼ毎年のように行われてきた行事である。
エレカシの野音の魅力についてここでは書ききれないのだが、日が暮れていく時間帯に野外で聴く良さ、そしてレアな楽曲を含めたエレカシ祭りとも言える選曲などがある。
曲数も多くなり、普段なかなか披露されないような渋い楽曲と、定番曲とが絡み合い、野音でしか味わえない体験になるのだ。
縦横無尽に変化するセトリではあるが、年数を重ねるごとに野音での定番曲も生まれ始めた。今回は野音の定番曲、野音でこそ聴きたい楽曲を15曲に絞ってみた。
いつもの定番曲も多くなっているが、野音ならではのシチュエーションや魅力について、実際に野音で聴いた体験をもとに綴っている。
曲順はリリースの古い順である。
ファイティングマン
- 収録アルバム:『THE ELEPHANT KASHIMASHI』(1988)
エレファントカシマシの記念すべきデビューアルバム1曲、そしてエレカシのライブにおいて最も重要と言っても良い代表曲の中の代表曲と言って良い楽曲である。
野音以外のライブにおいても、ライブ終盤で最大の盛り上がりとなる楽曲である。野音においてはその盛り上がり方はさらに凄まじいものがあるように思う。
2010年にリリースされた映像作品『エレファントカシマシ2009年10月24,25日 日比谷野外音楽堂』には、特別編集版「ファイティングマン」ライブ映像が収録されている。
歴代の野音公演における「ファイティングマン」のライブ映像が繋ぎ合わされた感動的な映像である。
それだけ野音には欠かせない楽曲であり、「ファイティングマン」なしに野音は締めくくれないとも言えるだろう。
星の砂
- 収録アルバム:『THE ELEPHANT KASHIMASHI』(1988)
「ファイティングマン」と同じく、1stアルバムに収録されたライブの定番曲の1つである。宮本氏が15歳の時に作られたと言うから、驚くべき才能である。
右翼思想のような歌詞と「星の砂」というおとぎ話のようなタイトル、そしてダンスビートの曲調が全く不条理なのだが、この曲はあまり深く考えずに演奏を楽しめば良いのだろう。
野音公演の場合、長丁場になることもあってか、序盤は静かに・じっくりと始まる(「序曲 夢のちまた」や「歴史」など)ことも多い。
そんな序盤に切り込み隊長のように盛り上がりを作るのが「星の砂」である。「星の砂」のところでは手首を回してきらきらの動作をやるのが定番化している。
「野音が始まったのだ」と思わせてくれる楽曲である。「星の砂」の役割を「デーデ」が担う年もあるように思う。
珍奇男
- 収録アルバム:『浮世の夢』(1989)
「珍奇男」もまたエレカシのライブでは欠かせない楽曲であり、バンドの一体感や宮本氏の鬼気迫るパフォーマンスが魅力である。
エレカシ初期の破天荒なパフォーマンスが見られる曲であり、ポニーキャニオン期などポップな作風になった時代などでも、この曲だけは割と継続して演奏されて現在に至っている。
野音でのライブの特徴には、エピックソニー期の曲が多く披露される、ことが挙げられる。その中にあっては「珍奇男」は極めて自然な流れで披露されることになる。
それでも主にライブの序盤~中盤での山場を作る役割となっている。日比谷公園に宮本氏の絶曲が響き渡るのが何よりの快感なのである。
バンドが宮本氏のその時のムードや感情に合わせて、迫力の演奏を行い、見事に完奏した時、いつも万雷の拍手となるのであった。
月の夜
- 収録アルバム:『生活』(1990)
野音のライブと言えば、エピックソニー期の曲が多いのだが、4thアルバム『生活』はとりわけ演奏されることが多いアルバムとなっている。
全7曲のアルバムであるが、全曲野音で聴いた記憶がある。その中でもとりわけ野音を思わせるのが「月の夜」である。
静かな前半から一気に盛り上がる短い中間部、というまるでプログレッシブロックを思わせる展開が印象的である。荒々しさもありつつ、非常に凛とした雰囲気の曲である。
夕暮れから夜に向かっていく時間帯、あるいは月が出始める時間帯にこの曲を野音で聴く体験は何物にも代えがたいものである。
月をテーマにした楽曲が多いエレカシであるが、野音で最も聴きたい月にまつわる曲だと思う。
星の降るような夜に
- 収録アルバム:『東京の空』(1994)
エピックソニー期の超名盤『東京の空』からも野音では演奏される曲がいくつもあるが、とりわけ頻度が高いのが「星の降るような夜に」ではないだろうか。
ライブの終盤、アンコールにおもむろに演奏が始まる、というパターンが多い。エレカシのライブではアンコールが決まっていないこともあるようだが、パッと演奏しやすい曲でもあるのだろう。
男の友情を歌った曲の多い『東京の空』であるが、この曲はとりわけ男友達と歩いている絵が浮かぶ曲で、それがエレカシのメンバー間と重なって、微笑ましくなるような曲である。
「ガストロンジャー」とか「ファイティングマン」など戦うモードの曲が多い終盤、何だかほっこりする曲で、野音では泣けてくるような時もあるのだ。
陽気な曲調で言えば、1stアルバム収録の「ゴクロウサン」も野音の定番の1つである。
悲しみの果て
- 収録アルバム:『ココロに花を』(1996)
エピックソニーとの契約が切れ、起死回生の1曲となった1996年の「悲しみの果て」である。この曲もライブの超定番であるが、野音においても演奏頻度は高い。
宮本氏自身がギターでカウントを取って始めるこの曲、野音では比較的序盤に披露されることが多い。「星の砂」とはまた違った意味で、野音のコンサートに来たことを実感させてくれる。
2分30秒しかない短い曲であるが、宮本氏の作るポップなメロディやエレカシらしいロックサウンドの全てがこの曲には詰まっている。
野音と言うマニアックな曲のオンパレードになる選曲の中だからこそ、「悲しみの果て」が披露されることで、場が締まるというか、凛とした空気感にさせてくれるのである。
今宵の月のように
- 収録アルバム:『明日に向かって走れ-月夜の歌-』(1997)
ドラマの主題歌に起用され、80万枚を超える大ヒット曲である。ライブにおいても演奏頻度の高い楽曲である。
日比谷野音でのコンサートにおいては、必ず披露される楽曲と言う訳ではない。「今年は今宵がなかった」という年もあって、それはそれでマニアックな選曲だったと言う印象の年になる。
一方でライブの後半に「やっぱりこの曲を」と言う趣旨のMCから披露されると、また特別な気持ちで聴くことができるのである。
つまり野音と言うマニアックな曲が揃うからこそ、定番曲が光って見えるということである。
また中に入れず、外で聴く時には、街行く人たちもこの曲で足を止める光景を見るのが好きだったりする。
※【エレファントカシマシ】大ヒット曲「今宵の月のように」の魅力とは? – コード進行と宮本浩次のボーカルから考える
so many people
- 収録アルバム:『good morning』(2000)
エピックソニー期を経て、一気にロック路線になった『good morning』に収録の人気曲「so many people」もまた野音に欠かせない楽曲である。
普段のライブでも終盤に披露されて大いに盛り上がるのだが、野音での盛り上がり方はその何倍も、という印象がある。
やはりマニアックな曲も含め、かなりの曲数を披露するのが野音である。宮本氏もかなりハードに歌いまくった後半にやってくるこの曲、もうヤケクソのような時もあったりする。
しかしそのヤケクソぶりが、この曲のスピード感とマッチして、言いようのない盛り上がりを作り出すことがある。やはりそれは野音ならではの良さである、と言って良いだろう。
なおこの曲に加え、同時期の「コール アンド レスポンス」が聴けると、野音らしさがさらに増す。
武蔵野
- 収録アルバム:『good morning』(2000)
激しいロック路線のアルバム『good morning』の中では異色の美しいメロディが印象的な楽曲、そして隠れた名曲が「武蔵野」である。
東京のある地域を武蔵野と言っていた江戸、また国木田独歩が『武蔵野』という随筆を書いた頃の雰囲気を、現代の視点から歌ったものであり、宮本氏の文学的センスも光る曲である。
普段のライブではあまり頻繁に披露されないが、野音での演奏頻度は結構高い。そして日比谷野音の舞台で歌うことに、宮本氏は特別な思いがあるのか、涙することもしばしばである。
日比谷野音の空気感、秋の虫の音や人の行き交う気配などに包まれて聴く「武蔵野」は、東京生まれでなくとも、不思議な郷愁の念を呼び起こす。
この感覚はあの野音にいて「武蔵野」を聴くことでしか得られない不思議な感覚なのである。
友達がいるのさ
- 収録アルバム:『風』(2004)
2004年のアルバム『風』に収録、模索を続けていた印象のある時代に生まれた隠れた名曲である。静かに淡々としたリズムで進んでいくが、後半にかけての盛り上がりが快感である。
筆者が野音公演を初めて観たのが2008年のことであったが、その当時はそれほど定番という感じではなかったが、そのパフォーマンスの凄さは印象に残っていた。
2008年の野音での「友達がいるのさ」はシングル『新しい季節へキミと』の初回限定盤に収録され、映像に残るようになると、そのパフォーマンスの魅力は徐々に知られわたることとなる。
後半部分の盛り上がりでは、宮本氏のアドリブの歌詞が織り交ぜられ、その時のムードが反映されるのが、いかにも野音という感じで素晴らしい。
”友達”とはエレカシのメンバーであり、会場に来ている全員である。そして「また出かけよう」という歌詞は、生きてまた来年も野音で会おう、という意思確認のようなものに聞こえてくる。
決してそれは和気あいあいという感じではなく、それぞれが各自の生き方で歩んでいく、という感覚で、エレカシと野音に来ている皆の歌、という感じである。
地元のダンナ
- 収録アルバム:『町を見下ろす丘』(2006)
東芝EMI在籍最後のアルバムにして、渋い名盤『町を見下ろす丘』は、野音で披露される楽曲が実はかなり多い。中でも序盤に披露されることが多いのが「地元のダンナ」である。
2004年の『扉』辺りから、中年という等身大の自分で鳴らすロックを意識していた路線の1つの到達点という感じがする。リフはハードであり、絶叫も交えつつ、どっしりしたロックだ。
野音では1曲目や序盤の早い曲順で披露されることが多い。低いところから一気に絶叫するように音階の上がる曲で、宮本氏にとっては序盤の声出しにも都合が良いようである。
楽曲の時期はずいぶんと異なるが、「おはよう こんにちは」なども声出しソングとして野音では定番の1つである。
「星の砂」や「悲しみの果て」が切り込み隊長とすれば、そのさらに先陣を切り、エレカシのライブに来たのだ、とまずは実感させてくれる楽曲という印象である。
シグナル
- 収録アルバム:『町を見下ろす丘』(2006)
アルバム『町を見下ろす丘』のリードトラックであり、渋いロック路線だった当時の中では、ポニーキャニオン期を思わせる美しいメロディが印象的だった。
おもむろにつま弾かれるアルペジオ、さりげない宮本氏の歌唱から、徐々にサビへと盛り上がっていく展開が素晴らしい。サビでは神々しさすら感じさせるような楽曲である。
「月の夜」や「月夜の散歩」など月を思わせるこの曲は、ライブの中盤に日が暮れてきた頃に聴くのが最高である。
この曲とともに同アルバム収録「なぜだか、俺は祷ってゐた。」なども野音で聴くとたまらないのであり、『町を見下ろす丘』の良さを再確認できるのだった。
俺たちの明日
- 収録アルバム:『STARTING OVER』(2008)
エレファントカシマシが東芝EMIからユニバーサルミュージックへと移籍になり、どうなるのかと思っていた時に放たれた起死回生の1曲である。
「俺たちの明日」にまつわる話だけでもたくさんあるのだが、野音と言う意味では、2007年の野音で2回披露されている。当時はまだリリース前で、楽曲自体も完成前夜と言う感じだった。
エレカシはその後も野音でリリース前の曲を披露することが何度かあり、「俺たちの明日」も野音に揃ったファンとともに歩んできた、という印象もある。
世間的に知られる「俺たちの明日」と、野音と言う会場でバンドメンバーやファンと共有する「俺たちの明日」とは、やはり異なるものなのだ。
そして「友達がいるのさ」と感覚的には近く、また来年も野音で会おう、と言う意味合いもあり、「今年の野音もそろそろ終わりだな」と少し寂しく感じられるのもこの曲が披露される頃だ。
同時期にリリースされた「笑顔の未来へ」とともに披露されることが多く、2008年前後のエレカシを思い出すとともに、胸が熱くなるのだった。
ズレてる方がいい
- 収録アルバム:『RAINBOW』(2015)
野音とともにあった曲の1つが、この「ズレてる方がいい」であろう。一般的には映画『のぼうの城』の主題歌として知られるが、エレカシファンには違った見え方がしている曲のはずだ。
それは2012年の日比谷野音公演を前にして、宮本氏が急性感音難聴と診断され、ライブ活動の休止となったことから始まる。
大阪城野外音楽堂でのコンサートは中止となったが、日比谷野音ではどうしても宮本氏はファンに対して「直接想いを届けさせて欲しい」とアコースティックギターで数曲披露することとなった。
蓋を開けてみるとアコースティックで11曲、最後の「ズレてる方がいい」だけバンド演奏が行われた。大きな音が不安そうな宮本氏の様子を最後に、エレカシのライブは休止期間に入った。
そして2013年に『復活の野音』と称したコンサートでは、終盤に堂々たる演奏で「ズレてる方がいい」が披露され、見事に復活を宣言したのである。
「ズレてる方がいい」はファンにとっては、あの2012年~2013年の野音を思い出す曲であり、エレカシの復活を願う応援歌のようでもあったのだ。
RAINBOW
- 収録アルバム:『RAINBOW』(2015)
2015年のアルバム『RAINBOW』のタイトル曲となった「RAINBOW」もまた、日比谷野音とは切っても切り離せない曲である。
なぜならば「RAINBOW」が初披露されたのが、アルバムリリース前の2015年9月の日比谷野音公演だったからである。
これまでも野音で初披露と言う曲はあったが、この曲の初演は衝撃的であった。ライブ活動休止前後、アルバム『MASTERPIECE』などの曲も含めて、大人のロック路線に進むのかと思っていた。
そこで意表を突かれたのが「RAINBOW」である。まくし立てるような歌い方と、疾走感あるハードなロックサウンドは、非常に若々しい感じだったのだった。
50歳を目前にしてまだやるのだ、というエレカシの叫びのようである。最後の「嘘じゃないさ」の絶曲が日比谷公園に響き渡るのがとても快感だった。
この曲のMVに野音公演の映像が使われているのは納得であり、普段のライブでも盛り上がる曲であるが、ファンにとっては野音が原点であり、特別な思いがある。
まとめ
今回はエレファントカシマシの日比谷野音公演での定番曲、野音で聴くと魅力が増す楽曲について紹介してきた。
ここで紹介した曲の多くは、普段のライブにおいても定番となる曲であるが、野音での特別な意味合いやあの場所で聴く感慨深さのある曲ばかりを選んだ。
挙げ始めれば野音の定番曲はもっとある(「風に吹かれて」「生命賛歌」など)し、ほとんど野音でしか聴けない超レア曲も魅力的である。
野音公演を万全に楽しむためには、エレカシの全アルバムはもちろん、シングル曲にわたるまで隈なく聴いておくことだろう。
今回の記事は野音公演に向けた入門編であり、あるいは野音公演をより楽しみに待つための記事となればと思った次第である。
※【エレファントカシマシ】”野音の外聴き”が世界で1番音楽を楽しめる空間で困る – 会場内にない魅力とは
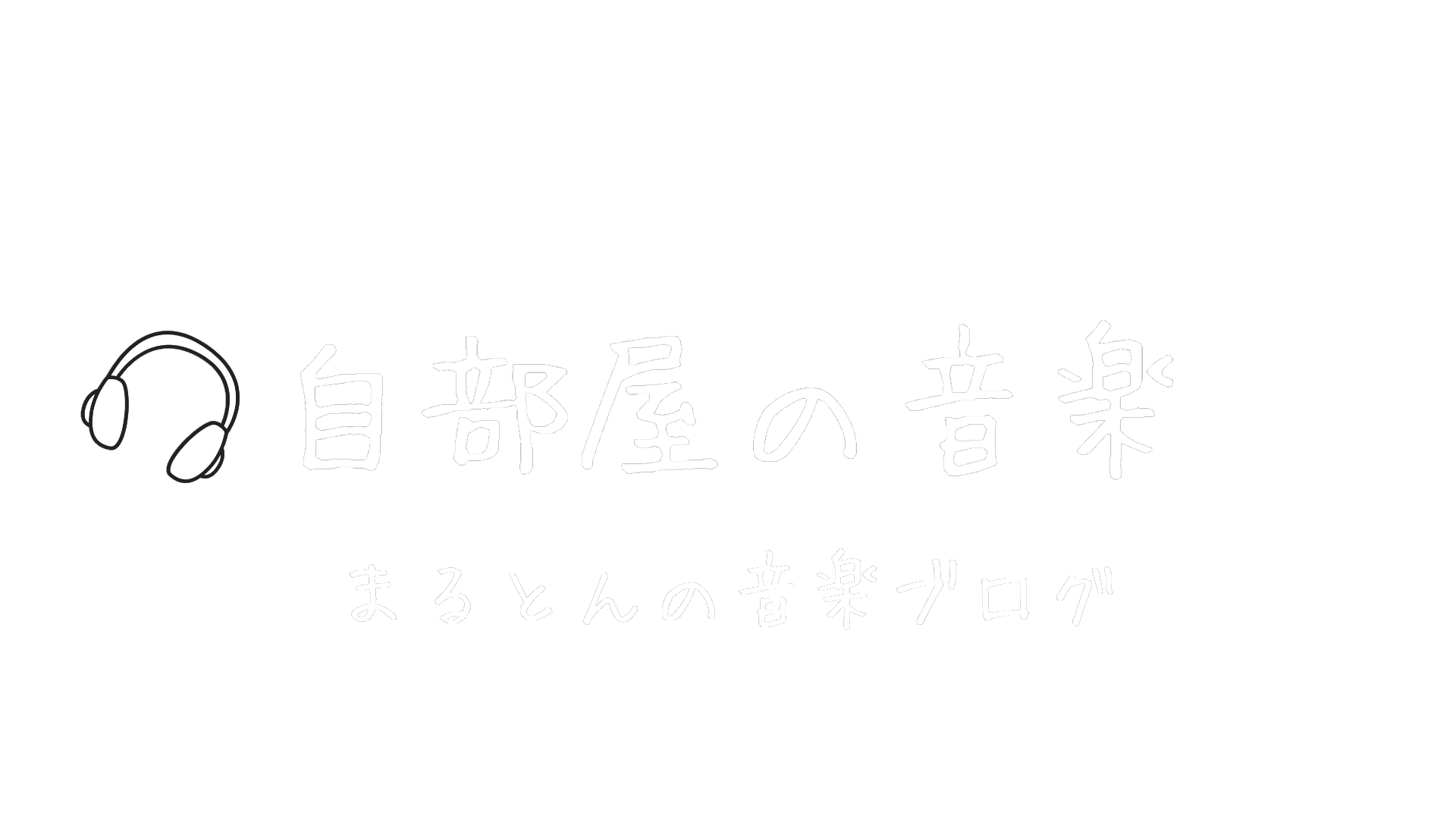























コメント