1981年にデビューしたシンガーソングライターの角松敏生は、2021年に活動40周年を迎え、なおも活動を続けている。
ここ最近は彼の初期のシティポップ、AOR感覚の楽曲が、海外で起きている日本のシティポップブームの流れで再評価の機運が高まっている。
その一方で当人の活動は、彼がかつてより関心のあった音楽と演劇の融合である総合エンターテインメント表現「MILAD」が中心となっている。
そして彼の近年の作品を振り返ると、企画作品ではないオリジナル作品で、いわゆる王道のポップス・AOR路線のアルバムは、何と2009年の『NO TURNS』以降リリースされていない。
角松氏の音楽的関心が移った、と一言で説明もできるのだが、彼自身がシティポップの枠で括られることを嫌っていることからも、どこか王道ポップス的な作品制作を避けているようにも思えてしまう。
角松氏はもう王道ポップスやAORの作品を作らないのだろうか?その答えは彼の歴史をひも解くことで、少しだけ見えてくるように筆者には思われる。
彼の活動の歴史の中で起きた出来事を取り上げつつ、角松氏の心理を推測しながら、考察したのがこの記事である。
活動の歴史から見る角松敏生の王道ポップス・AOR楽曲との向き合い方
今回の記事では、角松敏生がどのように王道ポップス・AORと向き合ってきたのか、その振り返りから始めたい。
ちなみに筆者が王道ポップス・AORと言っているのは、いわゆる彼が活動初期からおよそ2000年代くらいまで作っていた3~5分程度のポップス形式の楽曲のことである。
そして夏・海のイメージから、街・夜のイメージが加わり、都会的な洗練されたサウンドと世界観の楽曲がとりわけ初期の楽曲だった。
そして打ち込みサウンドを取り入れた時代を経て、80年代後半~90年代前半には角松敏生流のポップスが確立されたと言っても良いだろう。
しかし93年に活動”凍結”し、その後に98年に”解凍”してからは、ポップス路線を取りつつも、表現方法の模索が続いていたように思える。
こうした一連の流れにどんな背景があったのか、ファンにはもちろん分からない部分も多い。しかしインタビューや作風の変化からは、いくらか読み取れる部分もある。
角松氏の歴史を振り返りつつ、彼の王道ポップス・AORとの向き合い方について考察する。
音楽への希望・絶望と一体になっていた女性問題
1981年、日本大学在学中にシングル『YOKOHAMA Twilight Time』、アルバム『SEA BREEZE』で角松敏生氏はデビューした。
80年代前半の角松氏の作品群は、海外のAORなどに大きく影響を受けたもので、夏・海をイメージさせる爽やかなサウンド、そして都会・夜を舞台にしたテーマなどが特徴であった。
1983年『ON THE CITY SHORE』、1984年『AFTER 5 CLASH』の2作はまさにそうした世界観を体現したような作品である。
角松氏としてはまだ自身の作風が確立される前の未成熟な部分も感じているだろうが、この時期の楽曲群はいまだに人気が高い。
都会的で洗練された音楽志向、またドライブでのBGMなど、角松氏の作品が時代にも大いにマッチした部分もあるだろう。
しかしそれ以外にも人気の秘密があるように思う。角松氏の初期の楽曲は、本人曰く「女性に対しての憧れや、興味や思想や欲望」が音楽の原動力になっていたのだと言う。
女性への性的な興味・欲望、それを超えて自分自身が女性から受ける様々な影響、という明確なテーマが、角松氏の作品に煌めきを与えていたようである。
もっと言ってしまえば、角松氏の中で音楽・表現することが、女性との関係ということと不可分になっていた、とも言えるだろう。
その証拠に、彼の作品は女性への純粋な憧れや興味から作られた80年代前半の作品から、女性関係が複雑になっていった80年代後半以降では、カラーが随分と変化しているのだ。
その辺りの事情は、筆者の以下のブログ記事にも詳しく書いたが、80年代後半に2人の女性との関係、結婚・離婚を短期間に経験し、手痛い別れをしていたのだと言う。
1991年リリースの『ALL IS VANITY』の中には、”赤裸々に”と言っても良いほど、角松氏の私生活の苦悩が吐露された楽曲も収録されている。
苦悩は彼の歌詞をより哲学的なものにし、サウンドも陰のある音になったが、奇しくも角松氏の音楽的成熟が見られた時期ゆえに、1つの角松サウンドとして確立しつつあったように思う。
そして1993年の『あるがままに』では、離れて行った1人の女性に向けたラブレターのような作品であり、角松氏は彼女への一縷の望みを音楽の中に全力で込めた。
その覚悟はブックレットに”If my music cannot change your mind、Music does no longer make sense to me”という手書きのメッセージを残すまでであった。
「君の心を変えられないならば、音楽は僕には何の意味もない」と書かれているこれこそ、角松氏の中で女性関係と音楽が不可分であった、何よりの証拠と言えるだろう。
しかし『あるがままに』で込めた思いは女性に届くことがなく、角松氏は疲弊感の中で活動”凍結”を決めたのであった。(凍結の理由は私生活のみではなく、音楽的な部分もあったらしい)
ただ彼が最後の希望を込め、全力で作り上げた『あるがままに』は角松氏の最高傑作に挙げる人もいるほどで、音楽性の高さと表現の力がマッチした素晴らしいアルバムになっていた。
活動凍結までの角松氏の作品は、都会的で洗練されたAORに影響を受けた音楽と、女性への憧れ・興味などが不可分なものとして存在していた。
80年代前半まではそれがポジティブに作用したことで煌びやかな楽曲が生まれたが、80年代後半以降は最後の煌めきを残しつつも絶望感とともに終結してしまったのである。
あまりに生々しい表現は非常に危うさを伴うものであり、だからこそ魅力的でもあり、プロの音楽家としては諸刃の剣であったのは事実である。
しかしその危うさゆえに、魅力的な作品群が生まれたのもまた事実であり、そうした音楽性に多くのファンが魅了されたのだった。
角松氏の王道ポップス・AORと言える楽曲群は、こうした背景の下で生まれたことは彼の歴史を知る上で重要なことである。
凍結前の自分との決別とさらなる悲劇
角松氏は1998年に活動を”解凍”するまで、約5年間の間も音楽活動を活発に行っていた。当初は音楽活動からも退く構えも見せていたが、所属事務所の説得により、音楽活動は継続した。
結果的にはそれまで以上に忙しく、長万部太郎と言う変名で作ったAGHARTAの楽曲「ILE AIYE〜WAになっておどろう〜」は、角松氏の楽曲の中で日本国民が最も知る曲の1つとなった。
1998年に角松敏生として、活動を”解凍”を宣言し、凍結した時と同じ日本武道館公演を行った。そこで「君をこえる日」の中で、「I’ll be over you」を「I’ll be over me」と替えて歌った。
角松氏は凍結前のような女性と音楽が一体となった表現とは決別し、アルバム『TIME TUNNEL』で新たなスタートを切ることになった。
しかし女性について歌わないことは、彼のかつてのような煌びやかなAOR的楽曲とも決別をすることを意味し、音楽的なアプローチについても模索の時期に入ったように思える。
しかも90年代後半から、徐々に音楽業界の斜陽が始まった。CDの大ヒットがあった時代から、あまり音楽が聴かれない時代へと入りつつあった。
そして角松氏がずっと行ってきた、自分の身を削って表現を行う、ようなミュージシャンは減り、プログラミング1つで曲が作れるようになってしまったことにも角松氏は批判的だった。
ますます角松氏の中で、自分にとっての表現とは何か、という問いに頭を悩ませる事態になってしまったのかもしれない。
2002年リリースの『INCARNATIO』は、これまでと全く異なる民族楽器を取り入れたアプローチで、角松氏の表現の模索の1つの終着点となった。
非常に音楽的にはクオリティの高いアルバムとなったが、一方でファンは凍結前の角松氏との違いに戸惑いを覚えた人も多かったようである。
ファンにしてみれば、角松氏の音楽は凍結前から連続しているわけだが、角松氏の中では完全に断絶していると言って良いのだから、戸惑いが生じるのももっともである。
角松氏が女性との関係の中で作られた楽曲=角松流王道ポップス・AORだったがゆえに、それとの決別をした解凍後の楽曲は違うものにならざるを得ないのである。
つまり、角松氏は意図して王道ポップス・AOR的な音楽を避けざるを得ない状況に、自らを置いたということである。
しかし角松氏の中でも、綺麗に整理されたと言う訳でもないようだ。2003年にはかつての夏・海と言った角松ワールドをあえて再現した企画作品『Summer 4 Rhythm』をリリース。
後に2010年には都会・夜といったテーマの『Citylights Dandy』をリリースし、根強い過去作品の人気とともに、自身もかつて表現しきれなかったやり残しを表現したい思いもあったのかもしれない。
だがやはり角松氏の表現の根幹に、かつてのような生々しくも煌めく何かが宿っている訳ではないため、過去作品とは全く別物になっている、と言うのが正直な感想だった。
角松氏が過去の作品、サウンドとさらに離れることになってしまったのは、相次ぐバンドメンバーの死、と言う悲しい出来事もあった。
2006年にベースの青木智仁氏、そして2007年には闘病中だった浅野祥之氏が死去した。角松サウンドの要であり、プライベートでも親交の深かった両者の死のダメージは計り知れない。
角松氏の中で、盤石のバンドメンバーがいてこそ、彼なりの表現を模索していた最中だったが、悲嘆にくれる中で、新たなサウンドを構築しなければいけない状況に追い込まれた。
そしてますます過去の角松サウンドに回帰することが困難になり、とにかく前へと進む以外に道はなくなったのだった。
2000年代後半は、新たなメンバーと『Prayer』『NO TURNS』と言う作品を残しつつも、それ以降は王道ポップス・AORの作品はない。
プログレのオマージュである『THE MOMENT』(2014年)や架空の演劇サウンドトラック『東京少年少女』(2019年)が作られ、その後に演劇との融合の方向性がさらに推し進められた。
それが「MILAD」と角松氏が呼ぶジャンルであり、『Inherit The Life』(2022年)『Inherit The Life II』(2023年)の2作が彼の最新作である。
とりわけ2000年代後半以降、角松氏が王道ポップス・AOR的な作品を作らなくなったことについて、筆者は何があったのか詳しくは知らない。しかし音楽的に違う方向に舵を切ったのは事実だ。
角松敏生はなぜ王道ポップス・AORを歌わなくなったのか?
ここまで角松敏生氏の活動の歴史を振り返りつつ、彼の王道ポップス・AOR的な楽曲との向き合い方について書いた。
簡単にまとめれば、女性問題と不可分になってしまっていた若き日の音楽性は、女性問題の完全な崩壊(+彼の音楽生活での疲弊)により、ともに崩壊してしまったのだった。
それゆえ解凍後の音楽性は、当然凍結前とは異なるものになったのだが、女性への憧れと言う強烈なテーマを超えるものがなかなか見つからないうち、バンドメンバーの相次ぐ死を経験する。
過去の自分と現在とは十分整理されたとは言い難い中で、今の自分は前へと歩みを進める、と言うスタンスで、より斬新な音楽を求める方向に舵を切ったのではないか、と筆者は考えた。
これで一旦は考察できたのではあるが、まだ釈然としない部分もある。それは角松氏自身の中でも、どうやら過去の自分と良い形での折り合いがついていない、と思われる点である。
つまり「角松敏生とはどんなミュージシャンなのか」という、自身のアイデンティティに関する問題である。
そこで最後に、アイデンティティとトラウマという心理学の用語を用いながら、なぜ角松氏は王道ポップス・AORを作らなくなったのか、その考察を深めて終わりたいと思う。
若き日のアイデンティティ問題とトラウマ問題
角松敏生というミュージシャンについて考える時、筆者はいつも”アイデンティティ”と言う心理学用語が頭に浮かぶ。
アイデンティティとは自分とは何者であるか、という自分に対する感覚、そして自己の一貫性のようなものである。
この場合、「角松敏生と言うミュージシャンはいったい何者なのか」ということである。アイデンティティ問題が、角松氏の音楽にはいつもついて回るように感じている。
彼のデビューから凍結までの間、彼にとって音楽はシンプルに自己の表現であり、その表現方法として音楽があったように思う。
また自身の音楽表現には、常に女性と言う存在がセットになっていたのだった。そして彼の好きな音楽は、洗練された都会的感覚の音楽が中心にあり、それをシンプルに表現していた。
この時期の角松氏を”凍結前の角松敏生”と呼ぶとすれば、凍結前の角松氏は音楽のプロと言うよりは、音楽の表現者だった、と言っても良いだろう。
80年代後半、女性関係の問題が複雑化し、自身の音楽を女性に捧げるかのような(アルバム『あるがままに』)ところまで追い詰められ、角松氏は相当な絶望感を味わったのではないかと想像する。
それは角松敏生と言うミュージシャン、そして個人を揺るがすような出来事であり、だからこそ音楽活動を無期限で休止すると言う”凍結”宣言を当初したのである。
角松氏にとって、音楽を作ることが誰かのためになっていた、と感じていたのも、凍結前のことだったのだろう。しかし愛する女性に届かなかった絶望感は、音楽への無力感と結び付いてしまった。
この体験はトラウマ的な体験として角松氏の中に刻み込まれてしまったのではないかと考える。トラウマとは通常のストレスとは異なる、心理的に極めて負荷のかかる体験のことである。
そしていったん”凍結前の角松敏生”を封印したのだが、ミュージシャンとしての角松敏生は、音楽業界から非常に求められる存在となっていた。
そこで”ミュージシャン角松敏生”を切り離し、別の人格として活動させることにしたのである。”ミュージシャン角松敏生”はあくまで音楽のプロであり、自在に音楽を作って90年代を彩った。
この”ミュージシャン角松敏生”は、自身の名義でない方が輝く。なぜなら彼のアイデンティティ問題=凍結前の角松敏生との関連がない存在だからだ。
だからこそ、中山美穂らへの楽曲提供やAGHARTAの「ILE AIYE〜WAになっておどろう〜」などで、角松敏生名義よりもヒットを飛ばすことができたのではないかと考える。
そして1998年、”ミュージシャン角松敏生”での自信を胸に、再び角松敏生の名義でカムバックすることとなる。
しかし当然ながら、”凍結前の角松敏生”と”ミュージシャン角松敏生”をいかに統合するのか、という問題が、ここに来て勃発してしまったのである。
つまり角松敏生として表現するものは何か?というアイデンティティ問題を抱えつつ、90年代を駆け抜けた”ミュージシャン角松敏生”としていかに音楽を続けていくか、と言う問題である。
この問題が角松氏の解凍後の歴史を見て分かるように、思いのほか苦難の道だったと言えるのではなかろうか。
その苦難の背景には、やはり音楽を通じた表現に対して味わった絶望と言うトラウマが影響しているように、筆者には思える。「自分の音楽は無力なのではないか」という不安がそれである。
その不安をかき消すべく、角松氏は「I’ll be over me」と言ったのであり、その乗り越え方もまた音楽によるものである、としたのだった。
しかし日本の音楽業界はますます音楽自体の価値が下がり、「音楽の良さなどよく分からないファン」に曲を売らなければいけない状況になってしまった。
角松氏は「分かる奴だけついて来い」と、2000年『存在の証明』の頃に怒りをあらわにしていたように記憶している。
もちろん分かる人にだけ伝わる先鋭的な音楽を堂々と作る方向もあっただろう。
しかし彼の中には常に「自分の音楽は無力なのではないか」と言う不安があったために、怒りを振りまいたとしても、どこか虚しさが募るような状況になっていたように思う。
そこに追い打ちをかけるように、長年のバンドメンバーの相次ぐ死が重なってしまった。乗り越えたいトラウマの傷はなかなかふさがることがなかったのではないか、と想像する。
とはいえ、2009年の『NO TURNS』=振り返らずにまっすぐ進む、と言う宣言の下、”ミュージシャン角松敏生”は前に進む道を選んだ。
2008年に再婚し、女性関係の問題も起きることがなく、また2014年『THE MOMENT』辺りから、ギター鈴木英俊、ベース山内薫がほぼ固定となり、角松サウンドも固まっていった。
そして現在は演劇と音楽が一体となった総合エンタテインメントを作り上げ、長年の夢を叶えつつある。それで十分じゃないか、と思うかもしれない。
しかし残された問題は、彼の中にある若き日の”凍結前の角松敏生”との折り合いの問題である。それはいったい角松敏生として何を表現するか、と言うアイデンティティ問題でもある。
女性関係と密着した音楽が良かった、というものでもないが、多くのファンが表現者としての”凍結前の角松敏生”に魅了されてきた歴史は確かにある。
この問題はいかに解決されるのだろうか、またそもそも解決される問題なのだろうか。
「I’ll be over me」はいつ終わる?
角松氏のアイデンティティ問題において、象徴的とも思える発言が、1998年の解凍最初の日本武道館公演で「I’ll be over me」と歌った言葉である。
これは「君をこえる日」と言う楽曲に登場する「I’ll be over you」を替えたものである。ここで歌われたのは、まさに離れた女性との関係を乗り越えることを意味していた。
しかし「I’ll be over me」には、かつての女性への憧れを歌っていた”凍結前の角松敏生”を乗り越えていくのだ、という宣言が込められているように感じる。
そして彼の中には、若き日の純粋な表現者”凍結前の角松敏生”を”ミュージシャン角松敏生”が乗り越えていくのだ、という思いがあったように思える。
既に述べたように、”凍結前の角松敏生”は女性との関係と言うプライベートなものに左右される極めて危ういものであり、それゆえプロの音楽家としては未成熟なものとも言える。
それゆえ、もっと完成された音楽を作る自分、”ミュージシャン角松敏生”がそれを乗り越えていくのだ、と言う感覚である。
もちろん100%そのように思っていたかどうかは分からない。ただし角松氏の、過去の作品に対するスタンス・思いからは、そのようなニュアンスを感じる部分が多い。
たとえば、角松氏はリメイクアルバムをリリースしており、2012年に『REBIRTH 1 〜re-make best〜』、2020年に『EARPLAY 〜REBIRTH 2〜』を制作した。
角松氏としては過去の自身の力量では及ばなかった部分に花を添えたい、ということで凍結前の楽曲についてリメイクを行っている。
ここにも角松氏の過去の自分への微妙な葛藤のようなものが表れているように筆者は感じている。
過去の作品に対する至らなさ、については”ミュージシャン角松敏生”の観点から理解できる。しかしその矛先が歌詞やアレンジの大幅な変更に向かっているところには微妙なものを感じる。
確かに「当時そうすれば良かった」という後悔はあろうが、どこかで”凍結前の角松敏生”への認められなさ、なるものを感じているようにも思える。
しかしファンは、そんな稚拙さが残りつつの、でもありのままで表現していた”凍結前の角松敏生”を愛しているのだ。その愛が置き去りにされたような感じがしたのは、筆者だけだろうか。
角松氏の中で”凍結前の角松敏生”といまだに戦っているかのように、筆者には見える。まだ今も「I’ll be over me」の精神が継続中なのだ。
それは過去作品が今になって再評価されることに、不満であるような態度を取るところにも表れている。過去は過去、今は今と言う折り合いが、まだつかないように見える。
しかし本来人格とは、どちらかが制するようなものではなく、過去の自分も今の自分も緩やかに統合されることで、自分は自分だ、という感覚になれるものだ、と筆者は思う。
確かに自分の中での壁として、過去の自分を乗り越えていく、という段階は必要だろう。しかし、その戦いを止めるのも、自分自身が行うことである。
それこそがトラウマの傷が癒えて、過去の純朴な表現者としての”凍結前の角松敏生”を自由にしてやることである。
そして角松氏はプロのミュージシャンであり、同時に表現者である、という地点になって、初めて過去との折り合いが付き、もう一度王道ポップス・AOR的楽曲へと解放されるのではないか。
角松氏の中にあるアイデンティティの分断のようなものが、緩やかに統合され、かつての表現者としての角松敏生が、今のクオリティで楽曲を作れば最強なはずなのである。
もうそろそろ彼の中で、統合された”角松敏生”として過去を許してくれる日が来ないものか、と筆者は願うばかりである。
※【初心者向け】”はじめてのアルバム” – 第9回:角松敏生 各年代のおすすめ名盤を1枚ずつ選出!
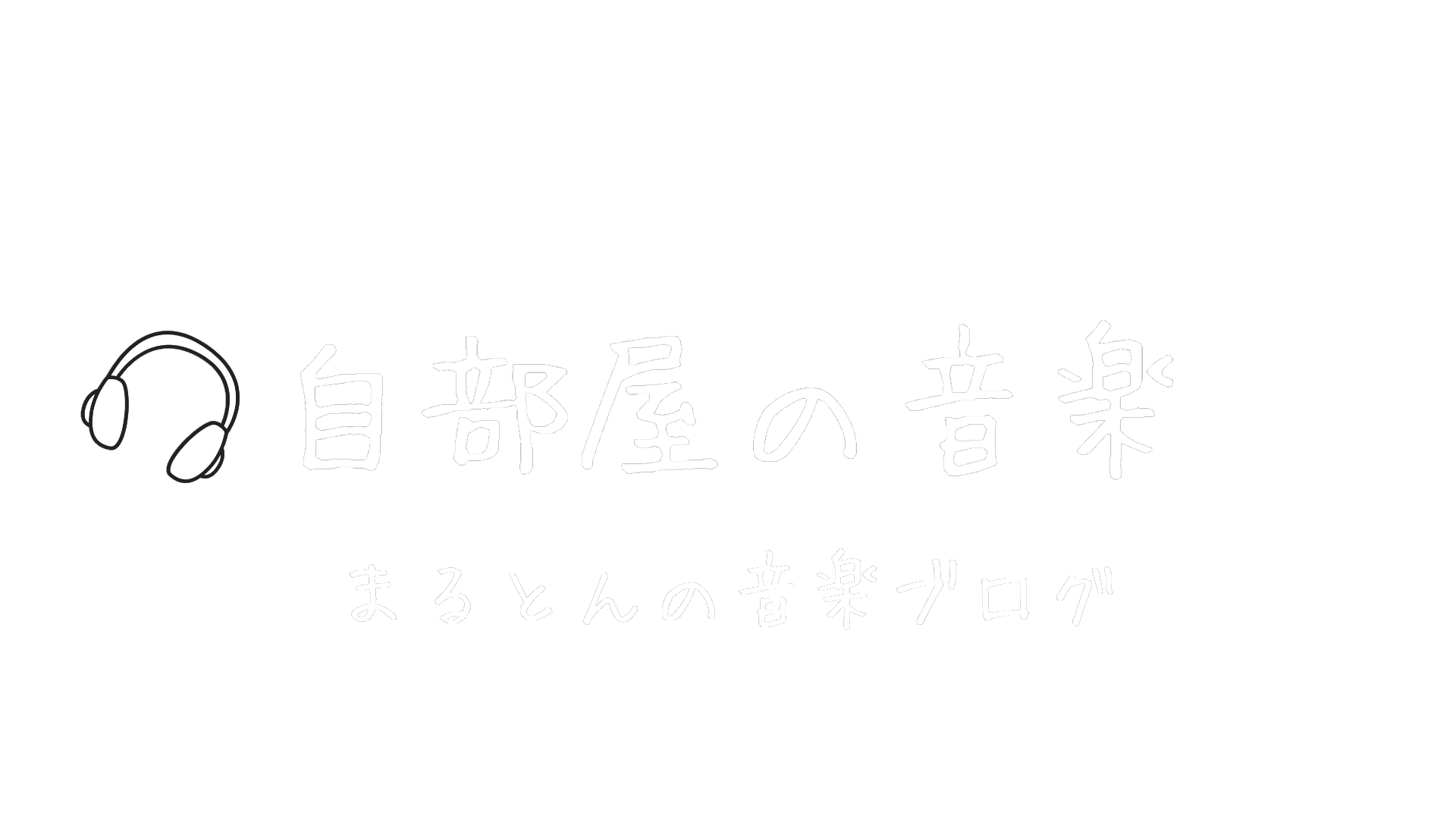























コメント