今回の記事は、ある時代にあった複数ジャンルの融合した独特の雰囲気の音楽についてである。
音楽の雰囲気で言えば、”暗く沈み込む美しい音楽”とでも言おうか。おそらく、この文言だけであれば、音楽ジャンル的には様々なものが思い浮かぶはずである。
今回取り上げたいのは、1980年代半ば頃を中心に、ニューウェイヴ・アンビエント・ジャズ・電子音楽、さらにはプログレなども融合した、前衛的な要素もある音楽である。
ニューウェイヴ・アンビエント・ジャズ・電子音楽のあわい – 5枚のおすすめアルバム
まずは取り上げたい音楽性について少し書いておこう。
70年代後半から80年代前半にかけてニューウェイヴが登場したが、電子音楽や前衛的な音楽と融合し、より奇抜な方向に行くバンドも多かった。
しかし一方で、より耽美的でゴシック要素の強い方向性のバンドも登場するようになった。ニューウェイヴやパンクの持つ尖った雰囲気を残しつつも、抒情的な要素を取り戻していくような音楽である。
そこにはアンビエントなどの環境音楽的要素(美しさや奥行き)が混ざり、ジャズのようなサウンドや即興演奏などのスリリングさ、さらには停滞していたプログレ方面からも歩み寄る向きもあった。
攻撃性や奇抜さも、後ろに少し残しつつ、耽美的で暗く沈み込むような美しさを持つ音楽が、80年代中盤を中心に登場していたように思われる。
たとえば暗く沈み込むような音楽であれば、ゴシックメタルもあるのだが、ゴシックメタルほどダイレクトにクラシックの影響を受けている訳ではない。
より前衛的な要素があり、肌触りは随分と違う。そしてアンビエント・電子音楽・ジャズなど、どの要素が強いかによっても、結構音楽性に違いが生まれるところが面白い。
とりわけ筆者の好きなアルバムを5枚紹介しよう。少し前の時代の作品が1枚、残りは全て80年代中盤以降の作品である。
The Durutti Column – The Return of the Durutti Column(1980)
今回紹介する様々な音楽の融合の時代より、少し遡って先駆的なことをやっていたアルバムを紹介したい。
それはThe Durutti Columnの1980年のデビュー作『The Return of the Durutti Column』である。パンク・ニューウェイヴの時代に作られた作品だが、音楽性はあまりに先駆的と言える。
ギターとキーボードを担当するVini Reillyが中心となった音楽ユニットで、静謐で浮遊感のあるギターと、時々バンドサウンドも登場するが、ギターのみのインストが多くなっている。
激しさや攻撃性を追求したパンクロックとはあえて真逆の、クリーンで奥行きのあるギターサウンドで静かな時間が流れる作品だ。それ自体が、流行の逆を行く、”尖った”サウンドとも言える。
単純にニューウェイヴと括るには違和感のある作品である。アンビエント的な要素もあれば、後のドリームポップサウンドの先取りとも言える。
The Durutti Columnは後の作品も素晴らしいものがあるが、この1stアルバムで既に音楽性は確立されており、あまりに独自のサウンドは異彩を放ちつつ、今も輝いている。
やはり何と言っても1曲目「Sketch For A Summer」、打ち込みの簡素なドラムが淡々と鳴り続ける中での、美しいギターの音色が生き生きとしながら、包み込むように聞こえるのが素晴らしい。
Cocteau Twins – Victorialand(1986)
イギリス、スコットランドのロックバンドCocteau Twinsの4枚目のアルバムである。暗く沈み込むような幻想的なサウンドと、メランコリックで独特なエリザベス・フレイザーのボーカルが特徴だ。
3枚目までのアルバムは徐々にゴシック的要素を強めつつ、ビートのあるポストパンクという感じであるが、本作ではアンビエントとも言えるビートのない作品に仕上がっている。
当時LPでのリリースでは、33回転ではなく45回転で収録されており、EP的な立ち位置だったのかもしれないが、音質的に高いものにこだわったのかもしれない。
本作の特徴を一言で表せば中毒性である。この暗く沈み込むような美しいサウンドの中に埋もれてしまうような感覚になり、一度ハマると抜け出せない。
ごく一部にリズムマシンが使われているが、基本的にはエフェクトのかかったギターとキーボードのみで構成されたサウンドだが、どこまでも広く、そして深いサウンドが作られている。
「Lazy Calm」の、まるで夢の中で鳴っている音楽かのような幻想的なイントロがたまらない。あまりに独特なサウンドで、ジャンルに括ることのできないアルバムである。
Depeche Mode – Black Celebration(1986)
イングランド出身、世界的に人気を誇るニューウェイヴのグループDepeche Modeのアルバムである。
彼らはニューウェイヴと電子音楽を軸としつつ、攻撃的な要素もありながら、本作ではアンビエント要素さえ感じるダークさと美しさがある。
ダンスミュージック的なビートも見られるが、どちらかと言えば、沈み込むような暗さと美しさが前面に出ているところがとても気に入っている。
ファンの間でも非常に人気の高い作品であり、確かにそれが頷ける内容の良さである。
また電子音楽と生楽器のバランスも良く、無機質過ぎず、一方でドライな雰囲気は残しつつ、というのがニューウェイヴと電子音楽・アンビエントの間という感じがする。
死や闇などがテーマになっている「Black Celebration」はダークな雰囲気が漂い、ゴシックの影響を感じさせる名曲である。
David Sylvian – Gone to Earth(1986)
JapanのボーカルであったDavid Sylvianのソロ作である。ソロ作としては通算3枚目、2枚組の大作であり、1枚目がボーカル曲で2枚目がインストとなっている。
Japan時代はグラムロックから始まり、ニューウェイヴや電子音楽を取り込み、ソロになってからはさらにアンビエントや前衛音楽まで取り込んでいくようになった。
本作はその過渡期とも言えるし、1つの到達点と見ることもできなくはない。1st『Brilliant Trees』にあったビート感は徐々に減り、沈み込むようなダークさ・美しさが目立つようになる。
そして本作2枚目ではボーカルもなく、静かに時が流れていくようなアンビエントが続いて行く。音楽における暗さとはサウンドがヘヴィなだけでなく、独特の音の隙間にあるようにも思える。
豪華なミュージシャンによる演奏も、非常に贅沢に使われているのが本作の特徴である。しかし足し算で詰め込むのではなく、日本の侘び寂びのような引き算の美しさがある。
アンビエントな雰囲気の楽曲も良いが、1枚目のラストに配置された「Silver Moon」が全てをかっさらうような名曲ぶりである。
The Cure – Disintegration(1989)
イングランド出身のポストパンクのバンド、The Cureの人気作の1つである。ロバート・スミスの特徴的な歌声と、変化の大きな音楽性が特徴である。
The Cureの音楽性は、初期のポストパンクからゴシック調になったり明るくなったりと変化が大きい。ただ”暗黒期”とも言えるダークで沈み込むようなサウンドは1つの特徴であろう。
既にその時期を脱して、バラエティ豊かなサウンドを見せていた80年代後半に、突如としてダークな作風が戻ってきたのが本作である。
80年代前半に見られたミニマルでダークなサウンドからさらに進化し、音の広がりや奥行きは保ちつつ、見事に沈み込むような美しいサウンドの構築に成功している。
暗い曲一辺倒という訳でもなく、優し気な雰囲気が漂う「Pictures Of You」などがアルバムの中のバランスを取っている。
※【初心者向け】”はじめてのアルバム” – 第16回:The Cure 入門作から個性的な暗黒作品まで
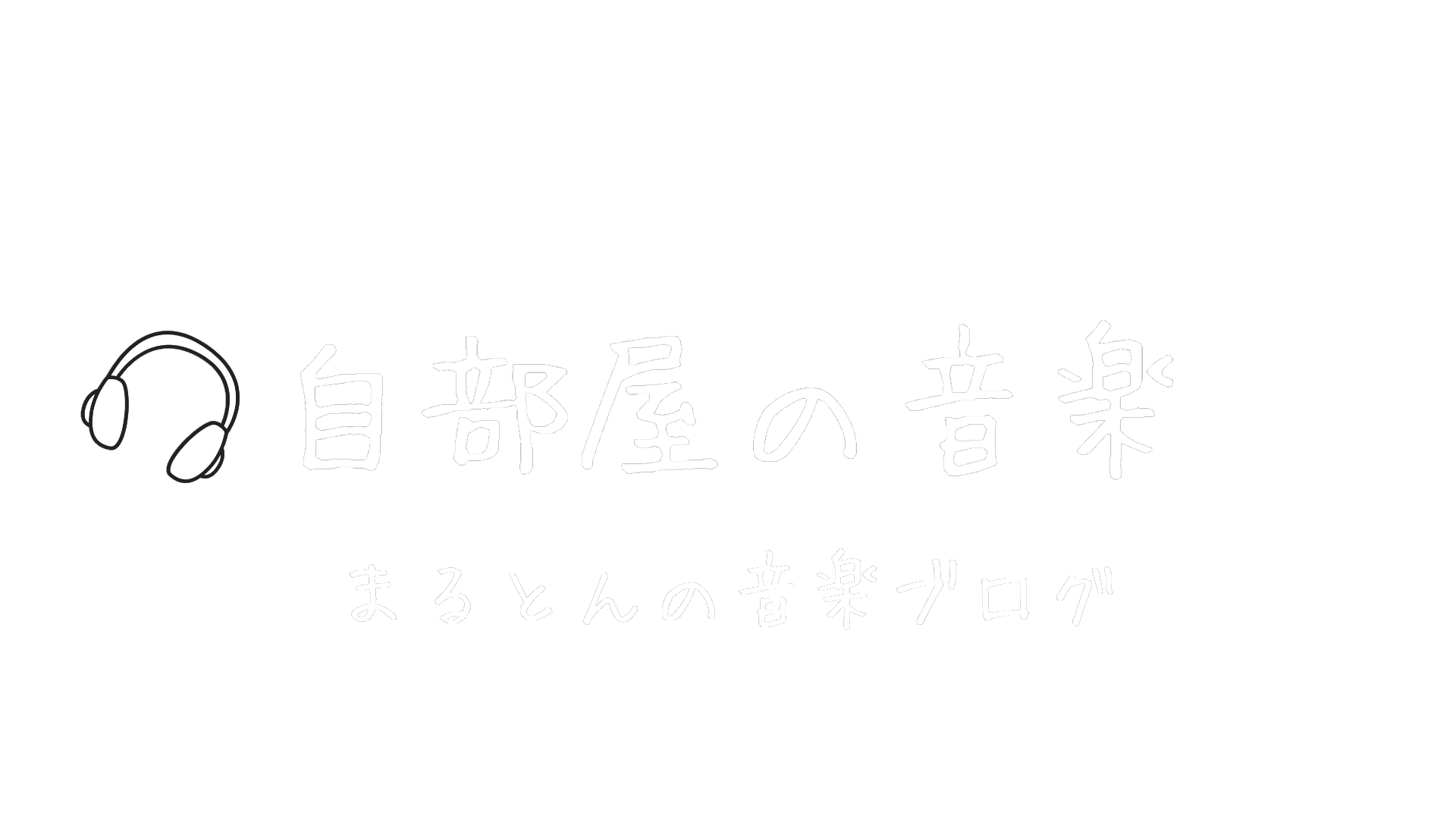


















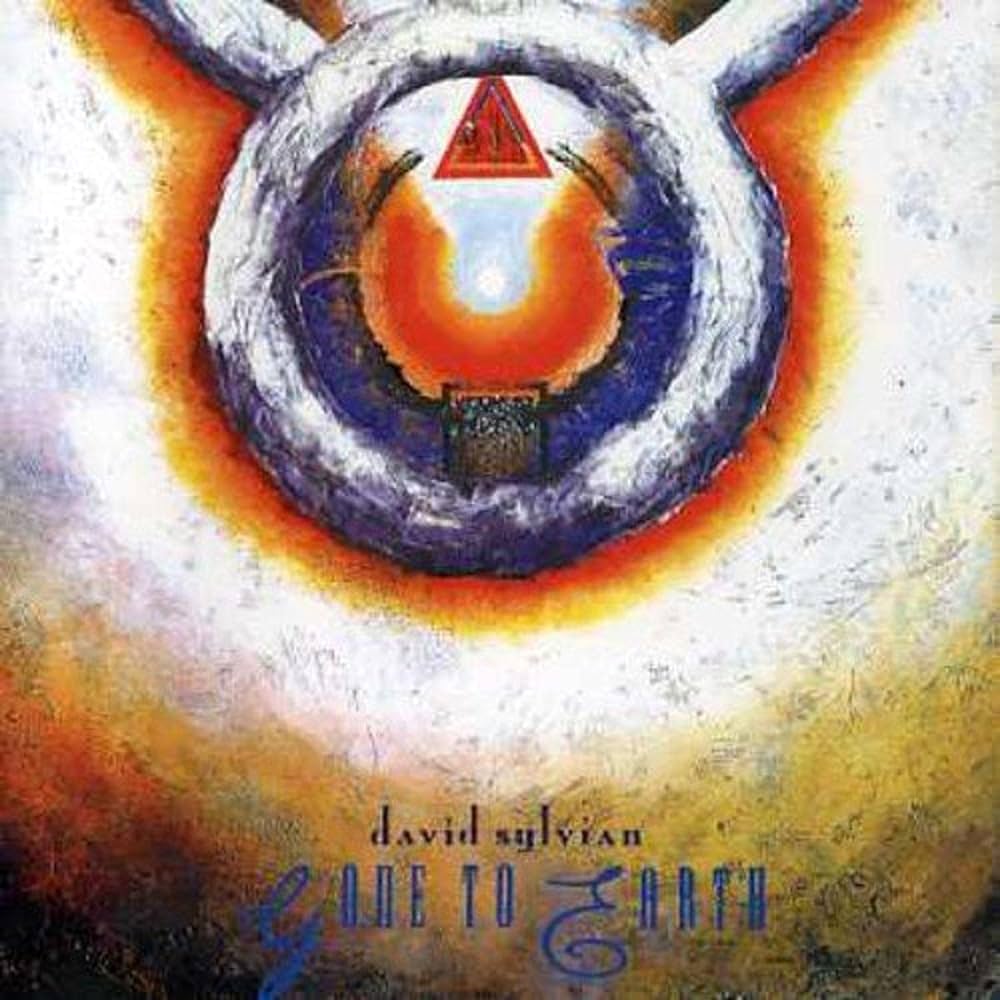



コメント