近年は活動ペースを落としつつ、新春ライブやフェス出演などで活動を続けるエレファントカシマシ。
彼らの活動の最初のピークと言えば、1997年の「今宵の月のように」に代表される、ポニーキャニオンに在籍していた時代(通称ポニーキャニオン期)である。
それ以前に在籍したエピックソニーの時代(通称エピックソニー期)の破天荒で尖ったロックサウンドから、より間口を広げたポップな作風に移行したことで知られる。
ただポニーキャニオン期の楽曲は、全面的にポップに振り切ったように見えて、実はエピックソニー期の武骨さと、新機軸のポップさが同居したような楽曲もみられる。
エピックソニー期とポニーキャニオン期の魅力が混ざり合うような楽曲の魅力は、かなり独特のものがある。今回はそんなエピックソニー期を感じさせるポニーキャニオン期の楽曲の魅力を掘り下げた。
エピックソニー期の雰囲気が残るポニーキャニオン期の楽曲の魅力とは?
ポニーキャニオン期と言えば、アルバムで言うと1996年『ココロに花を』から1998年の『愛と夢』までの3枚の時期のことを指す。
「悲しみの果て」「今宵の月のように」「風に吹かれて」など、ポニーキャニオン期を代表する楽曲は、エレカシのポップな部分を上手く前面に出した楽曲である。
しかしポニーキャニオン期はそうした楽曲だけではなく、エピックソニー期の名残を感じさせる楽曲もそれなりに存在する。
それはエピックソニー期の武骨さと、ポニーキャニオン期の切なさ・ポップさが、絶妙なバランスで混ざり合っている曲なのだ。
土台にはハードロックやパンクなどの荒々しいロックを据えつつも、ポップなアウトプットに成功しているタイプの楽曲と言える。
具体的には後で述べるが、たとえば1996年の『ココロに花を』はまだエピックソニー期の雰囲気を色濃く残しており、リードトラックの1つだった「ドビッシャー男」はかなりエピック寄りの楽曲である。
「孤独な旅人」はポップなメロディのAメロながら、Bメロ部分ではがなるような歌い方はエピックソニー期を思わせるものである。
こうした楽曲がポニーキャニオン期に生まれている背景には、エピックソニー期の歴史を少し押さえておく必要があるだろう。
破天荒なエピックソニー期にみられる変化
エピックソニー期のロック要素強めの楽曲を知るには、エピックソニー期の音楽的変化が関係している。
1988年に1st『THE ELEPHANT KASHIMASHI』でデビューしたエレファントカシマシは、RCサクセションに影響を受けたロックンロールバンドであった。
しかし分かりやすく衝動的なロックを鳴らしたのは1stまでであり、2nd『THE ELEPHANT KASHIMASHI II』からは内向的でフォークや演歌に近いような曲調もみられた。
1つの転換となったのは4th『生活』である。ボーカル宮本浩次氏の歌唱が異様に大きく聞こえるミックスが話題になることが多いが、音楽的な変化にも注目したい。
本作ではかなりハードロックやプログレッシブロックなど70年代のロックに影響を受けた作風に変わっている。曲も長尺となり、まさにアート色の強い70年代ロックを思わせる曲が多い。
その路線を受け継ぎつつ、3rd『浮世の夢』の雰囲気もある5th『エレファントカシマシ5』、そして1stのパンキッシュな要素を復活させようとした6th『奴隷天国』へと変化していく。
6th『奴隷天国』の頃には、リフを軸としたハードロックを中核に据えつつ、パンクやロックンロールを感じさせるようなエレカシ独特のロックが生まれつつあった。
『東京の空』こそエピックソニー期の原点?
そしてエピックソニーとの契約が終了することが決まっていた中で制作、リリースされたのが1994年の名作7th『東京の空』である。
渋谷陽一氏がブックレット内で絶賛していた本作は、ようやくエレカシの武骨さとポップさがちょうど良いバランスで成立した作品である。
本作での”武骨さ”とは、どこかヤケクソなほどの勢いがあり、これまでのような厭世的でウェットな雰囲気は後退して、カラっとした男臭さのようなものに変貌している。
一方で安易に”頑張ろう”などの前向きな意味での男臭さでもなく、どこかぶっきらぼうでいて、悲哀も感じさせるものだ。
それを破壊的な歌唱や演奏で表現するのではなく、ポップな聴きやすい形でアウトプットがなされ始めた作品が『東京の空』だった。
エピックソニー期は基本的に『東京の空』を原点にして、その延長線上にあると筆者は考える。
『東京の空』の中でもポップ寄りの曲、ロック寄りの楽曲がある。たとえばポップ寄りの「もしも願いが叶うなら」「誰かのささやき」などは、ポニーキャニオン期のポップ路線を予感させる。
一方で「この世は最高!」「甘い夢さえ」「男餓鬼道空っ風」など、それまでのエピックソニー路線を受け継ぎつつ、男臭いロックを展開している。
これらの楽曲は、ポニーキャニオン期にも受け継がれており、今回取り上げたい楽曲はまさにこの路線の楽曲だ。
それらの曲は、言ってしまえば『東京の空』を感じさせるポニーキャニオン期の楽曲と言っても良いかもしれない。ただ『東京の空』よりも表現が磨かれて、洗練されたものになっているのが特徴である。
※【アルバムレビュー】エレファントカシマシ – 『東京の空』(1994)
エピックソニー期の雰囲気が残るポニーキャニオン期の楽曲紹介
ここまで述べたような作風のポニーキャニオン期の楽曲を具体的に取り上げ、その魅力を紹介してみようと思う。
3枚のアルバムしか残していないポニーキャニオン期であるが、各アルバムに何曲かずつそうしたタイプの曲が入っている。
『ココロに花を』『明日に向かって走れ-月夜の歌-』『愛と夢』の3枚に加えて、シングルのみ収録の楽曲、さらには当時作られた未収録楽曲も含めて紹介したい。
8th『ココロに花を』+未収録曲
ポニーキャニオンに移籍した第1弾のアルバム。シングル『悲しみの果て』がスマッシュヒットし、アルバムもオリコンチャート週間10位を獲得している。
エピックソニー期の荒々しい音楽性から脱しようと言う方向性と、まだとどまろうとする方向性が、独特な緊張感を生み出しつつも、全体的にはポップな雰囲気のロックアルバムに仕上がっている。
なお2013年にリリースされた『great album deluxe edition series 2 「ココロに花を」deluxe edition』には、アルバムに収録されなかった当時のデモ音源が収録されている。
本作に関してはそのデモ音源からも紹介している。
ドビッシャー男
既に紹介した通り、本作のリードトラックにして、最もエピックソニー期の色合いを感じさせる楽曲である。この曲を1曲目に配置しているあたり、まだエピックの方向性も残している印象だ。
エピックソニー期から続く”男シリーズ”の曲であり、”ドビッシャー”は言葉遊びのようなもので、ドビュッシーから来ていると言う噂もある。
この曲がまさに『東京の空』における「この世は最高!」「極楽大将生活賛歌」「男餓鬼道空っ風」などの路線をそのまま受け継いでいる。
ダイナミックかつ男臭い、ちょっとやさぐれた雰囲気のハードロックであり、次に続く「悲しみの果て」と同じ人物が作っているとは思えない荒々しさが魅力である。
ただ演奏やミックスなども含めて、エピックソニー期に比べると、まとまった音として作られており、メンバーというよりプロデューサーの意向だったと思われる。
かけだす男
こちらも”男シリーズ”の楽曲であり、どこか焦燥感に駆られるようなメロディラインと、ダンスビートが独特な楽曲である。
ミックスの終わったこの曲をウォークマンで聴いた宮本氏がウォークマンを叩き壊した、というエピソードはファンの間ではよく知られている。

エピックソニー期の武骨さを残しつつも、やはりエピックソニー期とは異なる、パッケージ化されたサウンドに仕上がっているようには思える。
しかしこの独特な緊張感こそ、ポニーキャニオン期の始まりの不思議な魅力である。「Baby, Baby」という宮本氏の叫びがどこか悲痛にも聞こえる、差し迫った感じが実にカッコいい。
孤独な旅人
『悲しみの果て』の次にリリースされたシングル曲。雰囲気としてはどこか牧歌的と言うか、かなり古い時代のロックをイメージしたような楽曲に思える。
しかし最初は優しげなAメロから、Bメロに入るとあわや絶叫しそうな勢いの強いボーカルを聴くことができる。ここにもエピックソニー期とポニーキャニオン期の間の独特な雰囲気がある。
この曲はMVも独特であるが、前半部分は青空のもとお花畑のセットの中で演奏するメンバーのシーンである。後半では夕日にかわり、宮本氏がセットを破壊し始めると言う衝撃の映像である。
引きの映像になり、お花畑のセットを放り投げたり、蹴飛ばしたりしていく、エピックソニー期の宮本氏を思わせる。
うれしけりゃとんでゆけよ
『ココロに花を』に収録のミドルテンポのロックナンバーである。アルバムリリース後に発売されたシングル『悲しみの果て』のカップリング曲に選ばれている。
アルバムの中でも実は最もエピックソニーの雰囲気を漂わせている。曲調は『東京の空』収録の「甘い夢さえ」などと近いものがあり、男臭い感じのするハードロック的な曲だ。
エピックらしさを感じさせる要因の1つが歌詞にもある。「ぶちのめせ世間の渦」など尖った表現があり、ラブソング主体となっていくポニーキャニオン期にあってはかなりロックな歌詞である。
とは言え、エピックソニー期のど真ん中の時代に比べれば、かなりポップな仕上がりであり、アルバムの中に上手く収まっているように感じられる。
Baby自転車
先行シングル『孤独な旅人』のカップリング曲に選ばれている楽曲である。軽快なロックンロールナンバーであり、割と珍しいタイプの曲で、この頃ならではの雰囲気がある。
『東京の空』で見せたヤケクソな元気さ、少しコミカルなタッチの延長線上にあり、「真冬のロマンチック」などの雰囲気を、もう少し洗練させた感じである。
「ステイション」「ロケイション」と韻を踏んでみたり、横文字を入れてみたり、とこれまでにないアプローチを入れているのが可愛らしくも見えてしまうところだ。
ライブでは結構盛り上がる曲で、楽しげな気持ちになれる曲である。
夢を見ようぜ(未収録)
エピックソニーから契約を切られた後に、『ココロに花を』収録の楽曲とともにライブで披露されていた楽曲である。
90年代から比較的最近に至るまで、ライブではよく披露されている楽曲ながら、スタジオ音源としての正式なリリースはない曲である。
『great album deluxe edition series 2 「ココロに花を」deluxe edition』にはデモ音源が収録されている。歌詞は「夢を見ようぜ」がほとんどで、ライブのための楽曲と言う位置づけだったのかもしれない。
こうした言葉遊びのような曲はエピックソニー期らしさを感じさせる。一方でライブでお客さんを乗せるような曲調は、確実に新たな方向性に向かっているのも感じさせるのだった。
BABY BABY(未収録)
『great album deluxe edition series 2 「ココロに花を」deluxe edition』に収録されていたデモ音源の中の1つであり、deluxe editionで初めて公開になった楽曲である。
当時の歌詞に多用されていた「BABY」を繰り返す楽曲であり、かなりロック色の強い楽曲である。エピックソニー期の雰囲気がありつつも、より洋楽テイストの強い作風になっている。
個人的にはこの曲の中間部の展開が、エレカシの全ての楽曲の中で、最も好きな展開である。ミドルテンポでどっしり終わるのか、と思っていたら、急にアッパーな展開が入って来るのが素晴らしい。
こうした急展開はエピックソニー期の後半に多いものであり、ハードロックに影響を受けていたものと推測される。
9th『明日に向かって走れ-月夜の歌-』
バンド最大のヒット曲「今宵の月のように」を含むアルバムで、週間オリコンチャートでは2位を獲得している。
『ココロに花を』の方向性を踏襲しつつも、陽気な雰囲気だった前作から、より哀愁や切なさを感じさせるような楽曲が増えた印象の作品である。
「今宵の月のように」「風に吹かれて」など、よりメロディの美しさが前面に出た楽曲が多いが、テンションの高いアルバムでロック要素の強い曲も一部に残されている。
戦う男
アルバム先行シングルとしてリリースされた楽曲で、KIRIN「JIVE COFFEE」CMソングに起用された。
アルバムの中では最もロック色の強い楽曲であり、冒頭の歪んだギターによるリフはエピックソニー期から脈々と続くサウンドである。
冒頭のリフから歌が始まると転調しており、歌の部分はポップな雰囲気、イントロはかなり激しい、という棲み分けができている、実は凝った曲である。
MVでメンバーが走っている映像に象徴されるように、疾走感のある楽曲となっている。
昔の侍
ラブソングや青春を感じさせる楽曲が多いアルバムの中、異色のテーマの楽曲である。売れっ子のバンドの歌詞として「自ら命を絶つことで」と言うフレーズはかなり衝撃的だ。
どうやらこの曲自体はエピックソニー期に出来上がっていたようであり、発表がこのタイミングとなったのだった。確かに歌詞の文学的な雰囲気など、エピックソニー期らしさを思わせる。
ただアレンジ的にはがっつりロックと言うよりは、ストリングスを用いて壮大で美しい印象も与える。武骨だがポップと言うこの曲の雰囲気は、まさにこのタイミングでの発表が良かったのだろう。
この曲がアルバムに入っていることで、背筋を正すというのか、凛とした気持ちになるのだった。
せいので飛び出せ!
実はこのアルバムは、全曲が宮本氏単独によるものではなく、他のメンバーが作曲に参加している楽曲がある。「せいので飛び出せ!」もその1つで、ベースの高緑成治氏が参加している。
印象的なギターリフが楽曲を引っ張っていきつつ、サビの部分ではかなりポップなメロディが登場するという、これも武骨さとポップさのバランスにおいて絶妙に良いラインである。
やはり同じ組み合わせの『東京の空』収録の「星の降るような夜に」のような、どこか青春を感じさせる、明るい曲調がこの2人の組み合わせの特徴のようだ。
切ない雰囲気の曲も多いアルバムの中で、この曲も良い味付けになっている。
10th『愛と夢』+シングル曲
ポニーキャニオン期最後のアルバムとなった本作は、ラブソング主体でありつつも、前作以上に内省的で静かな作風となっている。
宮本氏がカセットのMTRを用いてデモ音源を作り始めたことで、アレンジはバンド主体ながら、どこか無機質な感じも漂っている。
『愛と夢』という一見明るそうなテーマでありつつ、その奥には尖った内面が見え隠れするような、どこか危険な雰囲気もはらんだ作品だと筆者は思っている。
エピックソニー期の雰囲気はますます後退してはいるが、やはりロック色の強い曲にはその名残も見られる。
涙の数だけ
最初に取り上げたのは、アルバム未収録でシングル『はじまりは今』のカップリング曲である。非常にヘヴィなリフで始まるこの曲、実はエピックソニー期を思わせる隠れ名曲だ。
冒頭のリフからAメロ部分に関しては、『東京の空』や『ココロに花を』辺りを思わせる雰囲気であるが、Bメロと言うかサビの部分はポップなメロディが印象的である。
歌詞の内容を見ても、「涙の数だけ働いて」「慌てて駆け出しゃビルの町」など、エピックソニーの頃を思わせるような独特の言い回しが見られる楽曲なのだ。
ポップな作風が増えていた時期にあっては、貴重なエピックソニー期を感じさせる楽曲なのである。
ヒトコイシクテ、アイヲモトメテ
先行シングル第2弾としてリリースされた楽曲で、ニッポン放送『オールナイトニッポン』エンディングテーマなどに起用された。
非常に歌謡曲的な哀愁漂うメロディであり、エピックソニー期とはずいぶん違う方向性にも思えるのだが、どうしても筆者はエピックソニー期の武骨さのようなものを感じる曲だと思う。
やはり冒頭のリフの荒っぽさにそれが表れているように感じる。Led Zeppelinなど70年代ハードロック的なギターリフから始まるところに、エピックソニー期の名残を感じさせる。
楽曲自体は独特の哀愁と色気を感じさせるものであるところに、エレカシ特有の武骨さが良い味付けと言うか、不思議な魅力を引き出している。
寝るだけさ
冒頭のスライドギターから、ややルーズな感じで進んでいくロックナンバーである。シングル『愛の夢をくれ』のカップリング曲にもなっている。
雰囲気は『ココロに花を』の頃に近く、どこか牧歌的な雰囲気が漂いつつ、サウンドはロックバンドらしいものとなっている。
楽曲の展開は「涙の数だけ」と似ており、ロックっぽいメロディの前半と、中間にはポップで美しいメロディが登場するという、曲の中で2つの顔があるような展開になっている。
歌詞も「生き延びてまた明日も俺は働くのさ」など、単なるラブソングやポップスの主題とは異なる雰囲気が漂っているのが、エピックソニー期の名残を感じさせる。
ココロのままに
シングル『夢のかけら』のカップリング曲で、近年では2023年公開の映画『愛にイナズマ』の主題歌に起用されたことでも話題になった。

『愛と夢』のアルバム前半はメロディアスな曲を並べ、後半の「寝るだけさ」に続いてロックな雰囲気の楽曲がこの「ココロのままに」である。
冒頭のリフからAメロは、やはりリフ主体のロックな展開で、サビは分かりやすいというこの時期の定番の展開である。
珍しく間奏のギターソロが長く、ブレイクの後に「ホウッ」というよく使われる掛け声が多用されている。こうした独特のノリがエピックソニー期の名残を感じさせるのである。
ポニーキャニオン期にはギリギリ叫び過ぎない歌唱で収録されているが、サビのメロディはライブでは叫んで歌うような心地よさがある。
まとめ
今回の記事では、エレファントカシマシのポニーキャニオン期におけるエピックソニー期を感じさせる楽曲を紹介した。
ポニーキャニオン期はポップな作風で変貌したと言われるエレカシであるが、実はエピックソニー後期の作風をかなり受け継いでいることが分かる。
とりわけ『東京の空』の作風がポニーキャニオン期の土台になっており、そこにどれだけポップな要素を交えつつ、楽曲を展開させていくか、という時期だったように思える。
そしてポニーキャニオン期の魅力には、エピックソニー期の名残、それは武骨さのようなものが漂っているところにあった。
その後の「ガストロンジャー」以降、東芝EMI期に入ると、そうした男臭い武骨な感じは次第に薄れていくのであり、ポニーキャニオン期と東芝EMI期の間に境目があるように感じている。
今回のように、エピックソニー期とポニーキャニオン期を地続きとして聴いてみると、そこに流れる共通した楽曲の雰囲気を感じ取ることができるだろう。
※【エレファントカシマシ】エピックソニー期という時代 前編(1st『THE ELEPHANT KASHIMASHI』~4th『生活』)
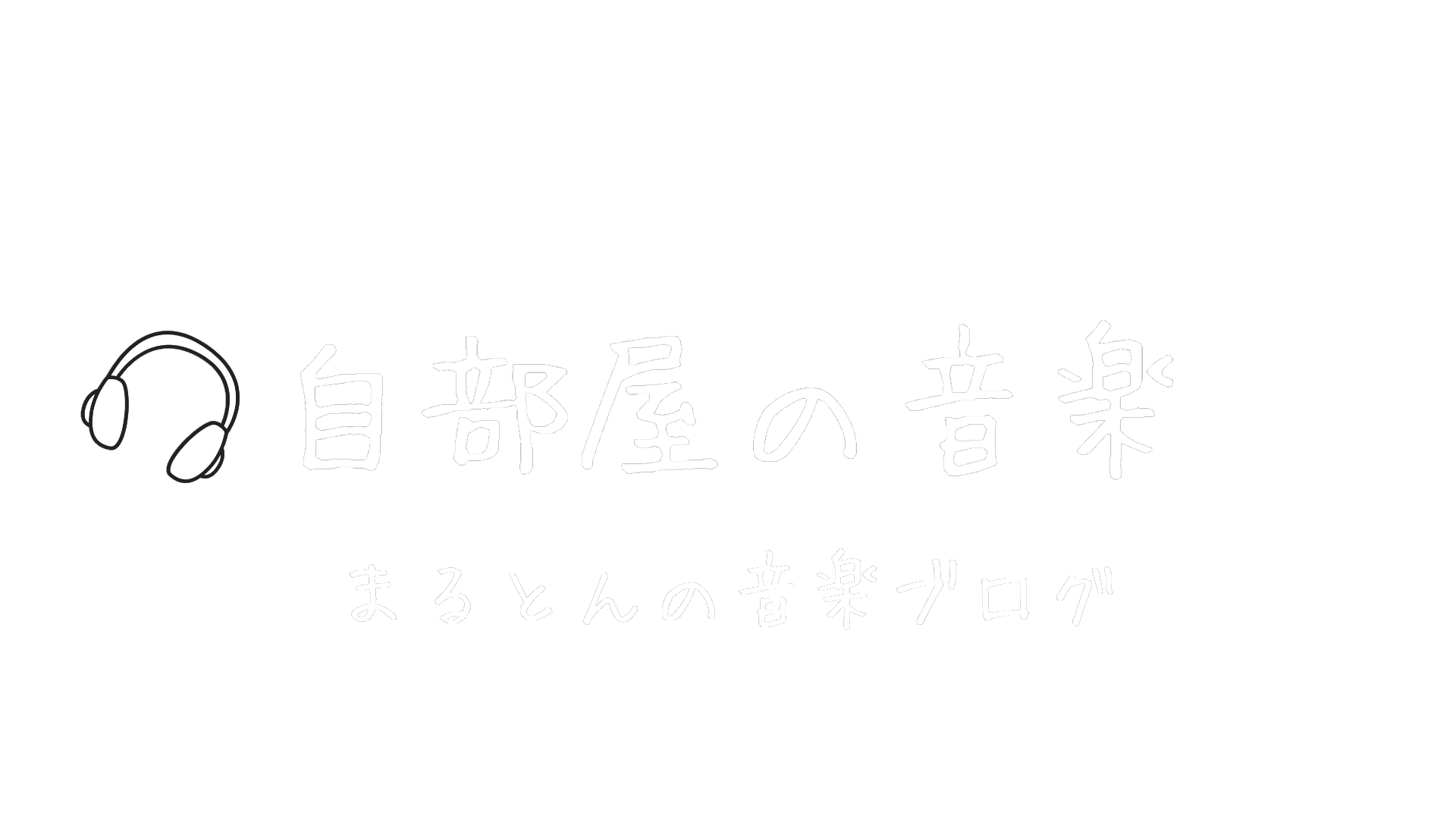



















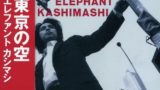


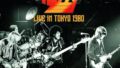
コメント