ソングライター浜田省吾は、デビューから45年以上の活動を続けている。
2023年から7年ぶりとなるコンサートツアー「ON THE ROAD 2023 Welcome back to The Rock Show youth in the “JUKEBOX”」を行い、約20万人を動員するなど支持を集めている。
浜田省吾氏のアルバムには名盤が多数あるが、今年でリリースから40年を迎える1984年の9thアルバム『DOWN BY THE MAINSTREET』もその1つである。
代表曲の1つ「MONEY」を収録する本作だが、ある種のコンセプトアルバムとしての完成度も高く、40年経った今も色褪せないアルバムであると筆者は思っている。
今回の記事では、リリース40年を記念して『DOWN BY THE MAINSTREET』のアルバムレビューを行い、今なお色褪せない理由について考察してみようと思う。
『DOWN BY THE MAINSTREET』作品概要
| No. | 曲名 | 時間 | 編曲 |
|---|---|---|---|
| 1 | MONEY | 5:15 | 町支寛二 |
| 2 | DADDY’S TOWN | 5:15 | 板倉雅一 & 江澤宏明 |
| 3 | DANCE(Album Version) | 5:17 | 浜田省吾 |
| 4 | SILENCE | 5:51 | 古村敏比古 |
| 5 | EDGE OF THE KNIFE | 4:54 | 江澤宏明 |
| 6 | MIRROR | 0:35 | 町支寛二 |
| 7 | A THOUSAND NIGHTS | 2:39 | 板倉雅一 & 江澤宏明 |
| 8 | HELLO ROCK&ROLL CITY | 5:12 | 古村敏比古 |
| 9 | PAIN | 5:38 | 板倉雅一 |
| 10 | MAINSTREET | 4:26 | 浜田省吾 |
| 収録時間 | 45:02 |
- 発売日:1984年10月21日、1990年6月21日(CD再発)、1999年9月8日(CD再々発初回限定盤)、1999年9月29日(CD再々発)、2021年6月23日(CD再々々発)
- レーベル:CBS・ソニー、クリアウォーター(再々発・再々々発)
- プロデュース:浜田省吾
浜田省吾の9thオリジナルアルバム『DOWN BY THE MAINSTREET』は、1984年10月21日にリリースされた。1999年のCD再発時には、リミックス・リマスタリングが行われている。
アルバムのテーマは、地方の工業都市に住む10代の若者の物語である。本作のテーマについて、浜田氏は、「1st『生まれたところを遠く離れて』の後に作らなければいけなかった」ものと語っている。
2ndアルバム以降の70年代は、職業作曲家的なポップな作風で売り出されていたため、1stアルバムの作風から方向転換していた。
本作リリース時の浜田氏は既に30代、等身大の歌ではなく、映画のプロデューサー・脚本家のような感覚で物語を作り、そのサウンドトラックを作るようにアルバムを作ったそうだ。
洋画のポスターのようなイラストのジャケット、英語で統一された曲名などからも、本作はコンセプトアルバムの色合いが強く、実は浜田氏のアルバムの中でも異色作とも言える。
本作は制作の体制などで初めてづくしだった。まずは所属していたホリプロを離れ、個人事務所『ロード&スカイ』を設立して、初めての作品である。
また初の浜田省吾自身によるプロデュース作品でもある。さらにはツアーバンドのメンバーとレコーディングを行った初のアルバムだ。
これまで水谷公生が担っていた編曲を、当時のバンドメンバーが分担して編曲を行っている。浜田氏いわく「反省点もある」とのことだが、自らで作り上げた記念盤とも言えるだろう。
基本的な流れはその後も継承され、現在につながる浜田省吾というプロジェクトの形を作り上げた作品で、次作『J.BOY』(1986)で大きく花開くこととなる。
本作はオリコンチャートで2位を獲得し、当時は自身最高位であった。
※ファンクラブ誌に掲載された浜田氏自身による作品解説(オフィシャルサイト)
全曲ミニレビュー
アルバム『DOWN BY THE MAINSTREET』の各楽曲についてレビューを行っていきたい。
本作はまるで青春映画のサウンドトラックのような内容のアルバムであり、全編を通じて地方都市に住む10代の少年たちの物語が展開されていく。
各楽曲で描かれるものにも触れつつ、音楽的な部分も述べておこうと思う。
MONEY
明るいタッチのジャケット写真からは想像もつかない、ハードなアルバムの幕開けである。浜田省吾を代表する1曲「MONEY」はシングルカットされていないものの、知名度が高い楽曲だ。
その理由の1つが、日本のポップスにはあまり見られない”お金”をテーマにした歌詞だからだ。この曲では、地方都市に住む若者やその家族がお金に翻弄されながら生きる姿を描き出している。
バブル経済へと向かって行く日本の状況と重なり、非常に社会性の強い楽曲だ。
サウンドは町支寛二氏による印象的なギターリフから始まり、ハードロックの影響を感じさせるもの。さらには中間部の超絶ギターソロは圧巻の一言である。
「MONEY」が1曲目に配置されることで、本作が単に若者たちの間に閉じた物語でないことを最初に宣言している。若者たちが生きている社会が周りに確実に存在し、影響していることを示唆している。
DADDY’S TOWN
「MONEY」の激しいサウンドから、ピアノとサックスの美しいイントロに導かれて始まるこの曲。明るい曲調のストレートなロックナンバーの「DADDY’S TOWN」である。
ある意味、最も浜田省吾らしいタイプの楽曲である。「MONEY」が本作の強烈な序章とすれば、この曲がアルバムのストーリー的には始まりの楽曲と言えるようにも思う。
ここで歌われているのは、バイクに乗って暴れている少年たちの日常である。工場で平日は働き、週末にはバイクを走らせるという日々であり、モデルとなった人物がいるのかもしれない。
1つの短編映画を見たかのような感覚になる1曲であり、本作の作風を象徴するような曲に仕上がっている。2曲目に配置されているのも納得できる、アルバムの顔とも言える曲だ。
DANCE(Album Version)
リリース当時に唯一シングルカットされている楽曲であり、本作ではアルバムバージョンとしてリアレンジされた。
歌謡曲的とも言えるストレートなメロディとダンスビートを組み合わせたこの曲。ディスコなどの軽快なダンス曲ではない、あえて”ヘヴィなダンス曲”を目指して作られたとのこと。
この曲の主人公は、大都市に出て地下鉄で仕事に通う人物であり、何か大切なものを失ってしまったかのような虚無感の中で生きており、”DANCE”という言葉がより空しく響く。
メロディが良いのはもちろんだが、こうした綿密な世界観の構築と音楽との融合は浜田氏の真骨頂とも言えるだろう。
なお2020年にリメイクされた音源では、より現代的なダンスアレンジになったが、曲の佇まいは変わっていないように感じる。
SILENCE
静寂・沈黙を意味する”Silence”をタイトルにしたこの曲。やや暗いトーンのバラード曲であり、簡素なアレンジに浜田氏の悲痛な雰囲気のボーカルが響き渡る。
LP盤ではA面最後の曲であり、本作の物語の全編の締めくくりということだろう。
ここで歌われているのは、若者たちが社会の中で生きていく途上で、いったい自分の心はどこに向かっているのか、と立ち尽くすような感覚である。
1番と2番では別の主人公の物語のようにも見えるが、それぞれ自分の生活スタイルを送りながら、心は全く満たされず、この先どうなっていくのだろうという不安の中で生きている点は共通する。
漠然とした不安をテーマにしたこの曲は、ある意味浜田氏自身と重なる部分でもあり、これまでの曲に比べると俯瞰の度合いは小さい。浜田氏の若き時代の心情を垣間見ることもできる気がする。
EDGE OF THE KNIFE
ここまで2曲ダークな雰囲気が続いたが、一転してゆったりと心地好いサウンドのポップス「EDGE OF THE KNIFE」が配置されている。
サウンド的にはThe Beach Boysなどに通じるサーフポップ・ロック的な趣のように筆者は感じている。
タイトルの”The edge of the knife”とはナイフの刃と言う意味だが、”on a knife-edge”が「極めて不安定な状態」という意味であり、こちらがタイトルの意味に近いように思える。
歌詞で描かれるのは、1番は若い男女のとてもロマンチックな恋愛の光景である。まるで青春映画を観ているかのような、美しい情景が歌われる。
一方で2番のBメロでは、俯瞰した視点から描かれる。まるでナイフのエッジを歩くかのような不安定な恋は、あっという間に終わりを告げたことが明らかになって曲が終わる。
若い頃の永遠に続くかのように思えたロマンチックな恋も、明日終わるかもしれないし、将来的に見れば儚い一時の出来事だったりする。
つまりは、ラブソングのように見えつつ、テーマは”若さ”そのもので、その最たる題材として恋愛が選ばれたに過ぎない。本作に通底するテーマに沿った重要な1曲ではなかろうか。
MIRROR
30秒ほどの短い序曲のような位置づけの楽曲である。LP盤のB面では、「EDGE OF THE KNIFE」から古き良きアメリカンポップス的な趣の楽曲が続いている。
浜田氏のバンドには欠かせないギターの町支氏だが、コーラスワークの技術が非常に高い。この楽曲でも本格的なコーラスを聴くことができる。
なお2020年のリメイクシングル「MIRROR/DANCE」では、よりパワーアップしたコーラスワークを楽しむことができ、35年の時を経て生まれ変わったバージョンも是非聴いてみてほしい。
A THOUSAND NIGHTS
「MIRROR」に導かれる形で、そのまま「A THOUSAND NIGHTS」に流れ込む。組曲のような形式になっている点が面白い。
この曲は浜田氏のルーツとも言えるようなR&Bをベースにした楽曲で、他の曲が5分ほどの長さに比して、2:39しかないというアメリカのオールディーズのような尺の楽曲だ。
歌の主人公は、地方都市で歌を歌っている青年だろうか。短い歌詞の中で、売れない時代からヒットするまでを歌っているようにも思える。
どことなく浜田氏とも重なる世界観であるが、これも短編映画のような物語性のある楽曲だ。
HELLO ROCK&ROLL CITY
「A THOUSAND NIGHTS」の世界観から導かれる形で、ライブには欠かせない楽曲「HELLO ROCK&ROLL CITY」へと続く。
日本の様々な都市にコンサートツアーをしているミュージシャンが主人公であり、この曲も浜田氏自身と重なる楽曲となっている。
これも浜田氏のルーツであるR&Bやロックンロールをベースにしたもので、ホーンを交えたゴージャスなロックサウンドに仕上がっている。
Cメロ部分では実際の楽曲名が登場するなど、現実とリンクする形になっている。架空の物語のアルバムながら、それを歌う浜田氏自身が映画に出演しているかのような感覚になる。
意外にも5分以上ある楽曲であるためか、近年のコンサートでは2番は歌われず、コンパクトな形にアレンジされる。
PAIN
一気に曲の流れは変わり、荘厳な雰囲気すら感じる名バラード「PAIN」である。
この曲は一聴すると失恋について歌っている楽曲のようにも思えるが、もう一段深く、普遍的な人間の心理を歌ったものであるところが秀逸だ。
それはタイトルにもある「PAIN」であり、”痛み”と訳せるが、単にストレスを感じた状態と言う意味ではなく、文字通り心が傷つく状態、その最たるものが喪失体験ではないだろうか。
ここで歌われているのは、大切な何か・誰かが目の前からいなくなる喪失体験であり、そして人は不思議なことにそこから立ち上がり再び生きていくのである。
しかし一見取り戻せた日常生活の先には、ふいに悲しみが後から襲ってくる。それが喪失にまつわる心理であり、この曲ではそういった人間の心理を的確に歌っている。
若者をテーマにしたアルバムだが、「PAIN」に関しては普遍的なテーマである。若者であれば、喪失への完成も豊かであるがゆえ、傷つきは大きなものになるのかもしれない。
※「PAIN」についてはこちらの記事でも詳しく書いている。
MAINSTREET
ラストに配置されたのは、本作のタイトル曲と言っても良い「MAINSTREET」である。浜田氏によれば、映画のエンドロールで流れるようなイメージでここに配置された曲らしい。
ヘヴィな「MONEY」で始まった本作ではあるが、ラストは突き抜けるようなストレートなロックで締めくくるところに爽快感がある。
歌詞の内容も、地方都市での物語の締めくくりに相応しく、街の通りとそこに集まる人々そのものをテーマにしている。
本作を通じて、何人もの登場人物が様々な体験をし、考えてきたが、最後は「走るだけ」である。やはりロックミュージックであるからして、あれこれ考えずに身体を動かせば良いのだ。
そうした音楽の楽しみ方を教えてくれるかのような、シンプルに盛り上がれる曲だ。だからこそライブでは1曲目に選ばれたりするのも納得である。
総評 – なぜ発売から40年を経ても色褪せないのか
それぞれの楽曲ももちろん魅力的であるが、この『DOWN BY THE MAINSTREET』はアルバムと言う単位においても、非常にクオリティの高い作品である。
発売から40年経った今も色褪せない作品になっていると筆者は感じている。本作は浜田省吾の代表作の1つでもありつつ、実は異色の作品であり、独特の魅力のある作品のように思える。
本作特有の魅力について、最後に掘り下げて書いてみようと思う。
実は珍しいコンセプトアルバム
まず本作がユニークであるのは、浜田省吾氏の歴史の中でも珍しいコンセプトアルバムになっている点であろう。
繰り返し述べている通り、本作は地方都市に住む少年たちが主人公の物語がアルバム全編を通じて描かれている。
洋画のポスターのようなジャケットに、英語のタイトルなど、雰囲気作りも含めてトータル感の強いアルバムになっている。
浜田氏の作品では、楽曲の方向性に統一感があることはあっても、アルバム1枚で1つの世界観に絞って制作されたものは本作だけと言っても良いのではないだろうか。
そして架空の短編映画を観たかのような感覚になる本作は、良い映画が後世に継がれていくように、特定の時代の雰囲気をあまり感じさせない作品になっているようにも思える。
こうした作品をクオリティ高く作り上げられたのも、浜田氏が10代の少年の物語を俯瞰しながら作れる年代になっていたからではなかろうか。
本来は自らが20代の頃、心情的に近い時代に作りたかったテーマの作品だと言うが、きっとその頃に作ったならば、全然違った趣の作品になっていただろう。
10代、20代を経て、様々な経験を積んだ浜田氏だからこそ、10代の物語を奥行きを持って描けたように思う。
とりわけ”自分”ばかりに目が行きがちな10代・20代とは異なり、彼らを取り巻く社会背景を描いているところに、浜田氏の俯瞰の視点が表れている。
そして歌の主人公の物語と彼らを取り巻く社会、という歌の作り方は、これ以降の浜田氏の楽曲の原型になっているようにも思える。
もちろんこれまでの作品にもその方法論は用いられてはいたが、より明確に打ち出すことに成功した作品であると言えるだろう。
「MONEY」「PAIN」に見る普遍的な人間のテーマ
本作は10代の少年たちの物語ではあるが、浜田氏の俯瞰した視点が作品に深みを増していると書いた。
たとえば「DADDY’S TOWN」「A THOUSAND NIGHTS」などは、まさにアルバムの世界観を体現するためのピースと言う印象が強い。
一方で作品の世界観をより広げることに貢献している楽曲が「MONEY」「PAIN」であると考えている。両者に共通するのは、単に10代の少年の物語に閉じていない、普遍的なテーマを描いている点だ。
「MONEY」はお金をめぐる歪んだ社会構造を鋭く描き、「PAIN」では喪失という心理的プロセスを的確に描くことに成功している。
こうした楽曲は本作のメインテーマからはやや逸脱するものであるが、いずれも楽曲単体のテーマが明確で、クオリティが非常に高い。
アルバム全体のバランスを考えても、少年の物語をテーマにした曲ばかりでは似たり寄ったりになってしまう。
「MONEY」「PAIN」など、独自のテーマを持ちつつ、本作のコンセプトとリンクする楽曲が、実は本作の肝になっているように思える。
さらには本作の制作を通じて、「MONEY」「PAIN」など社会構造や人間の心理を込めた楽曲の方法論がより明確になった感がある。
その方向性をさらに広げたのが、次作『J.BOY』であり、本作以上のヒットを飛ばしたところを見ると、本作は『J.BOY』の習作と見ることもできるかもしれない。
自分たちで作り上げた最初のアルバム
作品概要の項でも書いた通り、本作は初の浜田省吾セルフプロデュース、またツアーメンバーによる編曲・演奏による初のアルバムである。
これまでの浜田氏の作品はスタジオミュージシャンが演奏し、ツアーバンドはコピーをして演奏するという形だったようだ。
本作に至るまで、かなりの数のコンサートをツアーバンドと演奏し、結束も強くなっていたタイミングだったのだろう。
コンサートを見据えつつ、熱量の高い演奏を音源に込める、という意味で本作のサウンドの力強さ・勢いを感じることができるのではないだろうか。
そして本来は70年代のうちにやりたかったというテーマを、ようやく十分に実現できる体制が整った、ということで浜田氏の思いも強い作品だったことだと思う。
かつてやり残したことを、ツアーをともにしてきた仲間たちと作り上げる、という制作面での熱量が本作のクオリティを押し上げているように筆者には思える。
手探りだった面もあったそうだが、メンバーもまだ30代前半で、それを乗り越えるパワーが漲っているようにも思われ、そんな浜田省吾を中心としたプロジェクトのフレッシュな熱量も感じるところだ。
<『DOWN BY THE MAINSTREET』と近い時期に作られたアルバム>
・バラードアルバム『Sand Castle』(1983)
リアレンジによるバラード集の第1弾、佐藤準による美しいアレンジが秀逸な作品。
・浜田省吾 & THE FUSE『CLUB SURF&SNOWBOUND』(1987)
バンドメンバーとともに作り上げたサマー・ウィンターソングを収録した企画アルバム。
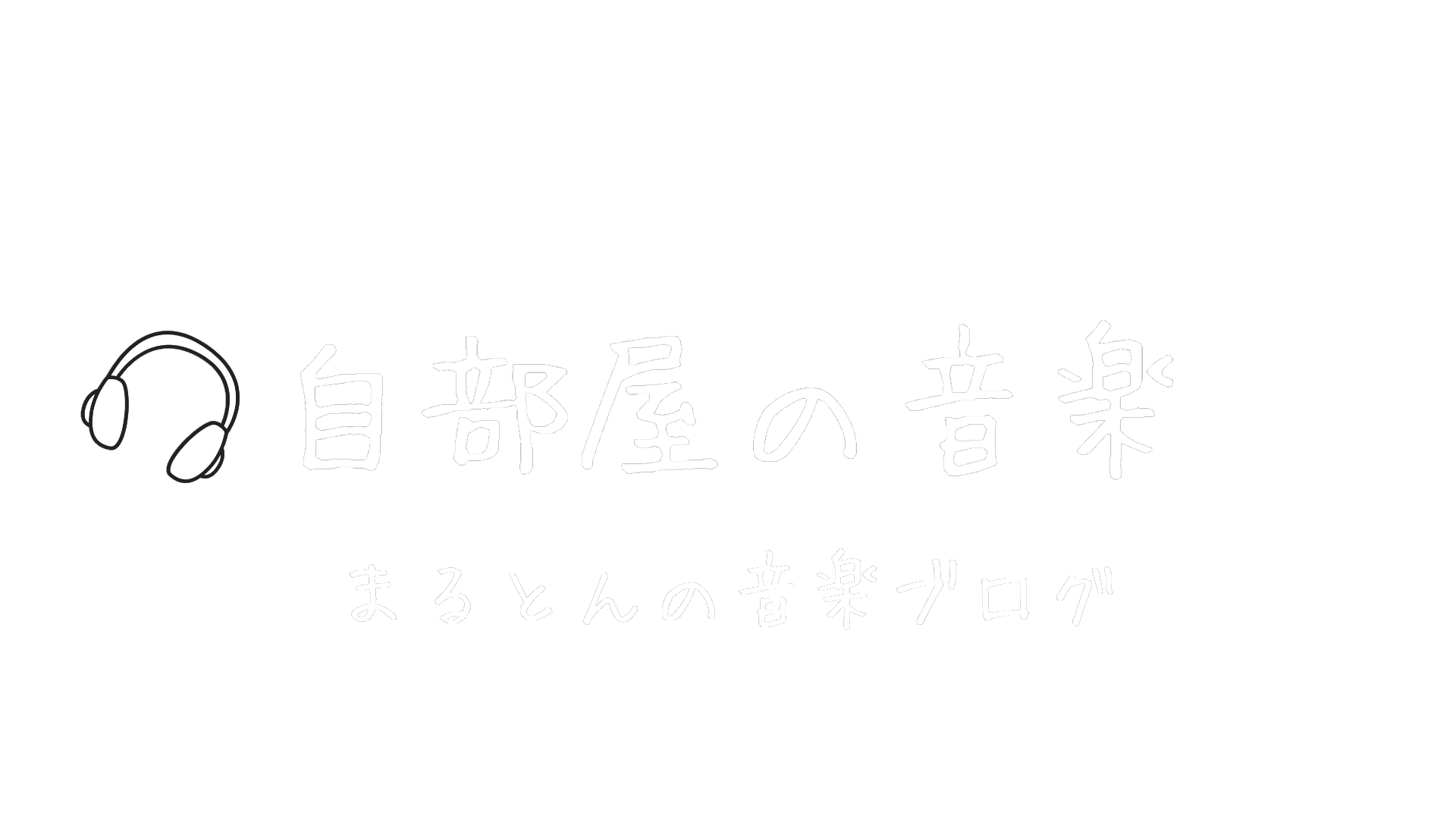






















コメント