いよいよ来年はメンバー全員が還暦を迎えるハードロックバンド人間椅子は、ヘヴィなサウンドと怪奇や幻想をテーマにした作風で知られている。
2025年11月19日リリースの24th『まほろば』はヘヴィさは保ちつつも、怪奇的な要素は後退し、優しさや柔らかさも感じさせる作風で、近年はそうした傾向が強まっている。
怪奇性、すなわち楽曲に漂う不気味さが近年減っていると感じるのは、単に『まほろば』のようなコンセプトの変化だけにとどまらない。
怪奇性の減少において重要な要因となっているのは、”歌の比重”の変化があるのではないか、と考えた。
実は曲の中で歌がどれだけ出てくるのか、という点に着目してみると、これが人間椅子の不気味さを作り出していた大きな要因だったのでは、と気付く。
今回は人間椅子の楽曲における怪奇性について、歌の比重が変化している点に着目して考察した記事である。
人間椅子の怪奇性を作り出していた”歌の比重”という正体
人間椅子の怪奇性を作り出しているものは何か、とはなかなか一言では説明できないものである。不気味なリフや展開、文学的な歌詞や歌い方に至るまであらゆる要素を含んでいる。
今回その中でも、実は重要な要素だったのではないか、と思うのが「歌の比重」である。
楽曲全体の中で、歌がどれくらいの時間を占めるのか、あるいはどれくらいの重要度を持つか、が「歌の比重」である。
歌は音楽に詳しくない人でも、楽曲の中で最も聴き取りやすいものであり、歌とメロディの良さが楽曲の良さを大きく決めることには違いない。
ポピュラー音楽やロックにおいても、歌が前面に出ているものこそ、「親しみやすい」ものだ。
その逆に歌があまり出て来ない、あるいはどこに出てくるのか分からない、というのは「親しみにくい」ものであり、場合によっては倒錯しており、不気味とさえ思えてくる。
こうした歌の少なさにより怪奇性を高める方法論が用いられた最初の作品は、1992年の3rd『黄金の夜明け』であると考える。
本作は大作主義・プログレ風味などと評され、人間椅子初期において怪奇的で高度に構築された楽曲が並ぶ名盤と言われることが多い。
収録された楽曲には、歌のない演奏部分がかなり長く続く曲が多い、というのが特徴である。それがプログレ的とも言えるが、人間椅子の場合は怪しさを醸し出すのに成功している。
具体的にはアルバム後半の「マンドラゴラの花」「無言電話」「狂気山脈」などに顕著であり、中間部や終盤に長いギターソロが挿入されている。
また「マンドラゴラの花」や「狂気山脈」は歌が戻って来ないで、演奏の終わっていく、というのもポップスなどではあり得ない展開で、迷子になったような不穏さを表現できる。
そして歌の中にメッセージや詳細な情景描写を入れ込むことなく、演奏だけで怪奇的な雰囲気を作り出す、というのもこの時代の人間椅子の特徴であった。
こうした「歌の比重」が少ないことで怪奇的な雰囲気を醸し出す楽曲は、人間椅子中期頃までは受け継がれていった。
たとえば「踊る一寸法師」「ダンウィッチの怪」「芋虫」などは、『黄金の夜明け』での方法論を用いたものであり、人間椅子の怪奇的な曲の代表格とも言えるだろう。
これらの楽曲に共通するのは、長い中間部が挿入されており、歌の登場する箇所は楽曲全体の中で少ないことである。他にも「人間失格」「屋根裏のねぷた祭り」などが該当する。
また中間部の後に、前半の歌メロが戻ってくるのではなく、展開したままエンディングを迎える、という先の見えない緊張感もまた共通した特徴である。
長いアウトロもまた不気味さをもたらすもので、「時間を止めた男」「ED75」や、読経で終わって行く「胎内巡り」なども不気味な感じを思わせる。
”歌の比重”の変化をもたらしたターニングポイントとは?
一方でその後の人間椅子は、「歌の比重」が増したことで、こうした怪奇的な楽曲が減少した、という歴史があるように思う。
近年の人間椅子はシンプル・ストレートになった、とも言われている。これが「歌の比重」が増した、と言い換えられるのではないかと思っている。
いたずらに長い演奏部分はなくなり、歌を中心に据えて、イントロ・中間部・アウトロを最小限に配置する傾向が近年ほど強まっている印象がある。
「歌の比重」が小さいことで怪奇性を醸し出していたアルバムは、2000年の9th『怪人二十面相』頃までだと思っている。
それ以降は、徐々にシンプルな楽曲構成とともに、歌の比重が増していく歴史ではないかと考えた。とりわけ重要な転換点を3つ取り上げて、その歴史を振り返りたいと思う。
10th『見知らぬ世界』での作風の変化
人間椅子の作風、というよりもギター・ボーカルの和嶋慎治氏の作風の変化では、2001年の10th『見知らぬ世界』は大きなターニングポイントであった。
和嶋氏の著書『屈折くん』で書かれた通り、この時期に和嶋氏は離婚を経験し、再び表現者として出直す決心をした時期だったと回想されている。
この時の大きな変化としては、和嶋氏は楽曲を通じてメッセージを発する、というこれまでの人間椅子ではやって来なかった表現方法を行ったことが挙げられる。
別れた妻への感謝を込めた「さよならの向こう側」は顕著だが、統合失調症と思われる少女への応援歌「エデンの少女」、死ぬまで生き抜こうと死神に言わせた「死神の饗宴」などがある。
メッセージを込めた「さよならの向こう側」「エデンの少女」などはかなりポップな作風となったが、ヘヴィな楽曲にも変化が見られているように思える。
ラストを飾る「見知らぬ世界」も表現者としての出発を高らかに宣言したもので、いたずらに展開を構成することなく、ヘヴィながら非常にシンプルな楽曲となった。
明確なメッセージ性と、そぎ落とされたシンプルなサウンドとなり、結果的には「歌の比重」が増したのが『見知らぬ世界』の作風だった。
当時はあまりの方向転換に賛否両論もあったのだが、音楽的には素直になったので、大衆性を獲得する可能性もあったのかもしれない。
ただこうしたシンプル路線に舵を切るには至らず、再び模索と低迷の時代に入って行くのだった。
とは言え、『見知らぬ世界』での方法論は、後の人間椅子の方向性を大きく決めるものだったと、後になって分かるのであった。
ナカジマノブ氏の加入
人間椅子のドラマーの交代も、楽曲の構成を変化させる一因になったように思える。
1993年の4th『羅生門』ではサポートメンバー、1996年の6th『無限の住人』のリリースツアーよりメンバーとなった後藤マスヒロ氏が中期の人間椅子を支えていた。
彼のプレイはプログレッシブロックを感じさせる、手数が多く複雑なドラミングを得意としていた。またアレンジでも大いに貢献していたようで、複雑な構成は彼の功績でもある。
2003年に脱退し、2004年からはドミンゴス等でプレイしていたナカジマノブ氏が加入することとなった。
どちらかと言えば、ロックンロールなど前に転がって行くようなドラムのナカジマ氏は、それまでの人間椅子の音楽性とは随分と異なっていた。
やはり彼のドラムが活きるのは、シンプルな4ビートや8ビートで突き進むような楽曲である。ナカジマ氏が加わった”新生”人間椅子は、楽曲の構成面でも模索の時代が始まった。
2004年の12th『三悪道中膝栗毛』~2007年の14th『真夏の夜の夢』辺りは移行期と言う感じであったが、2009年の15th『未来浪漫派』辺りから方向性が定まり始めた。
『見知らぬ世界』で見せた和嶋氏のメッセージを伝える歌詞が、より明確なものになったと言う要因も加わり、人間椅子の楽曲はよりシンプルなものになって行った。
一方で和嶋氏の中では模索の時代でもあり、「幻色の孤島」「世界に花束を」「春の匂いは涅槃の薫り」などプログレ風味の曲も残していた。
当時、これらの楽曲は「実験的な曲」と紹介されていたが、実はかつての人間椅子にあった「歌の比重」の小さい曲なのだが、徐々にアルバムの中では浮いてくるようになったのだった。
この時代は2011年の16th『此岸礼讃』まで続いたのだった。
この時代の変化を象徴するのが、「どっとはらい」である。中間部にはプログレッシブなフレーズが挿入されているが、かなり短時間でコンパクトにまとまっている。
以前の人間椅子であれば、より複雑な展開にするところを、ヘヴィなリフとズンズンと進んでいくようなビートを軸とした楽曲にまとめ、シンプルで怪しいサウンドを作り上げた。
『萬燈籠』以降の新たなヘヴィネス路線
もう1つ人間椅子がよりシンプルになった要因として、2013年のOzzfest Japan 2013への出演を契機とする、露出の増加がある。
敬愛するBlack Sabbathと同じステージに立ち、また人間椅子の名前だけしか知らなかった層に、人間椅子の音楽を届けることができた現場となった。
さらなる新規ファンの獲得が見込める大チャンスに、ちょうど新譜リリースが控えていた。2013年の17th『萬燈籠』は新たなファンに訴えかける勝負作となったのだった。
やはり『此岸礼讃』までの”実験的な曲”は影を潜め、より分かりやすく人間椅子の魅力が伝わる楽曲を中心に据えた作品となった。
人間椅子の魅力であるヘヴィなサウンド・リフを主体とした音楽に回帰し、いたずらに長い展開の曲はほとんど見られなくなった。
そして『見知らぬ世界』に端を発し、『未来浪漫派』頃に確立された和嶋氏のメッセージ性のある歌詞もまた中核に据えられたことで、歌も楽曲の主役になった感がある。
これが結果的には大衆性を獲得することに貢献し、再ブレイクをもたらした要因の1つではないか、とも推測している。
一方でポップになるだけでなく、人間椅子が持っていた怪奇性をいかに表現するか、という点は、ダウンチューニングを以前より多用する、という方法に落ち着いたように思われる。
近年の人間椅子がいわゆる”推し曲”にしているものは、圧倒的にダウンチューニングの楽曲が多い。たとえば「なまはげ」「命売ります」「無情のスキャット」などである。
ダウンチューニングは単純に音の低さがヘヴィさをもたらし、加えて弦のテンション感の緩さからくる気だるさなどから、不気味な雰囲気を醸し出しやすいものである。
『黄金の夜明け』は非常に怪奇性の高いアルバムながら、ダウンチューニング曲は「水没都市」の1曲だけなのだ。
また非常にダークな雰囲気の1999年の8th『二十世紀葬送曲』でも、10曲中「少女地獄」「黒い太陽」の2曲しかダウンチューニング曲は含まれていない。
一方で2019年の21st『新青年』以降は、13~14曲のうち6曲程度と半分近くがダウンチューニング曲となっている。
歌の比重を増した分かりやすい楽曲ながら、ダウンチューニング曲を増やすことでダークかつヘヴィな雰囲気を維持することで、人間椅子の新たなヘヴィネス路線が確立され、現在に至っている。
まとめ
今回の記事では、人間椅子の楽曲における怪奇性について、「歌の比重」に着目した考察を行った。
1992年の3rd『黄金の夜明け』よりおよそ始まる、「歌の比重」の小さな楽曲、逆に言えば演奏が長く、展開も複雑な楽曲こそ、初期~中期の人間椅子の怪奇性を支えていた。
この怪奇性とは、プログレッシブロックの雰囲気を持つものであり、歌の少なさやどこに進むか分からない展開が、不安感・緊張感をもたらす意味での怪奇性であった。
これは音楽的に高度なものになりやすく、一般的にはなかなか理解されにくい、マニアックな音楽となりがちである。
案の定、人間椅子は本当に知る人ぞ知る隠れたバンドとして、売り上げ的には低迷する時期を長く経験することとなった。
決して売り上げを伸ばす目的ではなかったが、いくつかの要因で、人間椅子の楽曲の「歌の比重」が増加、シンプルになったことが怪奇性の質を変えることになった。
既に述べた通り、和嶋氏の歌詞の考え方の変化や、ドラマーの交代、そしてOzzfest Japan 2013出演を契機とする再ブレイク期への突入などが組み合わさっている。
かつての難解さを伴った怪奇性は影を潜め、よりシンプルに分かりやすいながらも、ダーク・ヘヴィなサウンドをダウンチューニングの力を借りながら確立するに至った。
人間椅子の持つ怪奇性は保たれながらも、「歌の比重」を変化させたことで、その質は変化した、ということである。
これが「昔と変わったな」と感じさせる大きな要因であるが、一方で「人間椅子は変わらない」と評される部分であろう。
従来の長大で、音楽絵巻のようだった人間椅子の怪奇性が好きだったファンは離れてしまったかもしれないが、やはり歌を軸としたポップな楽曲の方が、圧倒的に付くファンの数は多い。
人間椅子が再ブレイクし、今日まで活動を継続できたのも、こうした作風の変化があったからこそとも言える。
一方で計算してここまで来たと言うよりは、長い歴史の中で紆余曲折、模索をしながらたどり着いた境地であるところが、とても人間椅子らしいと思う。
※【人間椅子】ライブ中盤にダウンチューニング曲が固まっている理由とは?意外な場所に配置されることも
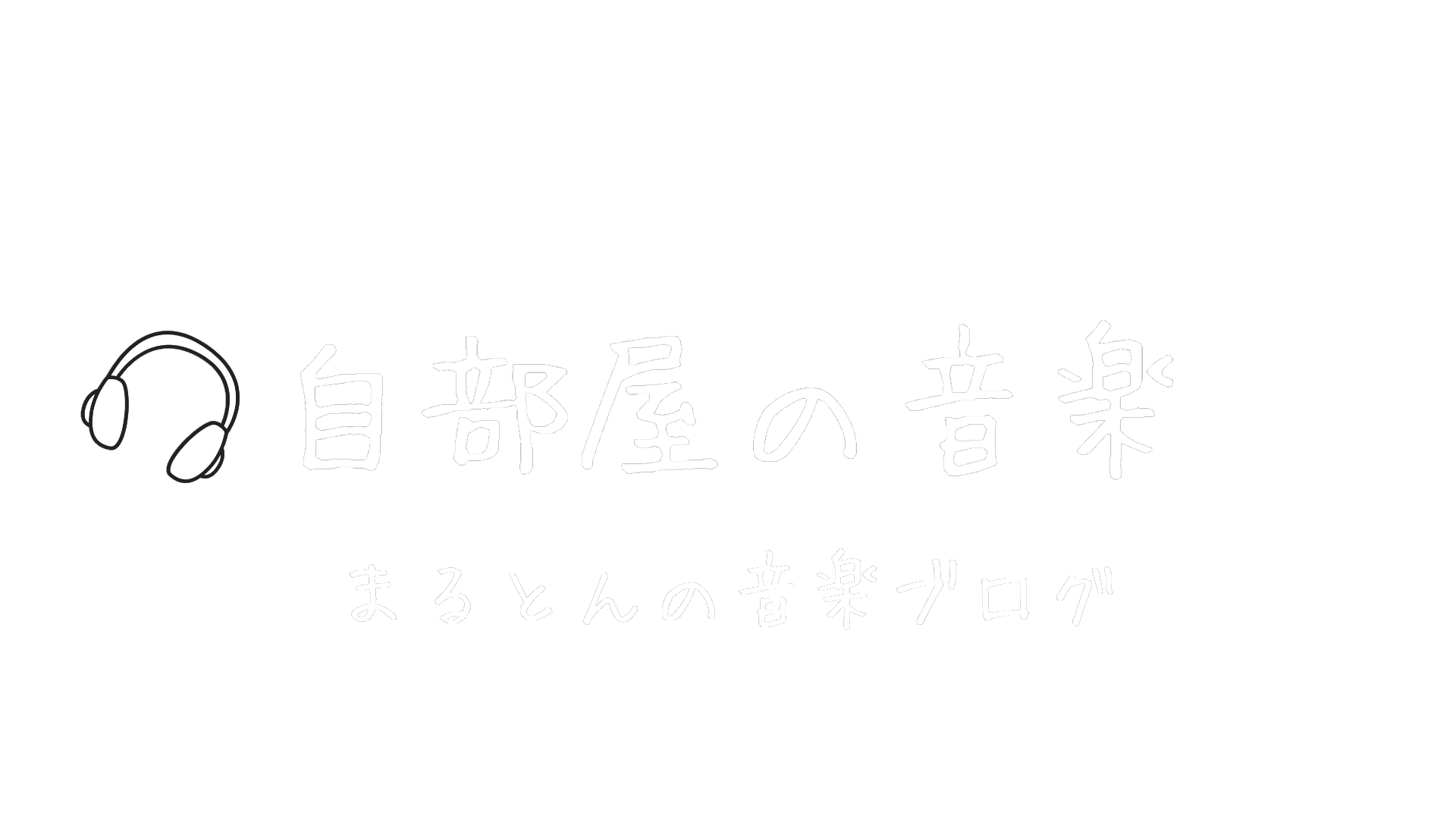






















コメント