デビューからおよそ25年を迎えた、妖怪ヘヴィメタルバンド陰陽座が、約2年半ぶりのアルバム『吟澪御前』をリリースした。
2020年にはボーカルの黒猫氏の突発性難聴に伴う休止期間を経て、2022年に『龍凰童子』のリリース、ツアー活動も再開に至っている。
前作『龍凰童子』が陰陽座そのものを表すタイトルであったが、本作もまた陰陽座そのものを表し、陰陽座であることを宣言するようなタイトルと言う意味では、連続性を持つものだ。
しかし内容面では『龍凰童子』とはまた違った一面、さらには次の段階へと進み始めていることを感じさせるアルバムとなっていた。
今回の記事では、陰陽座の16thアルバム『吟澪御前』のレビューを行う内容である。
『吟澪御前』の発売までの陰陽座の動き
アルバム『吟澪御前』の内容に入る前に、前作から本作に至るまで、ごくごく簡単に陰陽座の活動を振り返っておこう。
前作『龍凰童子』は2023年1月18日にリリースされた。龍と鳳凰という2つを纏った鬼と言う意味の、陰陽座を体現した前作は、これまでの陰陽座の総決算的な内容の作品と言う印象だった。
※【アルバムレビュー】陰陽座 – 龍凰童子(2023)近年の陰陽座らしさを詰め込んだ総集編的アルバム
冒頭にも書いた通り、黒猫氏の療養期間(それはコロナの時期とも重なった)は主だった活動はなかったが、2023年よりツアー活動も再開となる。
アルバムリリースツアーに先駆けて、4月に陰陽座特別公演2023『捲土重来』が3公演行われた。個々で披露された曲目は、初期の楽曲を中心に、ノーマルチューニングの楽曲のみで構成された。
7月から10月にかけ、アルバムリリースを記念して陰陽座ツアー2023『鬼神に横道なきものを』7公演が行われている。
2024年は、まず2019年に中断してしまった『生きることと見つけたり【参】』の鹿児島・宮崎公演を実施し、10月に陰陽座ツアー2024『神無き月に式の存る也』5公演を行っている。
ツアー本数はかつてより少なめにしているのは黒猫氏の体調も考慮してのことだろうか。しかし着実に陰陽座の活動が戻りつつある中での本作『吟澪御前』リリースとなった。
16thアルバム『吟澪御前』レビュー
本題の16thアルバム『吟澪御前』のレビューを行う。
前半では作品の概要とアルバム全体の印象を書いている。後半では全楽曲について短く感想を述べた。
なお歌詞の読み解きや世界観については、筆者より詳しい人も多く、またベース・ボーカル瞬火氏による全曲解説記事もある。
主にサウンドやメロディなど、音楽的な観点からのレビューとなっている。
作品概要とアルバムの最初の印象
- 発売日:2025年8月6日
- レーベル:キングレコード
- 収録時間(楽曲数):53:00(全12曲)
- 全作詞・作曲:瞬火
- 初回限定特典:特製スリーブケース/カラー・フォトブックレット
『吟澪御前』は陰陽座の16枚目のフルアルバムである。タイトルの意味は、「歌や音楽を吟ずること自体を己の澪として自分の生き様とする」であると瞬火氏が語っている。
”御前”が強力な女性の鬼に対する言葉であり、前作の”童子”が強力な男性の鬼を表す言葉であり、タイトルの上では対になる作品である。
前作のジャケットは特殊メイクを施した黒猫氏の写真であったが、本作はステージ上の黒猫氏そのものであり、より黒猫氏(や彼女の歌唱)に焦点を当てた作品であることが窺える。
内容的に前作との関連性がある訳ではないものの、連続する作品として、前作との比較もしながらアルバムを聴いた最初の印象について述べておこう。
まずは15曲70分超えの超大作だった前作に比べると、12曲53分と比較的コンパクトにまとまった作品であると言う印象である。
前作は制作期間も長かったようであり、多数の楽曲から選曲されたアルバムであったと瞬火氏が語っていたように、曲数も多かった。
本作はアルバムタイトルが目指す方向で書き下ろされた楽曲がほとんど(「誰がために釡は鳴る」はストックだったらしい)であり、制作の流れも少し異なったようだ。
音楽的に見ても、前作はかなりバラエティ豊かな作風に思えたが、本作はどちらかと言うと、ソリッドで、ヘヴィメタルに収束するような印象を持った。
ソリッドな方向で思い出すのは、前々作の『覇道明王』(2018)であるが、それに比べると、ゴリゴリのメタルと言うよりも、歌が前面に出たキャッチーさのようなものを感じた。
また本作では、政治思想的なものは含めないとしつつ、世界の行方を憂うようなテーマが随所に散りばめられており、ややメッセージ性の強い作品になっている。
物語を構築するタイプの楽曲が多かったのが、今回は社会に開かれた作品になっている点が、これまでと異なる肌触りになっているのかもしれない。

『吟澪御前』全曲レビュー
ここからはアルバム『吟澪御前』の全曲について、簡単に感想などを述べることにする。
なお各楽曲のテーマや、歌詞の内容などについては、作詞・作曲した瞬火氏による解説に既に詳しく書かれている。
そのため、音楽的な面での発見や興味深い点などを中心に書くことにした。また使用されていると思われる楽器のチューニングについても書いている。
※瞬火氏のブログ『まったり徒然草』 – アルバム『吟澪御前』全楽曲解説
吟澪に死す
・7弦楽器(Bm→Em)
アルバムの冒頭を飾る曲は、最も陰陽座の王道とも言える曲調の楽曲である。今回は序曲のような形を取っていない。
アルバムの楽曲制作で最初にできた楽曲と言うことで、本作を象徴する1曲と言って良いだろう。7弦楽器を用いて、7弦の響きを活かしたAメロから、サビでEmに転調している。
やはりEmの響きは、初期からの陰陽座を思わせるもので、安心感がある。非常にストレートで、展開もシンプルであり、メロディの良さや黒猫氏の歌唱の力強さが際立つ楽曲である。
本作では「シンプルにして力強い」と言うのが1つのキーワードかもしれない。
深紅の天穹
・7弦楽器(Bm)
1曲目の「吟澪に死す」と対になるような楽曲ながら、実際にはアルバム制作の最後に生まれた楽曲だと言う。青空が赤く染まる、という終末感を歌ったものだそうだ。
1曲目がハードロックなビートに近いとすれば、こちらはかなりヘヴィメタル色の強いリズムである。そして黒猫氏・瞬火氏の歌うパートが交互にやって来るのは実は珍しいものである。
まるで二人が歌いながら天に昇っていくかのような、疾走感があり高揚感のある楽曲だ。一方で歌うテーマの重さ故、ヘヴィさが伴う曲調に仕上がっている。
曲調としては、『迦陵頻伽』(2016)収録の「愛する者よ、死に候え」などに通じるものがある。
鬼神に横道なきものを
・7弦楽器(Bm)
酒吞童子の最後の言葉からタイトルを取ったもので、2023年に敢行したツアータイトルにも用いられた言葉である。
酒呑童子が騙し討ちによって源頼光に討伐される場面を歌ったもの、ということで、8thアルバム『魑魅魍魎』(2008)に収録の「酒吞童子」と、楽曲の中でも関連がみられる。
オープニングの群衆のようなSE、不気味なリフは7弦で弾かれ、その後のハモりによるギターフレーズは「酒吞童子」の前半部のサビの演奏と似たものになっている。
荒々しい瞬火氏の歌唱部分と、黒猫氏の歌唱はシンフォニックな響きで、その融合が二面性を持つ楽曲である。
誰がために釡は鳴る
・1音半下げチューニング(C#m)
この曲だけアルバム制作前より、アイデアとしてあったストック曲のようである。曲のテーマは、釜の鳴る音で祈願が叶うかどうかを占う特殊な神事についてである。
タイトルはヘミングウェイの『誰がために鐘は鳴る』をもじったもので、ちょっとコミカルな曲調である。
リズミカルなビートにヘヴィなリフが心地好い。Aメロ~Bメロはコミカルな雰囲気の歌唱で、サビは突き抜けるようなメジャー音主体の爽やかなメロディである。
「自分の進むべき道は自分で決める」と言うメッセージ性が背後にはあり、サビにはそうした意図がありそうだ。
曲調は『鬼子母神』(2011)収録の「組曲「鬼子母神」〜徨」に通じるところがある。シンプルながらよくまとまった曲で、個人的には本作お気に入りの曲の1つ。
星熊童子
・1音半下げチューニング(C#m)
前作『龍凰童子』には「茨木童子」が収録されたが、「童子(鬼)」のシリーズである。詳しい物語は瞬火氏の解説を読んでもらうとして、ここでは裏切りへの怒りを歌ったものだということ。
そのため、曲調は本作の中でもかなりアグレッシブなものとなっている。いわゆるスラッシュメタルのビートであるが、これを1音半下げとしたのは非常にポイントが高い。
やはり7弦だとヘヴィすぎて、疾走感あるヘヴィさが出せないように思われる。ここは1音半下げにすることで、ちょうど良い疾走感が表現されていると思った。
瞬火氏によるシャウト、黒猫氏の流麗な歌唱という、陰陽座の王道パターンである。後半部分にややメロディアスな流れが組み込まれているところもポイントが高い。
毛倡妓
・7弦楽器(Bm→Em)
なじみの娼妓だと思った男が声を掛けたら、前も後ろも髪の毛の妖怪だったという話がモチーフになった楽曲。無粋な男を諫める女性の独白スタイルで綴られた楽曲である。
7弦にヘヴィなサウンドと、和を思わせるアレンジ、それでいてポップさも際立つ陰陽座の真骨頂の1つである。
この曲もBmからEmへと転調する最近の定番パターンであるが、Em部分が人間としての思い、Bm部分が妖怪としての恐ろしさを表現していて、上手く構成されていると感じた。
黒猫氏の歌唱も、妖怪と人間とを行き交うように、歌い方に違いが見られるのがさすがである。
紫苑忍法帖
・7弦楽器(Em)
陰陽座のデビュー以来続く、忍法帖シリーズの楽曲である。楽曲解説にあるように、”紫苑”の花言葉である、追憶などをテーマにした切なくも疾走感のあるメタルに仕上がっている。
毎度ながら忍法帖シリーズの仕上がりは素晴らしいものがある。1番のAメロでのクリアなギターがカッコいいし、サビの勇壮なメロディも素晴らしいのだった。
2025年9月時点では、Spotifyの再生回数においてアルバムの中で最も再生されているところからも、注目度や評価の高さが窺えるところである。
なお忍法帖シリーズのルールは、Amのキー(ノーマルチューニング)としており、今回は7弦におけるEmとしているので、ルール通りということなのだろう。
個人的にはこの曲のアウトロ部分のリフが、ベタではあるが、本作で1番好きなフレーズである。
地獄
・1音下げチューニング(Dm)?
本作唯一のバラード曲であるが、そのテーマはかなり重いものである。陰陽座の世界観的には、仏教世界の地獄かと思いきや、この世の地獄ともいえる、実際の事件がモチーフになっている。
瞬火氏ご本人が伏せているので、事件名までは控えたいところだが、北海道で起きたいじめに関する事件が思い起こされる。歌詞にある「雪」という天候、「将来」というワードが生々しい。
アコースティックなアレンジで、ギターの音が深々と降る雪の質感を表しているようにも思える。黒猫氏の歌唱は、鎮魂のようであり、涙なしでは聴けない曲だ。
「深紅の天穹」もそうであるが、かなり現代社会と接点を感じさせる作品であるのが特徴で、本作が今まさにリリースされる意義があるというものである。
鈴鹿御前 -鬼式
・7弦楽器(Bm→Em)
「地獄」で現代社会との接点を感じさせた後、ここから”鈴鹿御前三部作”である楽曲絵巻が始まる。組曲形式は取っていないが、実質的には3曲続きの物語である。
この「鈴鹿御前 -鬼式」は、鬼女としての力を人間のために使う神女へと転身する鈴鹿御前の覚悟を描いたものである。
シンフォニックなヘヴィメタルに仕上がっており、ここでもBmからEmへの転調が使われている。どうやら鬼女サイドがBm、神女サイドがEmに対応しているかのようである。
そのためギターソロもBmからEmへと転調するように作られており、非常に作りこみの細かさが垣間見える。
大嶽丸
・7弦楽器(Bm→Em)
田村丸と鈴鹿御前に倒された鬼である大嶽丸をめぐる物語の歌である。詳細は瞬火氏の解説に譲るが、大嶽丸と鈴鹿御前の間をめぐる心理や駆け引きなどが描かれている。
冒頭は7弦のヘヴィなリフから始まり、ボーカルを男女交互にすることで、大嶽丸と鈴鹿御前の物語であることが表現されている。
サビの瞬火氏の歌唱が素晴らしい。そしてシャウト部分からの黒猫氏の歌唱、またそのバッキングのアレンジも美しく、見事な展開である。
単純に比較はできないが、かつての「組曲「義経」〜夢魔炎上」「道成寺蛇ノ獄」くらいの時間をかけて表現するものを、6分ほどで構築し切った今回のアレンジの凄さを感じる。
鈴鹿御前 -神式
・1音半下げチューニング(C#m)
”鈴鹿御前三部作”を締めくくる超力作である。詳しい解説は瞬火氏に譲るとして、鈴鹿御前が25年の生涯を終えるまでの怒涛の人生や最期を描いた楽曲となっている。
前半部分はテクニカルメタル、ミクスチャーメタルのような現代的なビートが斬新である。サビの「六根清浄」というフレーズが頭に残る。
この曲の聴きどころは、ギターソロ後の黒猫氏の歌唱、そしてシンプルなヘヴィメタルのリズムに変わる後半の展開であろう。前半部分があるからこそ、後半部への展開が熱いものにある。
「大嶽丸」と同様、物凄い情報量を疲れさせることなく、いたってシンプルに6分ほどの曲にまとめているのが舌を巻くところである。
三千世界の鴉を殺し
・ノーマルチューニング(Em)
毎回ラストはコミカル、ポップな楽曲が配置される陰陽座である。本作では高杉晋作が詠んだとされる都々逸「三千世界の鴉を殺し、 主と朝寝がしてみたい」を元にした楽曲とのこと。
かなり久しぶりのノーマルチューニング曲である。そしてウネウネと動くベース、サビのシンコペーション三昧のリズムなど、いわゆる平成アニソンや邦ロック感が一気に漂ってくる。
高杉晋作の歌のような世界が来ることを願うところに、本作がやはり現代社会との接点をしっかり持っているところを感じさせる。
それにしても個人的にはやっぱり陰陽座はノーマルチューニングが似合うと思う。この疾走感やロックンロールな感じこそ、陰陽座の良さのようにも思えてしまう。
そしてラストの黒猫氏の「ならんもんかいな」の可愛さが全てをかっさらうのであった。
まとめと総評
ここまで陰陽座の16thアルバム『吟澪御前』の印象、全曲レビューを行った。もう少し作品を聴き込んだ段階で、この”まとめと総評”を書いた。
本作の特徴として、これまで以上に現代社会との接点を持ったテーマ性の重さを持ちながら、説明的にならないよう、コンパクトにまとめた楽曲群であった、という点がある。
そうした現代を生きる私たちにとってリアルな感覚を込めながら、陰陽座流の物語性やサウンドで仕立て上げ、そして背景知識や物語を知らずとも楽しめる楽曲に仕上がっている点で素晴らしい。
今までの作品でもそうした実践を積み重ねてきたバンドではあるが、より洗練されたものとしてアウトプットに成功している作品に思えた。
ここから楽曲、テーマ性、そしてサウンドや楽曲制作の3点について述べることにする。
コンパクトにまとまった粒ぞろいの楽曲
今回のアルバムにおいて、第一印象として大作がなくコンパクトにまとまった楽曲が中心であることを述べた。
長くても6分ほどで、一聴した感覚ではスピーディーに駆け抜けていくものだった。しかし細かく楽曲の展開などに工夫がみられ、十分な情報量でシンプル過ぎると言う印象はない。
また前作が音楽的には広い印象にあったが、本作はストレートなヘヴィメタルが多く、その意味では焦点を絞ったものになっている。
ただ楽曲それぞれを見ていくと、陰陽座らしい展開の妙や、作りこまれた物語性など、これまでの陰陽座の持っていた大作の要素は失われていない。
「鈴鹿御前 -神式」など物語的にはかなりボリュームのあるものであろうが、これまでの陰陽座と異なり、6分ほどにまとめ上げ、楽曲の中での情報量・展開に込めているのが実に凄い。
これまでの陰陽座であれば、もっとたくさん尺を使って、たっぷりと展開させたのだろう。
しかし今回はあまり説明的な作品にせず、曲や歌を聴くだけで伝わるものを目指したのではないかと思う。それ故にタイトルも”吟澪”となっているのだろう。
つまりそれは陰陽座が初期から持っていたキャッチーさであり、それと近年のヘヴィなサウンドや綿密な物語性や構築力の精度を高めて、キャッチーさを失うことなく両方を実現している。
ヘヴィさを伴った新たな”キャッチー”への移行とも言うべきアルバムが誕生したのである。
現代社会との接点を持つ重厚なテーマ性
コンパクトで粒ぞろいの楽曲という特徴とともに、本作で目立つのが現代社会との接点を持った重厚なテーマ性である。
もちろんこれまでの陰陽座も、伝承や妖怪などをモチーフにしながら、現代に通じる歌詞や世界観を作ってきたバンドである。
ただ本作はその感覚が、もう一段進んだというのか、明確に示されているように思える。
瞬火氏が楽曲解説やインタビュー等で語っている通り、現代社会に漂う終末感をうたわざるを得なかった、という事情があるようである。
今回のアルバムでは、そうしたリアルタイムな感じが、文学的・物語的な世界観の構築された陰陽座の音楽において、それをより説得力あるものにしているように思えた。
とりわけそうした現代社会を描いたのが「深紅の天穹」「地獄」であり、実は「深紅の天穹」のテーマを別の角度から歌ったのが「三千世界の鴉を殺し」であった。
これらの楽曲が前中後にそれぞれ配置されていることで、アルバムの流れも良くなっているように思える。つまりそれらに挟まれる楽曲にも、こうしたメッセージ性を見つけることができるのだ。
さらには私たちにできるのは、自らの道を進むことと言うメッセージは、陰陽座自身が体現してきたことであり、それゆえ説得力を感じることができるのである。
ダウンチューニングや7弦楽器で構築されるサウンド・構成の行方は?
本作は近年の陰陽座が作ってきたヘヴィなサウンドと、綿密な物語性を持ちながらも、キャッチーさが前面に出た、コンパクトな楽曲で勝負したところが非常に爽快で良いアルバムとなった。
それを踏まえたうえで、近年の陰陽座で用いられているダウンチューニングや7弦楽器を用いた楽曲制作がどうなっていくのだろうか、と思うところを述べてみたい。
陰陽座はずっとノーマルチューニングのみで楽曲制作を行って、2011年の『鬼子母神』で1音下げのダウンチューニングを導入している。
その後、2016年の『迦陵頻伽』では1音半下げのダウンチューニング、さらには7弦楽器を用いることで、楽曲によってチューニングやキーを自在に使い分ける方向に舵を切った。
ダウンチューニングや7弦楽器を用いるのは、もちろんヘヴィな音像を作り上げることに貢献している。
ダウンチューニングと7弦の音もやはり違いがあり、重い曲よりも、逆に速い曲になった時に、そのスピード感のようなものがチューニングによって異なるのが明白である。
さらには7弦楽器を用いることで、7弦を除けばレギュラーチューニングを内包しているため、EmとBmの転調を巧みに用いることとなった。
陰陽座の場合は、場面ごとにキーを変えて、登場人物が入れ替わっていることを表すなど、物語づくりにおいても7弦をうまく利用しているのだった。
このように作りこんだ作品を制作する上では、ダウンチューニングや7弦楽器はポジティブに作用しているようである。
一方で本作では久しぶりにノーマルチューニングの響きが懐かしかった。アルバムラストに配置された「三千世界の鴉を殺し」である。
たとえば2016年の『迦陵頻伽』における「刃」もほぼノーマルチューニングのように聞こえるが、ベースを聴くと7弦の音が入っているのが分かり、やはり肌触りが異なる。
ノーマルチューニングの持つ、このロックンロール感とは何なのだろう。聴いた瞬間に魂が沸き立つような感じ、最近の陰陽座にはやや感じにくかったものが、急に蘇った。
ただ陰陽座はノーマルチューニングを捨てたわけではない。近年のライブセットリストを見ていても、初期のノーマルチューニング時代の楽曲が中核に据えられている。
やはりノーマルチューニングの持つロックンロール感は、ライブにおいて威力を発揮するのだろう。
つまり今でも陰陽座はノーマルチューニングの魔力を信じているようではある。が、アルバム制作とライブと、ここ最近は切り分けて考えていたのかもしれない。
ノーマルチューニング曲の持つ、理屈を飛び越えてやって来る滾りのようなものが、陰陽座との相性がとても良いように思う。
個人的には自在に変化するチューニングの中に、ノーマルチューニング曲の復活を願うところであり、その意味で「三千世界の鴉を殺し」がやはり印象深かったと言わざるを得ない。
今後の陰陽座のサウンド、楽曲制作がどのように展開していくのか、楽しみである。
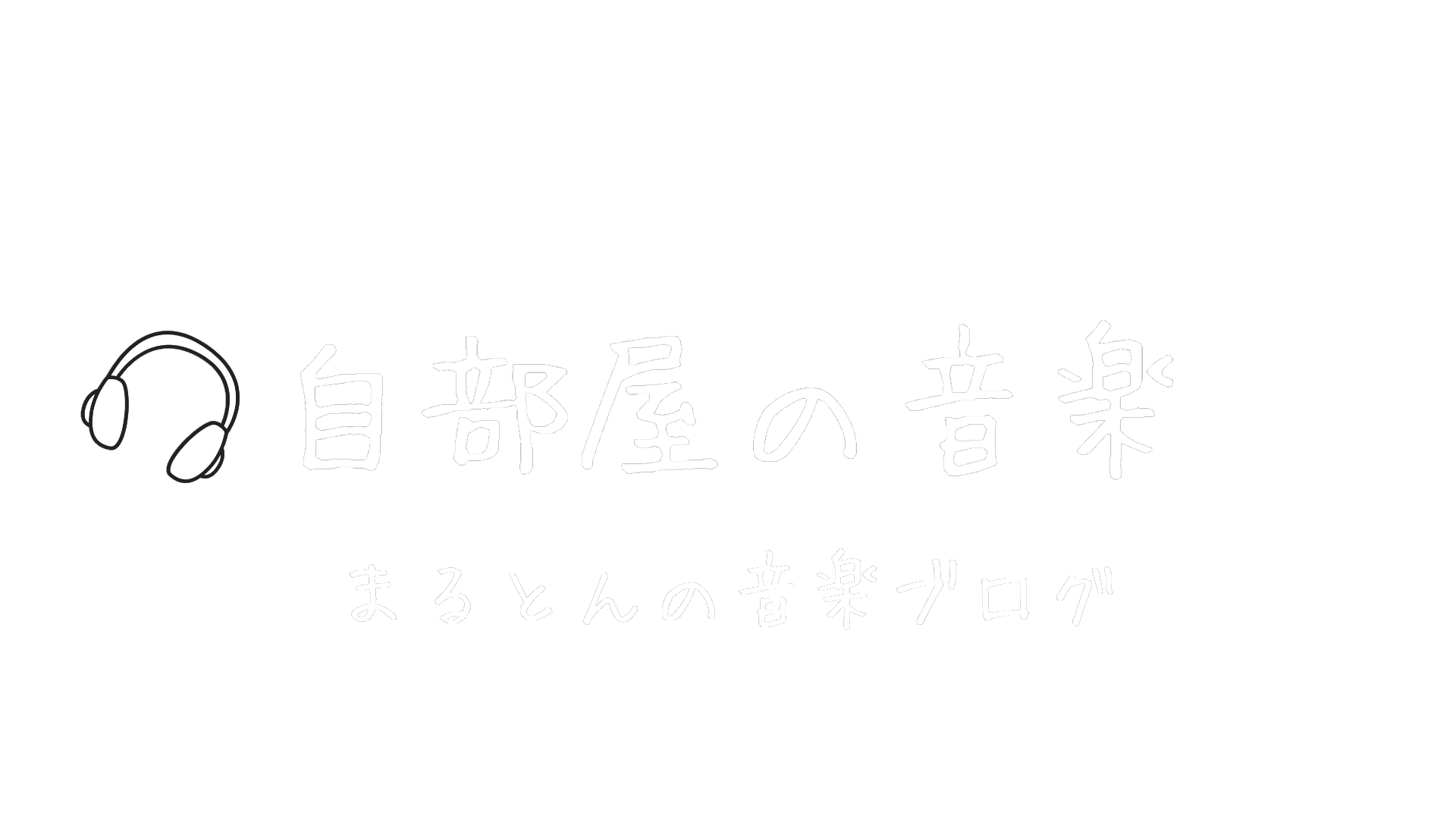






















コメント