1988年にデビューした4人組ロックバンド、エレファントカシマシは、現在実質的な活動休止状態にある。
ボーカルの宮本浩次氏のソロ活動が中心となっていたが、2025年9月28日に建て替え工事前最後の日比谷野外音楽堂での公演を行ったのが話題となった。
しかしその後、ドラムの冨永義之氏が酒気帯び運転による接触事故を起こし、活動休止状態に入っていた。
今は過去の作品を楽しむほかない。今回はエレカシの活動の中でも比較的地味な立ち位置にある、東芝EMI期の後期に焦点をあててみたい。
アルバムとしては『扉』~『町を見下ろす丘』の3枚の時代であり、この時期は初期であるエピックソニー期の雰囲気を再構成したような独特の魅力がある時代だと考えている。
エピックソニー期との共通点や違いなどを考察しながら、東芝EMI後期のエレカシの魅力について書いた記事である。
エレファントカシマシの東芝EMI後期の特徴とは?
今回取り上げてみたいのは、エレファントカシマシが東芝EMIに在籍した、後半の時代の作品である。
エレカシと言えば、レーベルの移籍とともに作風が大きく変わることで知られている。
東芝EMIの前のポニーキャニオン時代と言えば、「今宵の月のように」に代表される、男臭くもポップな作風で、ヒット曲を世に送り出した黄金期の1つである。
1999年に東芝EMIに移籍してからのエレカシは、作風としては振り幅の大きな時代となる。とりわけ1999年から2003年(この時期を前期と呼ぶ)は模索の時代だった。
打ち込みを多用したハードな『good morning』(2000年)を出したかと思えば、『ライフ』(2002年)ではポニーキャニオン期のようなポップな作風に戻った。
2003年の『俺の道』でバンドサウンドに回帰したことで、方向性が大まかには定まることになる。
今回取り上げる2004年~2006年(この時期を後期と呼ぶ)の3枚のアルバム『扉』『風』『町を見下ろす丘』の3作は、前期に比べると、作風は安定したものと言える。
ポニーキャニオン期の、ある種の躍動感や派手さと言ったものが、東芝EMI前期には残っていたが、後期の特徴としてはまず全体的に非常に渋い楽曲並んでいる、ということだ。
バンドメンバーは30代後半から40代に差し掛かり、宮本氏は”中年”を意識していた向きである。中年にとっての等身大のロックとは何か、という模索の様子が窺えるのだ。
そしてそのサウンドや音楽性は、エレカシ初期のエピックソニー期の荒々しさを、もう一度再構成しようという意図も垣間見える。
ストレートでポップなポニーキャニオン期の作風とは反対に、武骨なロックや展開の多い長尺な楽曲が入って来るなど、エピックソニー期を見つめ直したような作風になっている。
このまま枯れていくのか、いやもう一度立ち上がろう、という葛藤の中にあるような歌の世界観が特徴的でもある。そうした苦悩が源泉になっているのも、エピックソニー期に近い。
東芝EMI在籍最後の『町を見下ろす丘』では、ポップな方向性を少しだけ見出し始めており、それが2007年にユニバーサルミュージックに移籍してからの快進撃を予感させる。
筆者としては、エピックソニー期のような武骨さと、ポニーキャニオン期の前向きな作風の間で揺れるような、そして新たな方向を模索しようとする、この時代にとても惹かれるのだ。
東芝EMI後期のアルバム3枚の紹介
東芝EMI後期のエレファントカシマシは、3枚のオリジナルアルバム『扉』『風』『町を見下ろす丘』を発表している。
ここでは3枚のアルバムについて、その特徴・魅力について書いている。
先に述べた通り、この時期はどこかエピックソニー期の作風を再構成しようとする趣がある。過去のどのアルバムとの類似点を見出せるか、なども考察してみた。
14th『扉』
- 発売日:2004年3月31日
前作『俺の道』でバンドサウンドに回帰、そして前作もエピックソニー期に戻ったかのような荒々しいサウンドとロックな楽曲がインパクトのある作品だった。
エピックソニー期回帰という意味では、『俺の道』から既に始まっていたのであり、まるでデビューアルバムのような爆発力を呼び戻そうとしたのかもしれない。
そして次に制作された『扉』は宮本氏の苦悩がダイレクトに伝わって来るかのようなアルバムの印象である。
その苦悩の理由はいくつかありそうである。まずは『俺の道』で従来の爆発力を表出したが、宮本氏は40代間近になっており、より等身大のバンド、ロックとは何かを模索していた。
その様子は、『扉』の制作に迫ったドキュメンタリー映画『扉の向こう』で克明に描かれている。
加えて、前年に信頼していた人物に全財産を持ち逃げされ、高級マンションを引き払い、車や古書なども売り払って、質素な生活になっていた事情もあった。
本人の中でも、何か浮ついた状況が終わり、自身の表現に向き合わなければならないタイミングだったのだろう。
本作を作りにあたり、意識されていたであろうアルバムが1990年の4th『生活』である。『扉の向こう』でも、『生活』の曲を流して、これより下がっていてはダメだ、と語るシーンがある。
『生活』が孤独な若き文学青年の物語であるとすれば、両親など身近な関係の中で生きる(おそらく)文学好きな中年の物語になっているところが、最も共通点と言えるだろう。
自分が肥大化していた若き頃の『生活』に比べれば、その視野は広く、歴史や社会にまで広がっている。たとえば「化ケモノ青年」は日本の歴史を振り返るような内容である。
一方で音楽性と言う意味では、『生活』のような長尺な楽曲(「地元の朝」)はあるが、比較的シンプルな楽曲で構成されている点は異なる。
全体的に暗いトーンで統一されているところ、そして『俺の道』よりも緊迫感のある、ドスの効いた叫びが重みを増して感じられるところだ。
歌詞も『生活』の頃を超えなければという焦燥感のようなものが感じられ、ヒリヒリした感じがある。
ポップなメッセージではなく、「体の全て使い尽くして死にたい」が等身大の言葉なのだろう。
そしてポップなメロディが生み出せたのが「歴史」であった。しかしその曲に森鴎外の生涯を紹介する歌詞をつけたところに、この当時の迷いや模索が垣間見えるところだ。
15th『風』
- 発売日:2004年9月29日
宮本氏の苦悩が色濃く表れた『扉』からわずか半年後にリリースされたのが本作である。制作は同じような時期に行われていたと思われる。
(『扉の向こう』でのレコーディング風景には、『風』に収録さた楽曲も登場していた)
タイトルが漢字一文字である点、黒で統一されたジャケットの『扉』に対して、白でが基調の『風』と、この2枚が対になっているのは明白だろう。
そして全体を貫く雰囲気も対照的である。ダークで重々しかった『扉』に対して、どこか清々しさを感じる、カラっとした曲が多いのが『風』である。
音像も対照的なものだ。『扉』は熊谷昭氏を共同プロデューサーに置きつつも、バンドのみで編曲を行って、ほとんど4人の音だけで構成されたアルバムとなっている。
一方で『風』は久保田光太郎を共同プロデューサーに迎え、編曲にも加わっており、ギターなどで演奏面でもエレカシをサポートすることで、より立体的な音像になっている。
『扉』がまさにエピックソニー期の荒々しさを凝縮したような作風ならば、『風』は早くもそこから脱しようと、次なる模索を試みているアルバムと言うところだ。
本作は『扉』ほど、エピックソニー期とは直接的な関連性を見出すことは難しいかもしれない。強いて挙げれば、長尺の凝った曲が多いところに、エピックソニー後期の作風を見て取れる。
何と1曲目に9分超えの「平成理想主義」が置かれ、たとえば『東京の空』のタイトル曲「東京の空」「暮れゆく夕べの空」のような、長尺でよく構築された作風を思わせる。
人気の高い「友達がいるのさ」も、ポップなメロディは登場しつつも、演奏で盛り上げていくようなロックのマニアックさも感じさせる楽曲となっている。
あまり語られることの多くない本作であるが、後のエレカシにとっては重要なアルバムのようにも思える。
『扉』の重々しさを脱して、新たな方向性を見出しつつある点で、『東京の空』のような位置づけのような作品と見えなくもない。
どこか開き直ったような清々しさは、『東京の空』の時の雰囲気とは異なるものの、この時点での宮本氏の清々しさを感じ取ることがっできるようにも思える。
16th『町を見下ろす丘』
- 発売日:2006年3月29日
東芝EMI期最後のアルバムとなった、ファンから根強い人気のある作品が『町を見下ろす丘』である。
カラスが真ん中にデーンと描かれたちょっと不思議なジャケット、しかしこれぞエレカシと言う、宮本氏が描きたい風景のようなものがしっかりと描かれたアルバムと言う感じがする。
音楽的にエレカシらしいと感じる部分は、男臭さと哀愁とのバランスの絶妙さである。ダークさの『扉』、ドライな『風』の後の本作は、哀愁を感じさせる楽曲が並んでいるように感じる。
言い換えれば、耳馴染みやすいメロディの復活とも言える。「シグナル」「なぜだか、俺は祷ってゐた。」には、ロック路線が続いた東芝EMI期においては、かなりポップな作風だ。
「甘き絶望」「すまねえ魂」辺りも、『扉』『風』の雰囲気をまといつつ、ポップな方向に進みたい模索のような色が窺える。
一方で「地元のダンナ」の激しさや「人生の午後に」のダークな雰囲気など、『扉』の持つヘヴィさも本作では復活しているように思える。
本作の立ち位置としては、ポップな作風に向かいつつあった『ココロに花を』のような感じもする。
『ココロに花を』のポップさと音楽性は異なるが、次に進みたい葛藤のようなものが共通するように感じるのだ。
そしてユニバーサル時代を予感させるポップなメロディ、シンプルな楽曲が見え始めているのが特徴である。
あえてエピックソニー期との共通点を見出すとすれば、エピックソニーからポニーキャニオンに移る前後のざわざわ感のようなものが似ている気がする。
まとめ – 東芝EMI後期の魅力とは?
今回はあまり多く語られることのない、エレファントカシマシの東芝EMI後期の作品やその魅力について書いてきた。
キーになっている作品はやはり2004年の14th『扉』ではないか、と思う。『俺の道』でバンドサウンドに回帰した後、果たしてバンドとしてどこへ向かうのか、その模索が窺える。
そこで1つのきっかけになったのが、自身のエピックソニー期の作風だったのかもしれない。荒々しくも純度の高い音楽をやっていたあの頃、自分自身を取り戻すような作業だったのだろうか。
しかし現前には『生活』の頃の若き文学青年ではなく、中年に差し掛かった主人公が存在していたのだった。
そんな苦悩がダイレクトに表現された『扉』、一方で同時期に作られた『風』は、どこかそんな重苦しさから突き抜けたようなカラッとした雰囲気も感じられる。
エレカシの初期から東芝EMIの最初に至るまでは、文字通りスクラップアンドビルドで、暴力的に自らの音楽性をぶち壊して前に進んできた。
しかし東芝EMI後期からユニバーサル期への橋渡しとなるこの頃、破壊的に変えていくのではなく、自らを統合していく作業をしていたのかもしれない。
ダークさもカラッとした作風も、哀愁を感じさせるメロディも、全て自分たちの音楽なのだ、と『扉』『風』『町を見下ろす丘』は語っているようにも思える。
そして再びストレートな作風へと、戻って行く過程にあり、2007年にユニバーサルに移籍してからの快進撃は語らずとも、多くのファンが知るところであろう。
東芝EMI後期の魅力とは、ユニバーサルへ向けて変化の途上にあり、そこにエピックソニー期を振り返っていた点が1つにある。
そしてエピックソニー期を再構成しながらも、ポニーキャニオン期や東芝EMI前期も含め、あらゆる時代を統合し始めていた時代だったようにも思える。
その結果として、ユニバーサル期にはポップなメロディを軸に置きながらも、様々の時代のエレカシが顔を出す、バラエティ豊かな音楽性が花開いたのだと思う。
ユニバーサル期の準備期間としての魅力、そしてそれにとどまらず、エレカシが変化していく面白い時代なのだと感じている。
※エレファントカシマシと”暴力”について – 宮本浩次によるスクラップアンドビルドの魅力とは?
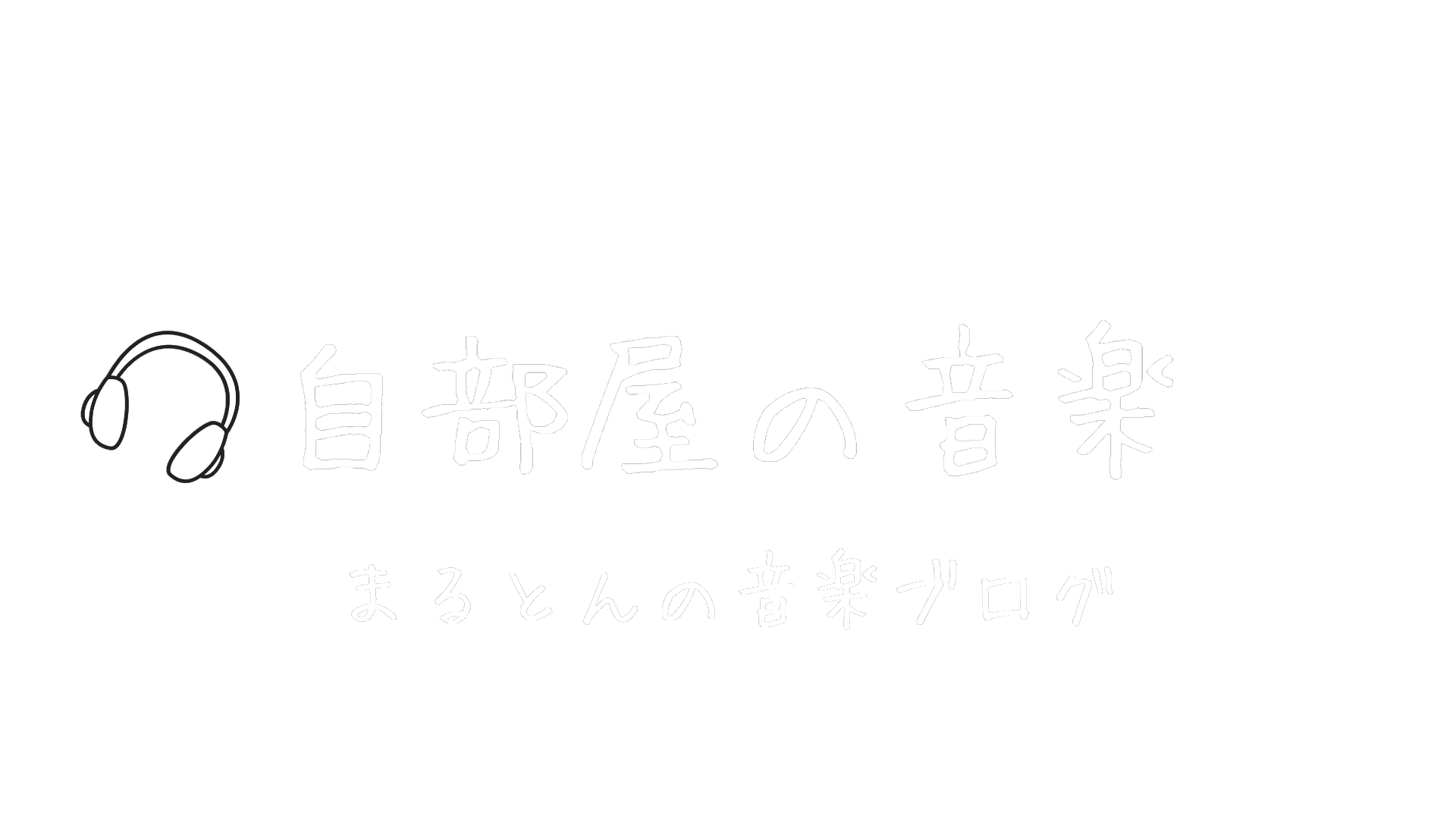





















コメント