2026年でデビューから45周年を迎えるシンガーソングライター・プロデューサーの角松敏生は、近年になってアルバム制作に精力的である。
一時は新作を制作することに対して消極的な時期もあったようであるが、2022年以降は毎年リリースを行っている。
そして「Contemporary Urban Music (C.U.M)シリーズ」と題した新たな作品群を生み出している。ある意味で、角松氏の原点回帰とも言える夏・都会的なサウンドが楽しめる。
中でもとうとう角松サウンドの完全復活を遂げた、と筆者が感じているのが、2025年リリースの『Forgotten Shores』である。
長らく王道のポップス・AOR路線の作品を封印していた角松氏だが、ようやくここに戻ってきた、と感慨深い作品だった。
今回は2025年発売の角松敏生氏の『Forgotten Shores』についてレビューを行った。
角松敏生『Forgotten Shores』の概要
- 発売日:2025年4月30日(水)
- 発売元:Ariola
<収録楽曲>
| No. | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | Blue Swell | 4:40 |
| 2. | Step out | 4:52 |
| 3. | Beach Road | 5:11 |
| 4. | Domino City | 4:23 |
| 5. | Slave of Media | 4:00 |
| 6. | Forgotten shores | 5:11 |
| 7. | TSUYUAKE | 5:26 |
| 8. | You can see the lights | 3:58 |
| 合計時間 | 37:43 |
『Forgotten Shores』は2025年4月30日にリリースされた、角松敏生氏によるアルバムである。
本作は”Contemporary Urban Music (C.U.M)シリーズ”の第3弾として位置づけられる作品である。
Contemporary Urban Musicは「都市生活者による都市生活者のための音楽」を意味するようだ。
「1970~80年代のフレーバーを纏った楽曲を、熟練のミュージシャンたちと若手の才能を融合させ、最新の技術と手法で練り上げた作品」とのことである。
角松敏生氏と言えば、1981年にデビューし、日本ではシティポップやAORなどと呼ばれるジャンルの流行していた時代に、より洗練された音楽で脚光を浴びた。
近年は海外において日本のシティポップ再評価の機運が、2010年代終わりから2020年の初めにかけて起こっていた。
しかし角松氏としては自身の音楽について、AORやシティポップと言うジャンルの中に一括りにされることを快く思ってはいなかったようである。
角松氏がシティポップ再評価の真っただ中の時期を過ぎてから、Contemporary Urban Musicと銘打ったのも、どこかそうした一括りにされることへの抵抗があったように思える。
前置きが長くなったが、Contemporary Urban Musicを謳い始めてからの角松氏のリリースは、水を得た魚のように精力的だった。
第1弾の『MAGIC HOUR 〜Lovers at Dusk〜』が2024年5月15日発売、そして第2弾のインスト作品『Tiny Scandal』は同年12月11日と、7か月弱でのリリースとなった。
言ってしまえば、初期の頃から続けている音楽性の、ブラッシュアップされたもの、ということだと思っている。”最後のリスタート”と謳っているのも、そういうことなのだろう。
歌モノとしては都会的なサウンドの『MAGIC HOUR 〜Lovers at Dusk〜』に対し、本作『Forgotten Shores』は角松氏のもう1つの代名詞である、夏向けアーバンポップスだ。
ただ楽曲の中には、ディズニーバラード的な楽曲やフュージョン歌謡とも言える楽曲が含まれており、近年の角松氏の趣味も込められた、やはり最新作という感じに仕上がっている。
角松氏自身によるセルフライナーノーツによれば、テーマは、「毒にも薬にもならない」「しかし、なんとなく聴くと高揚する」「聴き終わった後に何かが心に残っているのでもう一回最初から聴き直してみたくなる」だと言う。
(C.U.M)シリーズ以前の角松氏は、コンセプトや仕掛けが明確な作品が多くなっていたが、本作はとにかく”聴いて心地好い”作品を目指している点で、原点回帰的な作品と言うことだろう。

アルバムの印象+全曲ミニレビュー
ここでは角松敏生氏による『Forgotten Shores』のアルバムを聴いた印象と、全曲ミニレビューを行う。
まずアルバムの印象であるが、それより先にContemporary Urban Music (C.U.M)シリーズが始まった時のことが印象に残っている。
それまでの角松氏は、音楽ライブ、演劇、ダンスを融合させた新たな総合エンターテイメント「MILAD (MUSICLIVE, ACT & DANCE)」に力を入れていた。
角松氏は自身名義の制作において、1つのプロジェクトにのめり込むと、それに集中するタイプである。個人的には、純粋な音楽作品を待っていたので、「とうとう来たか」と言う感じだった。
第1弾である『MAGIC HOUR 〜Lovers at Dusk〜』は、まだ”MILAD”っぽい雰囲気を色濃く残す作品と言うのが第一印象だった。
古い話ながら、2002年に日本の伝統楽器を大胆に用いた『INCARNATIO』の後、80年代初頭の「海・夏・空港モノ」のコンセプトで『Summer 4 Rhythm』が作られたのと似ている。
つまり原点回帰的なコンセプトの『Summer 4 Rhythm』でありつつ、アルバムの中には『INCARNATIO』的なサウンドも組み込まれていたのである。
こうした過渡期の雰囲気が『MAGIC HOUR 〜Lovers at Dusk〜』にはあったが、『Forgotten Shores』はより原点回帰になっており、純粋な音楽作品の色合いがむしろ強くなった。
そして音楽性やコンセプト云々と言う理屈を全く抜きにしても、ただ心地好い音楽作品として楽しめるところまで、かなり戻ってきた感のある作品である。
それでは各曲のミニレビューに移りたい。
Blue Swell
まずは1曲目の「Blue Swell」、イントロが始まった瞬間に夏の海が広がるサウンドは、さすがの一言である。そしてこれぞ角松サウンドと呼べる音が耳に飛び込んでくる。
ライナーノーツによれば、山本真央樹氏のドラムと森俊之氏のフェンダーローズ、山内薫氏のベース、角松氏のギターと言う非常にシンプルな編成をベーストラックにしているようだ。
ここにホーンセクションが加わることで、一気にゴージャスさが増すのである。サビの部分で若干コーラスの厚みがあるが、MILADっぽさは随分と薄まっているのを感じる。
まさに1983年の『ON THE CITY SHORE』の頃を思わせる楽曲である。ただサビのリズムはなかなか複雑であり、これは今の角松氏ならではと言える。
今風のシティポップ的なサウンドと言うより、当時の音の作り方で再構築している辺りは、角松氏にしかできないサウンドだ。
Step out
印象的なギターカッティングから導かれる形で始まるこの曲。ミドルテンポで16ビートと来れば、これもまた角松氏がお得意のサウンドである。
Aメロ部分は、2003年の『Summer 4 Rhythm』前後の時期にありそうなコード進行である。一方でサビは、近年のMILADの重厚なコーラスが似合うメロディである。
その点で、どことなく過渡期っぽい曲調のようにも思える。全般に心地好いサウンドを目指したもの、という感じで、ラストのフルートソロはとても良い。
夏っぽさがありつつ、爽やかな風が吹き抜けていくような楽曲である。
Beach Road
こちらも夏っぽい雰囲気が漂う楽曲、ストリングスとホーンセクションが非常にゴージャスなアレンジとなっている。
ご本人も書かれている通り、2012年のリメイクベスト『REBIRTH 1 〜re-make best〜』の「SUMMER EMOTIONS」のアレンジがベースになっているようである。
アレンジは似ているものの、メロディやリズムなどは捻った部分があるのが今の角松氏らしい。たとえば角松氏が敬愛するSteely Danのような、大人っぽさを感じさせる。
これもライナーノーツに書かれているが、本作は角松氏がバッキングギターを務めている(時間とお金の節約とのこと)。左右で異なるバッキングが収められており、なかなか凝っている。
Domino City
ここまで3曲はまさに夏を感じさせる角松敏生であったが、この曲は都会・夜モードの角松氏が楽しめる楽曲である。
80年代初頭のファンクディスコ調を目指したと言うことで、確かに80年代の『ON THE CITY SHORE』~『GOLD DIGGER〜with true love〜』辺りの角松氏の雰囲気である。
当時再現し切れなかった音を、ようやく満足のできる形で作れた、という純粋な喜びがサウンドからも感じ取れる。個人的にはシンセサイザーの音が「まさに」と言うサウンドだと感じた。
昔のサウンドを真似たのではあるが、決して古びた感じはしない。むしろ現代にこうしたサウンドの再評価が起きていることもあり、瑞々しさすら感じるのだった。
Slave of Media
「Domino City」に続き、都会的なサウンドのこの曲。フュージョン的なキメが多く、複雑な展開ながらポップなメロディと言うことで、角松氏いわく「フュージョン歌謡」とのこと。
この曲は本作の中でも出色の出来ではないかと個人的には感じた。ドライブ感のあるリズム隊の華麗な演奏、テクニックがなければ絶対に成立しないものである。
複雑な展開やリズム、転調も交えているのに、サビを中心にメロディは非常にポップなものである。
聴こうと思えばどこまでも深く、一方でただ聞いていて心地好いものでなければポップスではないのだ。その塩梅が絶妙であり、角松氏の最新型として素晴らしい楽曲である。
間奏の本田雅人氏、勝田一樹氏のサックスソロ対決は聴きどころの1つである。また1番終わりのShakatakっぽいピアノソロもとても良い。
Forgotten shores
本作のタイトルトラックであり、アルバムタイトル曲が存在するのは比較的珍しいのである。この曲はまさに”AOR”を感じさせるもの、夏や海と都会的な雰囲気が漂ってくる。
力の抜けた演奏が全体にとても心地好い。アルバムジャケットのイメージがまさにこの曲とリンクする世界観で、誰もいない夏の浜辺の光景が浮かんでくるのだった。
歌詞の世界観はSF的なもので、主人公以外誰もいなくなったら?という物語らしい。個人的に想像したのは、夢か現実か分からないような、実は夢だったと言う話のようにも思えた。
そんな理想や自分の思い出の中の海や浜辺のようであり、どこか異国へ連れ去ってくれる音楽こそ、シティポップやAORが担っていた役割であり、その点ではこの曲はまさにそういう曲だ。
TSUYUAKE
重厚なコーラスとシンガロング的なサビが、少しMILADをやっていた時、あるいはAGHARTAの頃を思い出させるタイプの楽曲である。
ただサウンドを聴いてみると、80年代後半の角松氏の雰囲気でもあり、たとえば「REMEMBER YOU」(1988年の『BEFORE THE DAYLIGHT』収録)などを思い出した。
ダンスミュージックでありながら、跳ね過ぎない土着的なビートが特徴的である。ライナーノーツによれば、The Systemというユニットの楽曲がもとになっているという。
「Soul to Soul」を聴くと、驚くほどに『BEFORE THE DAYLIGHT』のサウンドと似ている。と言うか角松氏が強く影響を受けていたと言うことだろう。
ただこうしたサウンドの尖った部分はなく、やはり「WAになっておどろう」風の土着感が勝っているところが面白い。
You can see the lights
アルバムラストを飾るのは王道のバラード、そしてやはりディズニー映画のプリンセスものの楽曲と言う雰囲気が、ライナーノーツを読まずとも感じられた。
案の定、2014年の『THE MOMENT』でカバーされた「I SEE THE LIGHT 〜輝く未来〜」(『塔の上のラプンツェル』の主題歌)から繋がっているものであった。
角松氏のバラード曲は昔から一貫したものだな、と思うとともに、ディズニー映画の影響を受ける以前から、それに近い色合いがあったことが窺えた。
なおバッキングギターはほぼ角松氏ながら、この曲だけ鈴木英俊氏を起用している。バラードの空間系のクリーンギターのみで起用すると言うのもなかなか贅沢だ。
そして歌詞は高校に進学する娘さんに宛てたもの、2010年の『Citylights Dandy』収録の「See You Again」から娘さんの成長を追いかけているような感覚になった。
全体評価 – 待望の王道ポップス・AOR路線への完全復帰
今回は角松敏生氏の2025年のアルバム『Forgotten Shores』を取り上げてレビューを行った。全体的なレビューを書いてまとめとしたい。
何と言っても筆者が思うのは、待望の王道ポップス・AOR路線への完全復帰作ではないか、ということである。
角松氏と言うと、しばらくの間、王道のポップス路線のアルバムを作って来なかった。
「王道のポップス路線のアルバム」と言うのは、コンセプトなどが緩く、個々の楽曲として楽しめるアルバムと言う意味である。
コンセプト性が強まった作品で言えば、プログレの構成だった2014年『THE MOMENT』から、演劇との融合となった2019年『東京少年少女』の頃である。
そして「MILAD (MUSICLIVE, ACT & DANCE)」の路線となってから、2022年『Inherit The Life』、2023年『Inherit The Life II』とサントラと言う立ち位置の作品が続いた。
『THE MOMENT』前後からMILADの路線になるまでは、作品リリースもかなり期間が空いていた時期もあった。
筆者は角松氏が「何か乗り越えなければいけないものがあるのだろうか」と考察し、「I’ll be over me」はいつ終わるのだろうか、と以下の記事で書いたのだった。
※角松敏生はなぜ王道ポップス・AORを作らなくなったのか? – ”角松敏生”というアイデンティティ問題
果たして彼の中で「I’ll be over me」が完了したのかどうかは定かではない。しかし何らかの心境の変化があって、王道のポップス路線に回帰したのではないか、とは思う。
実際のところ、彼はMIRADシリーズを作り終えてから、音源リリースはしないかもと語っていた時期もあったように記憶している。
しかし「Contemporary Urban Music (C.U.M)シリーズ」と言う、言ってしまえば、彼が凍結前に喜々として作っていた音楽の再構築のテーマが打ち立てられたのだ。
5年ほどリリースが空くこともあったのに、『MAGIC HOUR 〜Lovers at Dusk〜』がリリースされてから、半年に1作ほどのハイペースでのリリースになっている。
彼がMIRADシリーズに没頭していた頃、海外では日本のシティポップ再評価の機運が高まり、角松氏の過去の作品もかなり取り上げられることがあった。
2020年には角松氏が提供した楽曲のオムニバス作品『角松敏生ワークス –GOOD DIGGER』もリリースされ、ライナーノーツでは角松氏にもコメントが求められていた。
しかし彼は今になって過去の作品が取り上げられることに、それほど好感を持っていないかのような書きぶりだったのが印象的だった。
結果的には再評価の波がひと段落したタイミングで、「Contemporary Urban Music (C.U.M)シリーズ」を打ち立てる、ひねくれたところが角松氏らしい、とも思ったのだった。
とは言え、そんなひねくれた部分すら感じさせない、王道の角松サウンドに回帰しているのが本作『Forgotten Shores』である。
これを待っていたと言う感想以外思いつかない、まさに角松サウンドの王道である。雰囲気としては『Summer 4 Rhythm』に似ていると言う声もあり、確かにそう感じるところがある。
ただサウンドの作り方としては、80年代の角松氏のエッセンスが散りばめられており、それらを再構築しようと言う意図が強く感じられる。
アルバム前半の「Blue Swell」~「Beach Road」や「Forgotten shores」などは、3rd『ON THE CITY SHORE』や、それ以前の作品の雰囲気を感じさせる。
また「Domino City」「Slave of Media」は4th『AFTER 5 CLASH』~6th『TOUCH AND GO』辺りのダンスミュージック要素が強い。
そして「TSUYUAKE」は7th『BEFORE THE DAYLIGHT』風であり、ある意味で80年代の角松サウンドを総括するような作品と言ってもいいかもしれない。
ただ違う点で言えば、当時のような「売れる曲」「売れるメロディ」とは異なる感触もある。つまりアルバム主体の音楽(アルバムオリエンテッド)を作っている印象ではある。
しきりにヒット曲がない、と嘆いていた角松氏だったが、音楽シーンも随分と変わって、かつての時代の”ヒット曲”という概念も変わってきたところである。
今後どのような作品を制作するのかも注目であるが、ひとまず80年代の自身の音楽的な総括をここまで行う作品は、あまりなかったように思える。
彼の中でのアイデンティティと言うのか、音楽人としての折り合いのようなものがついたのか、結果的にはストレートに角松サウンドらしい爽快な作品になったと思える。
※【初心者向け】”はじめてのアルバム” – 第9回:角松敏生 各年代のおすすめ名盤を1枚ずつ選出!
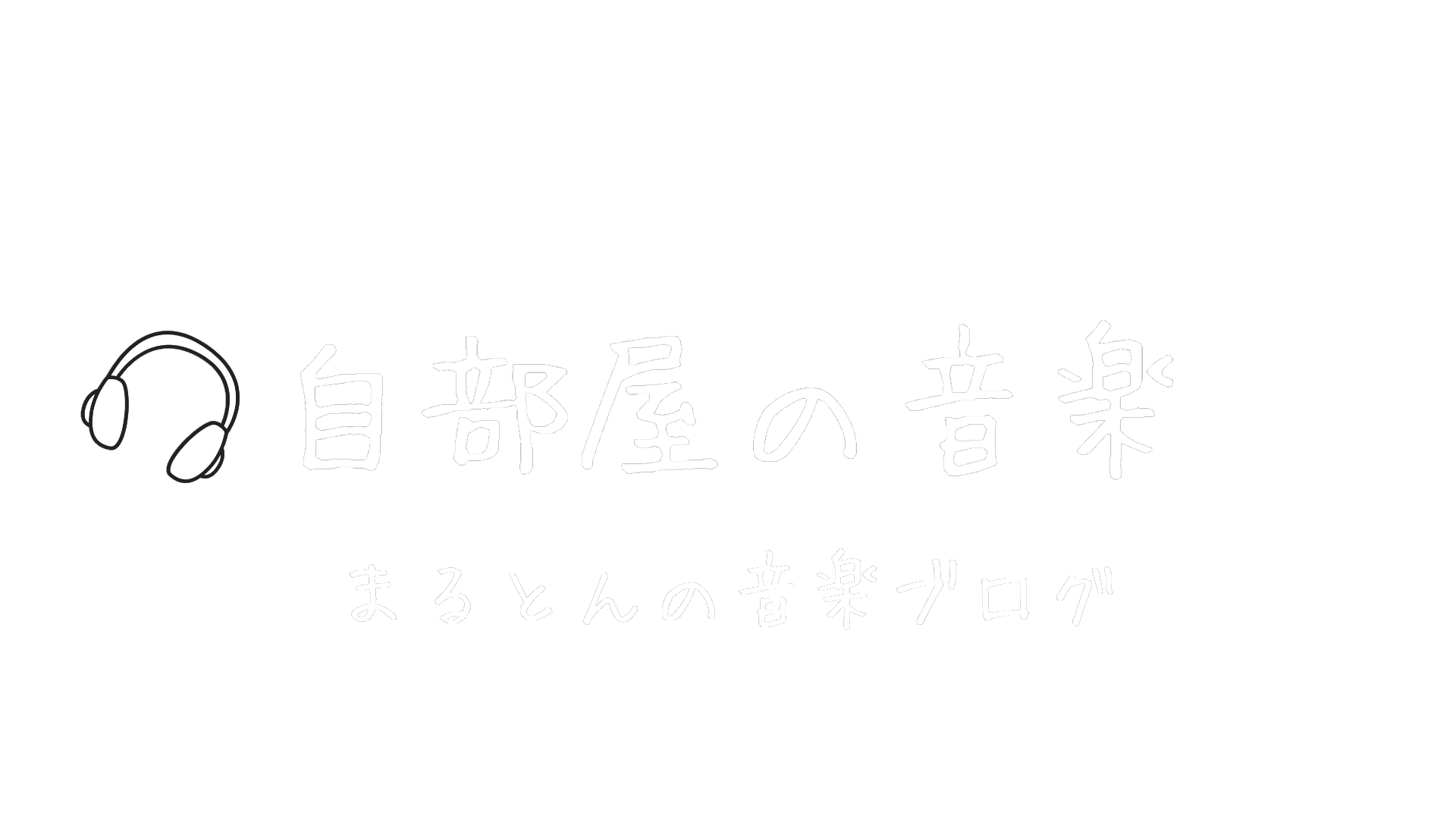























コメント